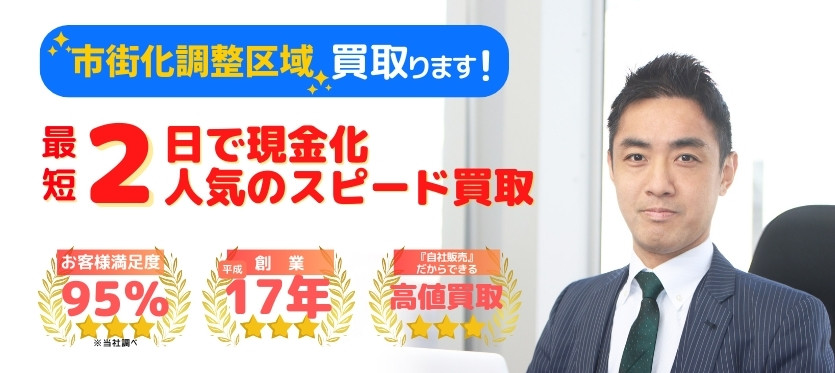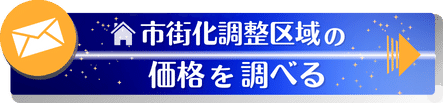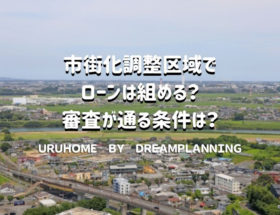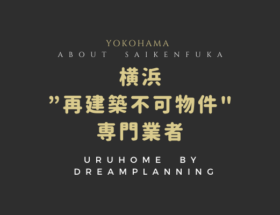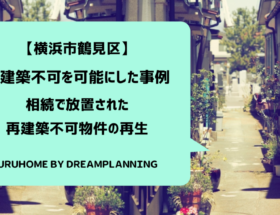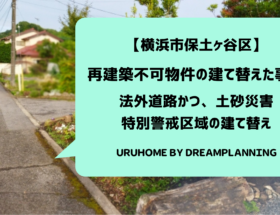「市街化調整区で開発許可をとりたいんだけど……」
ニッチな不動産URUHOMEでおなじみ当社ドリームプランニングでは、市街化調整区域の不動産をお持ちの地主さんから、開発許可について多くのご相談をいただいております。
今回は市街化調整区域で建物を建てるために必要な開発許可がとれるのか?
開発許可が必要/不要なケースや申請手続き・費用などを分かりやすく徹底解説してまいります!
【この記事は、このような方におすすめです!】
- 市街化調整区域で開発許可をとりたい方
- 市街化調整区域や開発許可など不動産知識を深めたい方
- 特に市街化調整区域の開発許可でお悩みの方
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の市街化調整区域や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に買取りするため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てたく「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 市街化調整区域の開発許可は?
- 市街化調整区域の開発許可申請手続きは?
- 【予備知識】開発許可とは何か?
- 【予備知識】市街化調整区域とは何か?
- 市街化調整区域の不動産を売却する方法
- 市街化調整区域の開発許可でお悩みならURUHOMEへご相談を
1.市街化調整区域の開発許可は?
建物を建てるためには、いきなり建て始めるのではなく、土地を整備する必要があります。
この土地整備や宅地造成を開発行為と言いますが、この開発行為について都道府県知事から許可をもらわないといけません。これが開発許可です。
また、市街化調整区域に区分された土地については開発に制限がかけられています。
開発許可や市街化調整区域についてはあとで詳しく解説しますが、ここでは結論を話すための前提として、サラッとふれるにとどめておきましょう。
- 1-1.原則的に市街化調整区域の開発許可は認められない(ただし例外あり)
- 1-2.開発許可が必要な特例要件(都市計画法第34条1~13号)
- 1-3.開発審査会提案基準(都市計画法第34条14号)
- 1-4.開発許可が不要な除外規定(都市計画法第29条1項2号ほか)
1-1.原則的に市街化調整区域の開発許可は認められない(ただし例外あり)
後ほど【予備知識】編で詳しく解説しますが、結論から言って原則的に市街化調整区域では開発許可が認められません。
市街化調整区域は「(市街化≒開発)を(調整≒抑制)すべき区域」だからです(都市計画法第7条3項より意訳)。
しかし、市街化調整区域であっても開発許可が認められる例外があるので、それらを確認していきましょう。
1-2.開発許可が必要な特例要件(都市計画法第34条1~13号)
都市計画法によると、市街化調整区域の開発許可を認める要件が第34条の各号(1~14号。途中に8の2号が挿入されているため、全部で15つ)に定められています。
都市計画法 第34条 第1~13号 【クリックで全文表示】
(開発許可の基準)
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為
六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
十 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。)
十四 略(後述)
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
長文かつややこしいので、かみ砕いておきましょう。
第34条 市街化調整区域で開発行為をする場合、以下にあてはまらなければ開発許可を出してはいけません。
(1)現地住民の利便や公益上必要な店舗や施設などを建てる
(2)現地の鉱物資源や観光資源などを活用する施設を建てる
(3)温度・湿度・空気など特別な条件が必要な施設を建てる
(4)農林水産業に必要な施設(処理・加工・貯蔵等)を建てる
(5)特定農山村地域で農林業を活性化させる施設を建てる
(6)都道府県が国等と一体で中小企業の連携・共同に必要な施設を建てる
(7)既に操業している工業施設の生産性を高める施設を建てる
(8)危険物の貯蔵や処理に必要な施設を建てる
(8の2)災害危険区域等にかかる危険物関連施設を移築する
(9)市街化区域に建てることが困難または不適当な施設を建てる
(10)地区計画または集落地区計画の地区の活性化に必要な施設を建てる
(11)市街化区域に近い一定範囲に50軒の建物が連坦している地域に建てる
(12)周囲を市街化させず、かつ市街化区域には不適切な防災施設を建てる
(13)市街化調整区域の指定前から土地を持っていた者が権利の行使として建てる
※分かりやすさを優先しているため、細かなニュアンスが抜けている場合があります。
一般の方には馴染みの薄い項目が多いですが、これらのいずれかに該当していれば市街化調整区域の開発許可が下りることになります。
ただし都市計画法の解釈は自治体の担当者によって異なるため、思い込みで決めつけてしまわず、市街化調整区域を管轄する自治体窓口で事前に相談しましょう。
1-3.開発審査会提案基準(都市計画法第34条14号)
都市計画法第34条の開発許可条件について第13号まで解説してきましたが、最後の第14号にはこんなことが規定されています。
都市計画法 第34条
前略
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
【意訳】これまで挙げた13号までのほか、都道府県知事が開発審査会と協議して認めた案件については、開発許可を出します。
いきなり出てきた開発審査会とは、都市計画法第78条に規定された組織で、都道府県等に設置されるものです。
都市計画法
七十八条 第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
2~8 略
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
この開発審査会が市街化調整区域の開発許可を認める基準を開発審査会提案基準と言い、自治体によって異なります。
1-3-1.自治体ごとの開発審査会提案基準(神奈川県各自治体)
市街化調整区域の開発許可を認める開発審査会提案基準は、自治体によって異なるため、そのすべてを網羅することはできません。
なので今回はドリームプランニング本社のある神奈川県を例に、市街化調整区域に開発許可が下りる建物を自治体別で見ていきましょう。
| 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 厚木市 | 海老名市 | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 藤沢市 | 大和市 | 神奈川県 | |
| 公益上必要な建物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 農家の分家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 既存建築物の増築・建て替え | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特別養護老人ホーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 市街化調整区域となった時点で宅地(建て替え) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 社会福祉施設・学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 幹線道路沿線の特定流通業務施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 障害者グループホーム | 〇 | |||||||||
| 医療施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 研究施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 神社仏閣・納骨堂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 従業員宿舎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※施設は主なもののみ取り上げました。他にもあるので、必要に応じてご確認ください。
一番右に神奈川県開発審査会提案基準を載せていますが、開発審査会を置いていない自治体については神奈川県の開発審査会提案基準が準用されます。
※参考:都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引について-神奈川県ホームページ
1-4.開発許可が不要な除外規定(都市計画法第29条1項2号ほか)
市街化調整区域でも開発許可の不要な除外規定が設けられています。
除外規定については都市計画法第29条1項各号(1~11号)に規定されているので、こちらも確認しておきましょう。
都市計画法 第29条1項 【クリックで全文表示】
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 3 略
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
市街化調整区域に関係するのは主に第2・3・10・11号。かみ砕いて解説します。
2号 農林水産業に用いる施設か、従事者の住居は開発許可が不要です。
3号 駅舎や鉄道・図書館・公民館・変電所など公益上必要な施設は開発許可が不要です。
10号 非常災害の応急処置として必要な工事は開発許可が不要です。
11号 通常の管理やちょっとした行為については、開発許可が不要です。「通常の管理」等について具体的には都市計画法施行令第22条で定義されています。
これらの開発行為には開発許可が不要とされますが、後からトラブルにならないよう、具体的な事案については自治体で確認するのがおすすめです。
2.市街化調整区域の開発許可申請手続きは?
前章では市街化調整区域で開発許可が必要/不要なケースについて解説してきました。
では市街化調整区域の開発許可が必要となった場合、どのような流れで手続きを進めていくのでしょうか。
市街化調整区域の開発許可申請は自治体によって若干手続きが異なるため、今回はドリームプランニングの本社がある横浜市を例に解説してまいります。
- 2-1.市街化調整区域で開発許可を申請する流れは?(横浜市の例)
- 2-2.市街化調整区域で開発許可を申請する費用は?(横浜市の例)
- 2-3.市街化調整区域で開発許可を申請する技術基準は?(横浜市の例)
- 2-4.市街化調整区域で開発許可を申請する立地基準は?(横浜市の例)
- 2-5.市街化調整区域の開発許可申請に関する相談はどこでできる?
2-1.市街化調整区域で開発許可を申請する流れは?(横浜市の例)
市街化調整区域の開発許可申請の流れを細かく解説すると非常に長くなってしまうため、大まかにとらえておきましょう。
事前に住民や公共施設の管理者への説明を行い、意見を集約して開発事業計画書を横浜市建築局へ提出。それをたたき台に協議を重ね、はじめて開発許可申請書の提出にこぎつけます。
開発面積によっては市長の同意(横浜市開発事業の調整等に関する条例。500㎡以上)も必要となり、より手続きが煩雑化するかも知れません。
建築局内での審査を経て許可されれば開発許可通知書を手にできますが、これが不許可になると開発審査会への不服申し立て(都市計画法第50条)や裁判所への取消訴訟も選択肢となるでしょう。
市街化調整区域の開発許可申請にかかる期間は、市長の同意が必要なケースでは約3ヶ月、その後スムーズに進むと2~3週間で許可が出ると言います。
全体的に3.5~4ヶ月程度かかると見ていいでしょう。
※参考:都市計画法による開発許可の手引
※参考:Q2-2 開発許可までどのくらい手続期間がかかりますか 横浜市
2-2.市街化調整区域で開発許可を申請する技術基準は?(横浜市の例)
市街化調整区域の開発許可にかかる技術基準は全15章にわたって定められており、これらを満たさなければなりません。
主な基準としては(1)予定建築物等の用途(2)公共の用に供する空地(3)排水施設(4)給水施設(7)公益的施設(8)安全上必要な措置(9)樹木の保存等の措置(10)申請者の資力信用(11)工事施工者の能力(12)開発行為の妨げとなる権利者の同意(13)敷地・街区(14)景観計画……など様々です。
※参考:都市計画法による開発許可の手引 横浜市『技術基準編』
2-3.市街化調整区域で開発許可を申請する立地基準は?(横浜市の例)
市街化調整区域の開発許可にかかる立地基準は全5章にわたって定められています。
主な基準としては(1)建築物の高さ等(2)建築物の連たん(3)都市計画法第34条各号の運用(4)横浜市開発審査会提案基準(4)第二種特定工作物(5)都市計画法第29条ただし書……などの基準があるので、これらを満たしていきましょう。
※参考:都市計画法による開発許可の手引 横浜市『立地基準編』
2-4.市街化調整区域で開発許可を申請する費用は?(横浜市の例)
市街化調整区域の開発許可申請にかかる費用は、開発区域面積によって変わってきます。
| 開発区域面積 | 自己の居住用 | 自己の事業用 | その他 |
| 1,000㎡未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
| ~3,000㎡未満 | 23,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
| ~6,000㎡未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
| ~10,000㎡未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
| ~30,000㎡未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
| ~60,000㎡未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
| ~100,000㎡未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
| 100,000㎡以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
2-5.市街化調整区域の開発許可申請に関する相談はどこでできる?

市街化調整区域の開発許可申請について、分からないことは自治体の市街化調整区域担当窓口で相談するのが一番早くて確実です。
が、細かな数字や耳なれない専門用語が飛び交うため、話を聞いてもよく分からない方も少なくないでしょう。
そういう時は、不動産のプロに相談するのもいいでしょう。
市街化調整区域の不動産取引に特化しているドリームプランニングでもご相談を承っております。
「市街化調整区域の開発許可について、役所で説明を聞いたけど、さっぱり分からなかった」という方はご連絡くださいませ。

3.【予備知識】開発許可とは何か?
さて。ここまで市街化調整区域の開発許可について解説してきましたが、中には
「そもそも開発許可って何?」
とよく分からないまま話を進めてしまった方もいるのではないでしょうか。
しかしご安心ください。ここではそもそも開発許可とは何か?分かりやすく解説していきます。
3-1.都道府県知事による開発行為の許可(都市計画法第29条)
開発許可を一言にまとめると「都道府県知事等による開発行為の許可」です。
都市計画法第29条に規定されているので、その条文を見てみましょう。
都市計画法 第29条 【クリックで全文表示】
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
……長いですね。全部読まなくても問題ありません。
要するに「開発行為(次に解説します)をしたい時は、都道府県知事などの許可をとってね。ただし許可が要らない例外あり」ということになります。
3-2.開発行為とは何か?(都市計画法第4条12項)
開発許可とは「都道府県知事等による開発行為の許可」と解説しました。
その開発行為とは何なのか?都市計画法第4条12項に定義されているので、その条文を確認しましょう。
都市計画法
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
(定義)
第4条 1~11 略
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13 以下略
堅苦しい言い回しをかみ砕くと、「建物や特定工作物を建てるために土地をいじる」ことを開発行為と言います。
「土地をいじる」と言ってもピンと来ないかも知れないので、具体例を見ていきましょう。
- 土地の「区画」を変更する
土地を区切る(区画する)公共設備、例えば道路や水路などを新設・廃止・移設することを言います。 - 土地の「形(形状)」を変更する
盛土(もりど。土を盛ること)や切土(きりど。斜面を切り取ること)によって土地の形状を(建物を建てやすく、平らに)変更することを指します。 - 土地の「質」を変更する
宅地以外の土地(地目。土地の性質)を宅地に変更すること(地目変更)を言います。
基本的な考え方はこの通りですが、より具体的な運用については各自治体の条例や開発指導要綱などで定めていることが多いので、市街化調整区域の開発許可を申請する時は自治体で確認しましょう。
3-3.市街化調整区域の開発許可まとめ
- 開発許可とは「知事等による開発行為の許可」
- 開発行為とは「建物等を建てるために土地の形状や性質をいじること」
- 市街化調整区域の開発許可をとる時は「開発許可が必要な特例要件」「開発審査会提案基準」「開発許可の不要な除外規定」の大きく3ルートがある(先ほど解説済み)
以上、開発許可の基礎知識についてざっくり解説してきました。
先ほど言及したように、実際の運用については自治体ごとに異なる点も多いため、市街化調整区域の開発許可をとろうとする時は自治体の担当者に相談するのが確実です。
4.【予備知識】市街化調整区域とは何か?
せっかくなので、市街化調整区域についても軽く解説しておきましょう。開発許可よりは聞いたことがある言葉かも知れませんね。
4-1.市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条3項)
市街化調整区域は都市計画法第7条3項に規定されています。
都市計画法 第7条
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域。調整≒抑制つまり「市街化したくない区域」と言えるでしょう。
行政当局としては、なるべく開発してほしくない事情があるため、開発行為については大きく制限をかけているのです。
(無秩序に家を建てられるなどすると、例えば山奥に一軒だけ建った家のためにインフラを整備しなければならないなど、維持コストがかさんで行政予算を圧迫してしまいます)
とりあえず「市街化調整区域は色々めんどくさい(制約がかけられている)土地」と覚えておけば問題ありません。
4-2.市街化調整区域以外の区域区分(市街化区域・非線引き区域)
都市計画法第7条では、市街化調整区域の他にも市街化区域が規定されています。こちらは「既に開発されている、または積極的に開発していきたい土地」程度の意味です。
それ以外に、市街化区域でも市街化調整区域でもない「非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)」があり、以上3種類を区域区分と言います。
【区域区分まとめ】
- 市街化調整区域……なるべく開発してほしくない区域
- 市街化区域……なるべく開発してほしい区域
- 非線引き区域……どっちにも線引きされていない区域
※非線引き区域はケースバイケースですが、「市街化調整区域よりは規制が緩めだけど、市街化区域よりは規制が厳しめ」なことが多いです。
5.市街化調整区域の不動産を売却する方法
さて。先ほど解説した通り、市街化調整区域は取り扱いが正直めんどくさいです。
だから当社にも「市街化調整区域を手放したい・売却したい」というご相談を多数いただくのですが、市街化調整区域を売却するにはどこで相談するのがいいでしょうか。
5-1.市街化調整区域は一般の不動産会社では敬遠されがち
不動産のことなら、不動産会社にお願いしたい。多くの方が、そう思われることでしょう。
しかし一般の不動産会社は利益を最優先するため、取り扱いが面倒な市街化調整区域の物件は難色を示すことがほとんどです。
不動産会社が受け取れる報酬金額は法律で上限が決まっているため、同じ金額ならスムーズに取引できる市街化区域などを取り扱いたい事情は解りますよね。
「いや~、この物件は難しいですね……」
既にそんなことを言われてしまった方も、少なくないのではないでしょうか。
5-2.市街化調整区域の専門業者に買取りを依頼
一般の不動産会社で渋られてしまっても、まだ手はあります。市街化調整区域で悩んだ時は、買取専門業者への売却も視野に入れたいところです。
市街化調整区域の買取専門業者は、買取りした市街化調整区域に付加価値を加え、再販することで利益を得ています。
また、市街化調整区域の開発許可申請など面倒な手続きについても独自のノウハウを持っているため、スムーズに売却できるでしょう。
加えて、仲介ではないので仲介手数料をとられないのも買取専門業者の魅力と言えます。ただし中には買取りを謳っていても他社へ仲介するだけの業者もあり、その場合は仲介手数料が発生してしまうため、自社買取りをしているか事前にしておきましょう。
6.市街化調整区域の開発許可でお悩みならURUHOMEへご相談を
以上、市街化調整区域の開発許可について、様々な角度から解説してきました。
市街化調整区域の開発許可をとるのは非常に大変で、一人で全部やるのは難しいと思います。
もし市街化調整区域の開発許可でお悩みでしたら、いっそ売却してしまうのも一つの手段。その時は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年の創業以来、神奈川・東京を中心に市街化調整区域のニッチな不動産を多数買取りしてまいりました。
永年の不動産取引で培ったノウハウを、今回のお悩み解決にも役立てられると思います。
市街化調整区域の買取査定はもちろん完全無料。最速のケースでは、ご依頼から2時間で査定完了、2日で買取できた事例もございました。
持て余している市街化調整区域の物件のスピード売却&現金化をご希望でしたら、ぜひ一度ドリームプランニングまでご相談くださいませ。