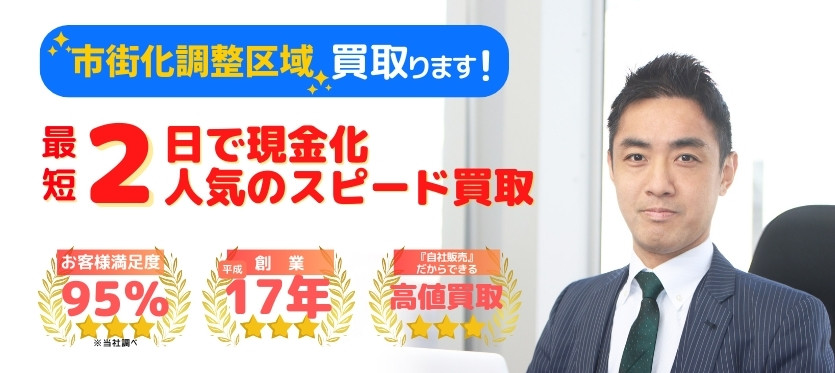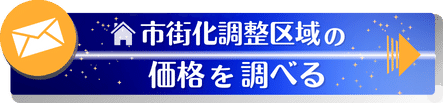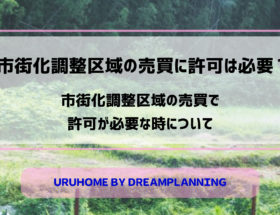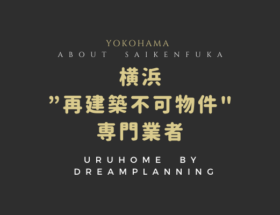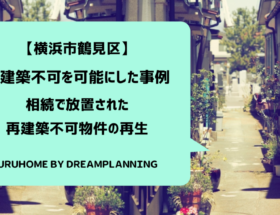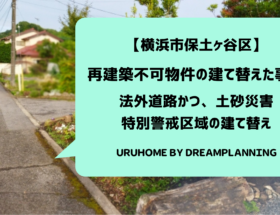「土地を相続したけど、市街化調整区域だから建物が建てられない」
「市街化調整区域で建築許可をとる方法はないの?」
市街化調整区域はじめニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、お客様から多くのご相談をいただいております。
そこで今回は悩める皆さんの参考になるよう、市街化調整区域で建築許可をとるための方法を徹底解説!
市街化調整区域で建築許可がとれる条件や手続きの流れ・必要書類に費用などをレクチャーして参ります。
【この記事は、こんなお悩みを持った方におすすめです!】
- 市街化調整区域で建築許可をとりたい方
- 市街化調整区域に建物を建てたい方
- 市街化調整区域の不動産を売却したい方
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の市街化調整区域や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に買い取る為、多数の相談を頂いてまいりました。
当サイトURUHOMEは、私達のノウハウが不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
市街化調整区域のお悩みがございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 建築許可とは何か?(都市計画法)
- 市街化調整区域で建築許可が不要なケースは?
- 市街化調整区域で建築許可がとれる条件・建物は?
- 市街化調整区域で建築許可をとらずに建築するとどうなる?
- 市街化調整区域で建築許可を申請する手続きは?
- 市街化調整区域で建築許可を申請する費用は?
- 市街化調整区域で建築許可が下りるまでの期間は?
- 市街化調整区域の物件を売却する方法は?
- 市街化調整区域でお悩みならURUHOMEへご相談を
1.建築許可とは何か?(都市計画法)
冒頭で「市街化調整区域で建築許可をとる」と言いましたが、建築許可とはなんでしょうか。
ここで言う建築許可とは、都市計画法で定められた市街化調整区域における建築行為の許可を言います。
1-1.市街化調整区域とは(都市計画法第7条3項)
都市計画法 第7条
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
市街化調整区域とは都市計画法で定められた区域区分の一つで、市街化を抑制すべき区域とされています。
市街化を抑制すべき事情から、基本的に家を建てるなどの建築行為が規制されているのです。
なお、区域区分にはもう一つ市街化区域(都市計画法第7条2項)があります。こちらは(1)既に市街化している区域、又は(2)今後積極的に市街化したい区域です。
都市計画法 第7条
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
そして市街化調整区域でも市街化区域でもない非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)が存在します。
1-2.建築行為とは(建築基準法第2条1項13号)
建築基準法 第2条1項
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
建築行為とは、建築をすること。そのままですね。
ではその建築とは、建築基準法第2条1項に定められている通り、建物を新築(新たに建てる)・増築(建て増しする)・改築(建て直しする)・移転(移築する)することを言います。
ちなみに土地自体を整備することを開発行為と言いますが、今回は既に開発(整備)された土地の上に建物を建築するケースで考えていきましょう。
1-3.建築基準法にも「建築許可」がある?
ところで建築許可と呼ばれるものは、都市計画法だけでなく建築基準法にもあります。
都市計画法の建築許可と、建築基準法の建築許可はどのような違いがあるのか、横浜市建築局調整区域課に問い合わせました。
「建築基準法にもとづく一般的な建築行為の許可は、建築許可ではなく『建築確認』と読んでいます。建築基準法で『建築許可』と言う場合、特例解除など特殊なケースでのみ用いるため、あまり一般的ではありません」
なので、一般的な感覚で「建築許可」と呼ぶ場合、都市計画法にもとづく建築許可と理解しておけば事足りるでしょう。
2.市街化調整区域で建築許可が不要なケースは?
今回は市街化調整区域で建築許可をとる方法について解説していきますが、そもそも建築許可が不要なケースもあります。
ここでは都市計画法第29条1項2~3号と同法第43条1項ただし書きに該当するケースを解説していきましょう。
2-1.市街化調整区域で建築許可が不要なケース①都市計画法第29条1項2~3号
都市計画法 第29条【クリックで詳細表示】
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 略
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 以下略
条文が長いのでかみ砕いて解説しましょう。
(1)農業・林業・漁業に使う施設や従事者の住居の建築は、開発許可と建築許可が不要
(2)駅舎や鉄道施設、図書館・公民館・変電所その他交易上必要な建物についても同じ
第29条では開発行為についてしかふれていませんが、次に出てくる第43条でこれらの建築行為について補完しています。
2-2.市街化調整区域で建築許可が不要なケース②都市計画法第43条1項ただし書き
建築基準法 第43条【クリックで全文表示】
第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2(以下略)
ちょっと分かりにくいので、これもかみ砕いて解説します。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けていない場所では、以下の例外を除いて建築行為をしてはならない。
例外1・都市計画事業として行う建築物の建築行為
例外2・非常災害時の応急措置として行う建築行為
例外3・仮設建築物を新築する建築行為
例外4・同法29条1項9号の開発行為や開発行為が行われた区域内の建築行為
例外5・通常の管理行為、軽易な行為など
これら5パターンについては建築許可なしで建築が可能です。ただし、皆さんのケースがこれらに当てはまるかの判断は自治体によります。
そのため自己判断で決めつけてしまわず、あらかじめ自治体の窓口で相談しておきましょう。
3.市街化調整区域で建築許可がとれる条件・建物は?
市街化調整区域で建築許可をとるためには、都市計画法第34条に規定される条件を満たす必要があります。
また、建築許可はどんな建物でもとれる訳ではなく、許可される建物の種類に制限があるので覚えておきましょう。
3-1.都市計画法第34条の規定
都市計画法第34条 【クリックで全文表示】
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為
六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
十 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。)
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
クリックで条文を開いた瞬間「うわっ……こんなの理解できない。無理」と思った方も多いことでしょう。でも大丈夫。
要するに「以下の条件を満たす建物等については市街化調整区域でも例外的に建築許可を出す可能性がありますよ」ということです。

【市街化調整区域で許可が出る可能性がある条件】
- ケース1:市街化調整区域で現に暮らしている方に向けたサービス等を提供する建物
- ケース2:市街化調整区域内の鉱物・観光資源などを活用するための建物
- ケース3:温度・湿度・空気など特別条件を満たす必要がある建物
- ケース4:農業・林業・漁業で収穫物の処理や貯蔵、加工に必要な建物
- ケース5:特定農山村地域における農林業等を活性化させるための建物
- ケース6:都道府県が国等と連携して中小企業を活性化させるための建物
- ケース7:現時点で市街化調整区域内にある工場施設と関連性の高い建物
- ケース8:危険物の貯蔵または処理に必要で、かつ市街化区域にはおきたくない建物
- ケース8-2:災害危険区域等からケース8の建物を移転させる場合
- ケース9:これらのほか、市街化区域に建てるのは難しいor不適当な建物
- ケース10:地区計画や集落地区計画にそって建てられる建物
- ケース11:近くに50軒程度の建物が密集(連坦)している場所に建てる建物
- ケース12:建てても市街化調整区域の現状に影響が少ない建物
- ケース13:市街化調整区域に指定される前から現地で建てようとしていた建物
- ケース14:以上のほか、都道府県知事が開発審査会との協議により認めた建物
実にいろいろありますね。これらが市街化調整区域でも建築許可が下りる可能性のある建物となるのです。
ただ、実際にこれらすべてを認めている自治体は少ないかも知れません。自治体によってどれを許可する・許可しないは自由なのです。
条文は「これらに当てはまらないものは許可してはならない」と書いてあり、「当てはまるものは許可しなければならない」とは書いていません。
例えばドリームプランニングのある神奈川県横浜市では都市計画法第34条のうち、許可を出す可能性を示しているのは1号・9号・14号に限られています。
※参考:市街化調整区域内の開発・建築 横浜市
詳しくは建築許可をとりたい市街化調整区域を管轄している自治体の窓口で確認しましょう。
3-2.開発審査会提案基準(都市計画法第34条1項14号)
先ほど挙げた15の建築許可基準のうち、最後にあった「都道府県知事が開発審査会の議を経て~」とは何でしょうか。
この開発審査会とは、都市計画法に基づいて市街化調整区域での開発許可や建築許可を審査するために自治体で設立された組織です。
開発審査会との協議によって認められた建築許可等の特例措置を開発審査会提案基準と言い、例えば神奈川県横浜市では以下のようなものが示されています。
【横浜市開発審査会提案基準の例】
- 第3号(公益上必要な建物に類する建築許可の特例措置)
- 第4号(農家等の分家住宅に関する建築許可の特例措置)
- 第5号(土地収用に協力した者の移転先住居に係る特例措置)
- 第6号(既存建築物の増築、建て替え等に係る特例措置)
- 第12号(屋外運動施設内において行う建築許可の特例措置)
- 第14号(市街化調整区域の指定時点で建築行為がされていた場合の特例措置)
- 第15号(道路位置指定等で造成された土地の建築許可の特例措置)
- 第19号(市街化調整区域の指定以前から土地を所有していた場合の特例措置)
- 第20号(特養ホーム及び介護老人保健施設の建築許可に係る特例措置)
- 第22号(市街化調整区域の指定時点で袋地である宅地に対する特例措置)
- 第23号(墓園における付属建築物の建築許可についての特例措置)
- 第27号(社会福祉施設・学校等の建築許可に関する特例措置
- 第28号(幹線道路沿いにある特定流通施設の建築許可に関する特例措置)
- 第29号(障害者グループホームの建築許可に関する特例措置)
- 第30号(資材置き場など土地利用の管理建物に係る建築許可の特例措置)
- 第31号(土地収用対象建物に代わる建物の建て替え等に係る特例措置)
- 第33号(医療施設の建築許可に係る特例措置)
※ここに挙げた提案基準の中には開発行為がかぶっているものもありますが、今回はなるべく分かりやすさ重視で建築許可に関する部分だけ抜き出しています。
詳しくは、市街化調整区域の物件を管轄する自治体窓口で確認するようにしましょう。
4.市街化調整区域で建築許可をとらずに建築するとどうなる?
これを読んでいる皆さんの中にはいらっしゃらないと思いますが、もし市街化調整区域で建築許可をとらずに建物を建ててしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
恐らく一生経験することはないでしょうが、都市計画法に規定されている罰則は以下の通りです。
建築基準法 第92条
第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~二 略
三 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者
四~六 略
七 第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
(以下略)
市街化調整区域で建築許可をとらずに建築物を建ててしまうと、50万円以下の罰金刑に処されてしまうのですね。
この時、建築許可をとらずに建ててしまった建物について都市計画法では特に言及がありません。
しかし建築基準法に抵触する場合、同法第9条の規定によって除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限が命じられる可能性もあります。
建築基準法 第9条
(違反建築物に対する措置)
第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(以下略)
都市計画法に違反している(建築許可をとっていない)けど、建築基準法には合致している(建築確認はとっている)、などというケースは考えにくいでしょう。
建築許可等をとらない違反建築物は常に除却命令等のリスクに怯えることとなります。

5.市街化調整区域で建築許可を申請する手続きは?(神奈川県の例)
さて、ここまで市街化調整区域で建築許可が必要な場合と不要な場合などについて紹介してきました。
それでは、実際に市街化調整区域で建築許可を申請するための手続きについて、ドリームプランニングがある神奈川県の例で解説していきましょう。
※参考:都市計画法第43条の規定に基づく建築許可申請の手引 神奈川県
5-1.建築許可の申請前にする手続き
5-1-1.市街化調整区域での建築計画についての事前相談
市街化調整区域で建築許可を申請する時は、土木事務所で事前相談を受けてください。
相談窓口は建築許可を申請する市街化調整区域を管轄する土木事務所となります。
【土木事務所の一覧:神奈川県の例】
横須賀土木事務所:逗子市・三浦市・葉山町
平塚土木事務所:伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町
小田原土木事務所:箱根町・真鶴町・湯河原町
相模原土木事務所:座間市
厚木土木事務所:海老名市・綾瀬市・愛川町
松田土木事務所:南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町
※土木事務所の名前はあくまでも地域名であり、例えば横須賀土木事務所は横須賀市を管轄していません。
ここにある以外の市については、各市に相談窓口が設けられています。
【政令市】横浜市・川崎市
【中核市】横須賀市・相模原市
【特例市】平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市
【事務処理市】鎌倉市・藤沢市・秦野市
5-1-2.市街化調整区域で建築許可申請を行う敷地内権利者の同意
市街化調整区域の建築許可を申請する際、その敷地について所有権や借地権などをもっていない場合、敷地の所有権をもっている方の同意を得ていなければなりません。
都市計画法 第33条1項14号
十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
他人様の土地について、勝手に建築許可をとって建築を進めてしまったら、後でトラブルになることは必至ですからね。
建築許可の申請時に同意書が必要になるため、同意した内容は必ず書面にまとめておきましょう。
※参考:開発許可等申請にかかる様式-神奈川県ホームページ
5-1-3.他法令等との関係
市街化調整区域で建築許可をとるためには、都市計画法だけ守っていればいい訳ではありません。
建築基準法にもとづく建築確認申請(よく確認申請などと言います)はじめ、農地法や風致地区条例・首都圏近郊緑地保全法・自然公園法など諸法律にもとづいた許認可が必要となる場合もあります。
どの法律や条例にかかってくるかは市街化調整区域を管轄する自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
5-2.建築許可の申請手続き
市街化調整区域で建築許可をとるための申請手続きは非常に煩雑です。
役所などへ通うことになりますが、何度も無駄足を踏まないよう事前に確認して、かかる手間と時間をなるべく減らすよう心がけましょう。
5-2-1.申請書の提出先等
事前準備がととのったら、建築許可申請書に必要書類を添付して、市街化調整区域を管轄する市・町を経由で土木事務所に提出します。
建築許可申請書の提出部数は、正本1部と副本2部です。
5-2-2.申請に必要な図書等
- 建築物の新築、改築又は用途の変更許可申請書
- 建築物(等)概要章
- 委任状
- 申請の理由等
- 位置図
- 付近見取図(1/2,500以上)
- 公図の写し(登記所保管のものに限る)
- 敷地内権利者の同意書
- 土地登記事項証明書
- 敷地現況図(1/300以上)
- 土地利用計画図(配置図・1/300以上)
- 建築物平面図(1/100以上)
- 建築物立面図(1/100以上)
- その他、土木事務所長が必要と見とめる書類
- 排水計算書(雨水、排水の排出ができるか判断が難しい場合)
5-2-3.その他の添付書類等
市街化調整区域の建築許可は、許可基準の別によって必要な書類も変わってきます。
そのすべてを網羅することはできないため、代表的なものをピックアップしました。
詳しくは、所管の土木事務所等でご確認ください。
【農家分家住宅の建築許可に必要な添付書類の例】
- 分家申告書
- 贈与証書
- 耕作証明
- 戸籍謄本
- 住民票
- 農地転用許可申請の受理証明書
- 現住所の証明書
- 資金計画書
- 分家住宅を他人に貸借、転売しない旨の念書……など
【土地収用で移転する場合の建築許可に必要な添付書類の例】
- 収用事業であることの証明書の写し
- 収用地と移転地との比較対象表
- 選定結果報告書
- 付近見取図(1/2,500以上)
- 公図の写し(登記所保管のものに限る)
- 土地登記事項証明書
- 収用地の丈量図
- 敷地現況図(1/300以上)
- 土地利用計画図(配置図)
- 収用建築物平面図(1/100以上)
【既存宅地の建築許可に必要な添付書類の例】
- 市街化調整区域に係る線引きの日以前から宅地であったことを証する書類
- 連たん図
- 周辺建築物リスト
5-3.その他の手続き
5-3-1.許可済の標識
市街化調整区域の建築許可が受けられたら、建築許可に係る建築等を行う工事現場の見やすい場所に、許可済みの標識(都市計画法による建築など許可済の標識)を掲示しましょう。
標識には以下の事項を明記します。
(1)建築許可の年月日
(2)建築許可の許可番号
(3)建築許可を出した者
(4)建築許可を受けた者の住所・氏名
(5)工事施工者の住所・氏名
(6)建築・建設に係る土地の所在
(7)建築物などの用途
掲示期間は建築行為の工事完了まで。標識のサイズはヨコ60cm以上、タテ40cm以上と決められています。
そのため、業者に発注する際は意識しておきましょう(大抵の業者は発注時に教えてくれますが、中には言われたまま作ってしまう業者もいたため要注意です)。
5-3-2.建築許可に基づく建築行為について
言うまでもありませんが、市街化調整区域の建築許可を受けた以外の方が建築行為をすることは認められません。
つまり建築許可の名義貸しはできないのです。
例えば建築許可をとった後に市街化調整区域を第三者に売却した時、その第三者が建築行為をする時は、新たに建築許可をとり直す必要があります。
5-3-3.建築行為の取り止め
市街化調整区域で建築許可をとった後、その建築行為を取り止めにする場合は、市街化調整区域を管轄する土木事務所に相談してください。
その上で、建築許可を受けた敷地とその周辺に防災上・交通安全上支障がないように必要な措置を講じることになります。
詳しいことは市街化調整区域の状況によって異なるので、土木事務所で入念に打ち合わせましょう。
6.市街化調整区域で建築許可を申請する費用は?(神奈川県の例)
市街化調整区域で建築許可を申請するための費用はどのくらいかかるのでしょうか。
大きく分けて、建築許可をとるための申請手数料と、それに伴う諸費用があります。
6-1.建築許可の申請手数料
市街化調整区域で建築許可を申請する際の手数料は敷地面積によって変わります。
| 0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 69,000円 |
| 1.0ヘクタール以上 | 97,000円 |
手数料は改定されることがあるため、申請の際には最新情報を確認しておきましょう。
6-2.その他、建築許可に伴う諸費用
市街化調整区域で建築許可をとる際、添付書類の発行手数料などをピックアップしておきます。
- 公図の写し 450円/通
- 土地登記事項証明書 600円/通
- 戸籍謄本 450円/通
- 住民票 300円/通
- その他、必要書類のコピー代……など
これらの中にはオンライン取得で安くなるものもありますから、可能であれば少しでも便利に経費を節約したいですね。
また、役所までの交通費や必要書類のコピー代なども加味しておきましょう。
7.市街化調整区域で建築許可が下りるまでの期間は?
市街化調整区域で建築許可をとる場合、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
結論から言えばケースバイケースで、スムーズに話が進めばおおむね2~3ヶ月前後で建築許可が下りることが多かったです。
例えば兵庫県神戸市では標準処理期間を設けており、こちらも参考になるでしょう。
- 開発許可を受けている土地の建築許可など(都市計画法第42条1項ただし書)
- ・開発許可を受けていない土地の建築許可など(都市計画法第43条1項)
⇒いずれも25日。
ただし補正に要する期間や都市計画法第32条の協議期間、事前審査等の期間は含みません。
また、開発審査会の議(都市計画法第34条1項14号)を必要とするものは30日or60日が加わります。
更に開発行為の許可(都市計画法第29条1項)も申請する場合は面積ごとに下記の日数が加わるため覚えておきましょう。
| 0.3ha未満 | 25日 |
| 0.3ha以上5.0ha未満 | 40日 |
| 5.0ha以上 | 55日 |
※参考:神戸市:市街化調整区域での開発(建築)許可に関するよくある質問
これらを総合すると、市街化調整区域で建築許可をとるためにかかる期間は、最短2~3ヶ月、開発許可を加えるとトータル半年くらいかかることがあります。
市街化調整区域で建築許可をとる場合は、十分な時間的余裕を織り込んだスケジュール作成が必要です。
8.市街化調整区域の物件を売却する方法は?
ここまで市街化調整区域で建築許可をとる方法などについて紹介してきました。
皆さんの中には、市街化調整区域で建築許可をとる手間を考えたら、むしろ売却したいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。
市街化調整区域の物件を売却しようと考えた時、まず思いつくのが不動産会社の仲介だと思います。不動産のことは不動産のプロにお任せしたいと思うのは当然ですよね。
ただ、市街化調整区域は制約が多く手間がかかるため、不動産会社でも取り扱いたがらないところが少なくありません。
また不動産市場でも流通量が少なく、会社によっては取り扱いに慣れていないことからトラブルが発生してしまうリスクも考えられます。
そこでおすすめなのが、市街化調整区域の取り扱いを専門に行う買取り会社です。
8-1.市街化調整区域を現況のまま買取りしてもらえるケースが多い
当たり前と言えば当たり前ですが、多くの不動産会社では面倒な物件を取り扱いたくありません。
例えば残置物の撤去や権利関係の問題解消(地権者共有者の承諾書や誓約書をもらう等)など、売主のコスト負担を求められるケースが多くあります。
しかし、管理が大変だから市街化調整区域の物件を手放したいのに、これ以上の負担を強いられるのは耐えられない方も多いのではないでしょうか。
一方、買取専門業者であれば市街化調整区域の物件を現況そのままで買取りしてくれるケースが多くあります。
もちろんコスト分は査定金額から差し引かれるでしょうが、自分でコスト負担することを考えれば、コスパは十二分です。
買取専門業者は市街化調整区域の取り扱いに慣れているため、一般の方や不動産会社が行うよりも低コストで問題解消できます。だから自分でする場合よりも安く済むでしょう。
8-2.市街化調整区域の売却に仲介手数料がかからないケースも
市街化調整区域の売却を不動産会社に仲介してもらうと、不動産会社に仲介手数料を支払わねばなりません。
仲介手数料の金額は法律で決まっており、売却する市街化調整区域の取引価格によって変わります。
| 200万円以下 | 取引価格×5% |
| 200万円超~400万円以下 | 取引価格×4%+2万円 |
| 400万円超 | 取引価格×3%+6万円 |
※土地の場合は非課税、建物等については消費税等(免税事業者の場合はみなし仕入れ率)が課税されます。
※低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の例外もあります。
これが買取り専門業者であれば仲介手数料は発生しません。仲介ではないから当たり前ですね。
ただし、買取りを謳っていても実際には自社での買取ではなく、他者へ仲介しているだけの会社も存在します。
その場合は仲介手数料が発生してしまうため、市街化調整区域を自社で買取りしているか事前に確認しておきましょう。
8-3.市街化調整区域の契約不適合責任が免責になるケースも
市街化調整区域の物件を個人に対して(不動産会社の仲介で)売却する場合、物件に瑕疵があると契約不適合責任を問われるリスクがあります。
事前に把握しきれていなかった瑕疵について、後から責任をとらされると思わぬ出費となるケースが多く、売却利益が大きく損なわれてしまうのは避けたいところです。
これが買取専門業者であれば瑕疵も織り込んだ上で買取りするため、契約不適合責任を面積してもらえるケースも多くあります。
後から責任を追及されないという安心感は、市街化調整区域を売却する上で大きなメリットと言えるでしょう。
これらのメリットを総合すると、市街化調整区域の売却は買取専門業者がおすすめです。
9.市街化調整区域でお悩みならURUHOMEへご相談を
以上、市街化調整区域で建築許可をとる方法などについて徹底的に解説してまいりました。
建築許可をとるためのハードルを思うと、市街化調整区域を売却したいと思われた方も少なくないのではないでしょうか。
そんな時は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
当社は2005年の創業より、神奈川県・東京都をはじめ全国各地で市街化調整区域などニッチな不動産買取りを専門的に行ってまいりました。今回も、お客様の悩み解決に役立てると思います。
市街化調整区域の買取査定は完全無料、最短ではご連絡いただいてから2時間で査定完了、2日で売却できたケースもございました。
皆さんが市街化調整区域のスピード売却&現金化をご希望でしたら、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。