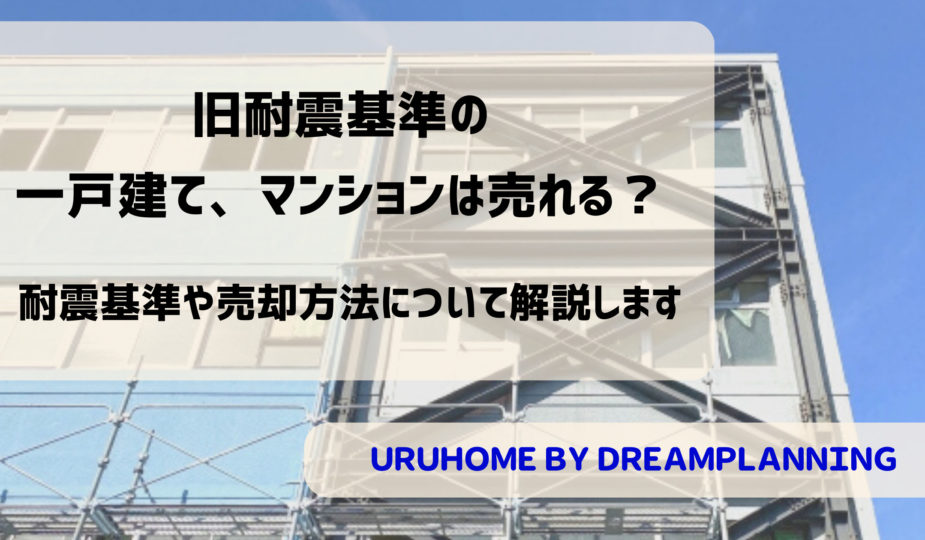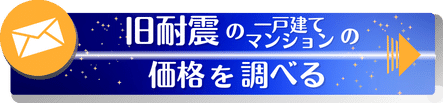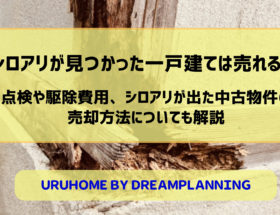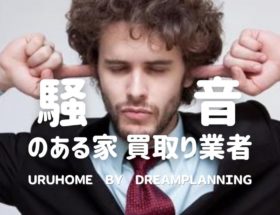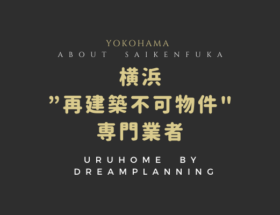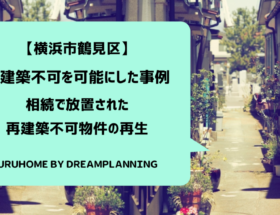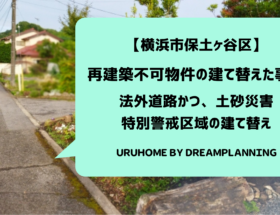「旧耐震基準の家を相続したけど、売ることはできる?」
売却の難しい不動産の買取を専門とする私達には、このような相談が日々寄せられます。
旧耐震基準ということはすでに築40年以上の建物ということで、売却が出来るか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回、旧耐震基準の一戸建てやマンションの売却方法、活用方法について、築古物件の買取を専門とする買取会社社長が解説いたします。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の傾斜地などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな傾斜地でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.旧耐震基準って何?
わたしたちが安心して生活するために、住宅や建物が堅牢なものであることは欠かすことができません。
「旧耐震基準」とは、1981年の建築基準法による新しい耐震基準が適用される以前に建てられた建物の事で、震度6以上の大地震などの際には、倒壊、崩壊、損傷する可能性が高くなります。
平成30年の住宅土地統計調査によると、全国の住宅総数約5,361万戸に対し、旧耐震基準で建てられた建物は少なくとも約1,200万戸(約22%)あり、国も建て替えや耐震改修工事を推奨しています。
地震の多いわが国では地震による被害から、財産や生命等を守るためにも旧耐震建物への対応が急務となっています。
1-1.旧耐震基準・新耐震基準とは
旧耐震基準とは
1981(昭和56)年5月31日以前の建築確認において適用されていた基準のこと。
震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されている。
耐震基準には新旧がありますが、1981年に建築基準法に定める耐震基準が改正され「新耐震基準」が定められたことで、それ以前の1950年に施行された耐震基準に則っている建物を「旧耐震基準」に準拠した建物というようになりました。
新耐震基準とは
1981(昭和56)年6月1日以降に建築確認において適用されている基準のこと。
「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準」であることが求められる耐震基準とされている。
1-2.旧耐震基準と新耐震基準の違いは?
新耐震基準とそれ以前の旧耐震基準にはどのような違いがあるのでしょうか。
建築物を建築するには、建築確認を申請します。
申請後、建築基準法に適合する建築計画であるか審査され、建築基準法に適合する計画であれば建物を建てることができます。
このとき建築された時点における建築基準法に含まれる耐震基準が準拠されることになります。
➤旧耐震基準 1950年 建築基準法施行 震度5程度の地震で家屋が倒壊・崩壊しない耐震性能
➤新耐震基準 1981年 建築基準法施行令改正 震度6強から7の地震でほとんど損傷しない建物であること
1-3.建築基準法改正の流れ
建築基準法は、これまで何度も改正され、耐震性能についても見直しがなされ、より厳しい基準で建築されるようになってきています。
これは実際にわが国が数々の大地震に見舞われた際に、被害を調査等したうえで精査され、より耐震性能を高めていくための改正を重ねてきたものです。
現在の基準では、震度6を超える大地震があっても倒壊しないような設計が求められています。
| 1924年 | 耐震規定が制定 |
| 1948年 | 福井地震発生(震度6) |
| 1950年 | 建築基準法の制定に伴い「旧耐震基準」が制定 |
| 1968年 | 十勝沖地震発生(震度5) |
| 1971年 | 鉄筋コンクリートのせん断補強基準の強化 |
| 1978年 | 宮城県沖地震発生(震度5) |
| 1981年 | 「許容応力度計算」と「保有水平耐力計算」の概念が取り入れられる バランスに配慮した設計が求められるようになった この年以降「新耐震基準」と呼ばれるようになる |
| 1995年 | 阪神・淡路大震災発生(震度7) |
| 2000年 | 木造住宅で地盤調査が義務づけられる また木造住宅で接合部の金物が指定され、耐力壁の配置のバランスが規定 |
| 2001年 | 品確法によって「耐震等級」が定められるように |
| 2007年 | 建築確認・検査が厳しくなり、3階建て以上の共同住宅で、中間検査が義務になる |
| 2008年 | 長期優良住宅の普及に関する法律が制定 長期にわたって住めるための措置がされた |
建築基準法改正の流れ
1981年に新耐震基準が制定されています。
大きな地震が起きるたびに耐震基準は見直されていますが、阪神・淡路大震災後は木造住宅への改正が主になっています。
1-4.旧耐震基準の見分け方
建築物が、新旧どちらの耐震基準になっているかという判断ですが、一般的にはその建物がいつ造られたかで判断します。しかし築年数だけでの判断は簡単にはできません。
一般的には1980年の建築ならば、旧耐震基準の建物と考えられるのですが、築年が1981年だとしても新耐震基準で建てられているとは限りません。
というのは、建物を造るときには、建築設計から建築確認までには時間を要します。また、建築確認から竣工(工事が完了)までにかかる期間も建物によって様々です。
マンションなどでは1年以上かかることもあるため、所有者が建築確認申請日を調べる時は「確認通知書(副)」の発行日で判断します。
1980年築は旧耐震基準の建物、1981~1983年築は要確認、1984年築は新耐震基準と考えられる
「建築確認の通知書」発行日付が1981年6月1日以降であれば新耐震基準、5月31日以前であれば旧耐震基準の建物と考えられます。そして、マンションのような大規模な建物で建築に1年程度要する場合、建築確認申請の確認通知書の発行日を参照して判断します。
➤ 旧耐震基準のマンション 1981年5月31日以前に建築確認済証が交付され、着工したマンション。マンションは着工から竣工まで1〜2年程度かかるため、竣工年は1982〜1983年であっても旧耐震で建てられている可能性があります。
2.旧耐震基準の建物を保有するリスクと対策
旧耐震の建物の最大のデメリットは、安全面のリスクがある事ですが、これは一戸建てだけでなく、マンションにも言えます。
熊本地震においても鉄筋コンクリート造の建物が倒壊している事からも、旧耐震基準の建物は耐震性などにおいて一定のリスクがある事を忘れてはなりません。
そこで、旧耐震の建物を保有することのリスクと対策について、ここでは解説してまいります。
2-1.旧耐震の戸建てを保有するリスク
旧耐震基準の一戸建てを放置してしまうと次のようなリスクがあります。
- 震災や自然災害による倒壊リスク
旧耐震の建物は震災による倒壊リスクがある事は前述したとおりですが、台風や水害、土砂災害などにおいても新耐震基準の建物より倒壊リスクが高いと言えます。 - 維持管理費用などがかかる金銭的リスク
空き家はそのままにしておくと建物が風雨や経年劣化によって老朽化し、維持管理、修繕のために様々な費用が発生します。 - 建物の倒壊などにより第三者に危害を与えるかもしれないリスク
建物の老朽化により、通行人などの第三者がけがなどをしてしまった場合、土地を所有しているだけでも所有者としての責任が生じることがあります。 - 「特定空き家」指定による固定資産税増加のリスク
空き家を適切な管理をせずに放置してしまうと、自治体から「特定空き家」に指定されることがあります。その場合、固定資産税が6倍に跳ね上がってしまう可能性があります。 - 犯罪行為に巻き込まれるリスク
放置された空き家となると、空き巣・放火の被害や、犯罪者・ホームレスなどが住み着くリスクも考えられます。実際に当社でも空き家を所有していて火災が起きてしまった方や、知らない人が住み着いてしまったという事例のご相談も受けています。
2-2.旧耐震マンションを保有するリスク
築40年以上のマンションは、旧耐震基準で建てられていることがほとんどです。
地震による倒壊の原因は、構造物だけではなく、地盤やコンクリートの劣化進度などさまざまな要因が影響して、被害の度合いが変化します。
しかし、旧耐震基準のマンションの老朽化は、建物全体の防水やひび割れなど、複数の要因が重なり、被害を招くことも考えられます。
特に大地震の際には、低層部分の構造が耐えきれずにつぶれてしまい、上層階が真上から落ちてくるということが想定され、コンクリートの大きなかたまりであるマンションが崩れるとその被害は甚大なものとなりえます。
旧耐震基準のビルでは、耐震補強工事をしている建物もあり、耐震基準適合証明書があれば、新耐震基準のマンションと同じ扱いになります。
適切な管理の下、定期的な修繕工事などで設備面、安全面からも手入れをしている物件などもありますが、大きな建物の崩壊に対する不安はリスクと言えます。
2-3.旧耐震の建物は耐震補強で地震対策できる
旧耐震のビルでは耐震補強をしていることもあるとご説明しましたが、マンションや一戸建ての場合にも安全性を高めるために、耐震補強をすることが可能です。
耐震補強工事をするには、まず耐震診断を行う必要があり、適切な耐震補強工事を行うことでリスクを減らすことができます。
尚、耐震補強の効果を達成するために以下のような方法があります。
- 建物の耐力を上げる方法
- 粘り強くさせる方法
- 地震挙動を制御する方法
耐震診断とは
耐震診断とは、旧耐震基準で設計された建物の耐震性能を、現行の耐震基準で測ることを指します。
1995(平成7)年1月17日の阪神・淡路大地震では、6,400人を超える命が失われましたが、その犠牲者の8割以上が、家屋の倒壊等による圧迫死が原因とされています。
そして、注目すべきは倒壊住宅の多くが「旧耐震」時期の建物だったことです。
このことから、旧耐震基準と新耐震基準では地震発生時に安全面で大きな差が生まれることが分かります。
2-4.耐震等級って何?
耐震診断と似た言葉に、耐震等級というものがあります。
これは平成 12 年 4 月 1 日に施行された “住宅の品質確保の促進等に関する法律” に基づき運用開始された「住宅性能評価制度」という制度の中で決められている、建物の地震に対する強さを表すものです。
新耐震基準以降に建てられたの建物であれば「耐震等級1」となりますが、旧耐震基準で建てられた建物については、「耐震等級1」に満たない地震による倒壊のリスクがある建物と言えます。
旧耐震基準で建てられた建物の中には、「耐震等級1」に満たない建物が6割(国土交通省住宅ストック状況より)ほどあり、こうした建物の耐震性を確保していくことを国でも課題としております。
| 耐震等級 | 耐震性能 地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ、地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
| 耐震等級1 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定め るもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
| 耐震等級2 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
| 耐震等級3 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定め るもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
3.旧耐震基準の家は売却が難しい
「新耐震基準でない建物の安全性の不安」といっても、地震はすぐに起こるかどうかはわかりませんし、実際、古いマンションや住宅に人が住んでいないわけでもありません。
それなのに、なぜ、売却が難しいといわれるのでしょうか。
3-1.旧耐震基準の家は築年数がかなり古い
旧耐震基準の一戸建てやマンションということは、1981年以前に建築された、築40年以上の物件になります。
築40年というと、まず築年数が古い建物という理由で、築浅の物件に比べて買い手がみつかりにくくなります。
築年数が古いと室内の設備や外観なども現在の生活スタイルに合わなかったり、そもそも劣化していることもあるので、敬遠される理由になります。
新耐震といえども経年劣化により売却が難しくなりますので、宜しければごちらの記事も参考にしてみてください。
3-2.旧耐震基準の家はローンや減税措置が使いにくい
2022年の税制改正では、住宅ローン減税が新耐震基準であれば利用出来る事になりました。
一方、旧耐震マンションは、住宅ローン減税を利用するためには耐震基準証明書が必須になったうえに、金融機関も耐用年数の関係で担保評価を厳しく見る(金利が高くなる)などのリスクもあります。
ローンや減税措置を利用しにくい事なども売却が難しい要因の一つと言えます。
3-2-1.旧耐震基準の家はフラット35が使えない
建築確認日が1981年(昭和56年)5月31日以前の物件は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準に適合していないとフラット35を利用することができません。
住宅ローンの選択肢が狭くなれば、当然買主も少なくなってしまいます。
民間の金融機関でも旧耐震の建物はローンが組みにくい事もあります。
➤ フラット35 フラット35とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすいメリットある。
フラット35は、耐震基準適合証明書の取得がなければ融資を受けらない。
3-2-2.旧耐震基準の家は減税や公的給付金(補助金)を受けられない
旧耐震基準の一戸建て・マンションの場合、耐震基準適合証明を受けなければ、次のような減税や公的給付金(補助金)を受けられません。
- 所得税の住宅ローン減税
- 不動産取得税、登録免許税の特例(優遇措置)
- すまい給付金
このなかでも、住宅ローン減税が使えないことは大きなリスクといえます。
住宅ローン減税では、住宅ローン残高の0.7%を上限として所得税や住民税の減税が可能です。
これに該当しないとなりますと、新耐震基準の場合に比べて損をしてしまうことになります。
3-2-3.旧耐震基準の家は融資額の上限が低い
住宅金融支援機構以外の金融機関でローンを組むことはもちろん可能です。
しかしその場合でも、旧耐震基準であることを理由に建物の担保価値が割り引かれてしまい、融資額が少なく抑えられることがあります。

4.旧耐震の家は投資用としても売却が難しい
旧耐震の一戸建て、マンションは実需では売却するのは難しい事をご説明してまいりましたが、投資用としても売却が難しいと言われています。一番の理由は投資用として購入する方がローンを組みにくいというのが挙げられます。
そこで、なぜ旧耐震の家が投資用としても売却が難しいのが解説してまいります。
4-1.旧耐震の家は賃貸に出すことが難しい
民法には「賃貸人(オーナー)は賃貸物件(アパート)の使用・収益に必要な修繕をなす義務を負う」と定められています。貸主である大家さんは建物の一部が損壊した場合、修繕を行う必要があります。
旧耐震基準の建物は、老朽化による改修費用もかかり、維持管理にもお金がかかります。
それらをすべて家賃に載せるとすると、築年数の新しい物件に比べて、むしろ高い家賃となってしまいかねません。
マンションの場合は、耐震改修工事が施されれば物件の価値が高まるかと思いますが、分譲マンションの場合、耐震改修工事は管理組合などで計画することになるので、いま出来ていないものをすぐに施すことは予算面でも非常に難しいと言えます。
4-2.旧耐震基準の家は投資ローンが組みづらい
まず、投資目的の方が購入しやすいかどうかですが、旧耐震の区分投資用マンションに融資をしてくれる金融機関は、ノンバンクを除くと数社に限られ買い手が限られるため、旧耐震の不動産は売却が難しいと言えます。
木造住宅の耐用年数は22年、マンションでも47年ですので、それぞれの耐用年数が経った時点で資産価値が0になるというのが金融機関の考え方です。
そのため、すでに築40年以上の旧耐震基準の建物は、担保としてはほぼ評価しないという判断になってしまうのです。
| 構造 | 法定耐用年数 |
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨プレハブ造(骨格材 肉厚3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨プレハブ造(骨格材 肉厚3mm 超4mm以下) | 27年 |
| 重量鉄骨造(骨格材肉 厚4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
5.旧耐震基準の物件の売却に困ったら
ここまで旧耐震基準のデメリットについて主にあげていますが、旧耐震基準の一戸建てやマンションは
- 敷地が広い
- 立地や眺望が良い
- 駅から近いなど利便性の高い地域にある
- 価格が安い
といったメリットを持つ物件も多く、売却が出来ないと決めつけることはありません。
しかし、こうした訳あり物件を売る際には、旧耐震基準の建物のデメリットを理解した上で取り扱ってくれる旧耐震の一戸建てやマンションを得意とする不動産業者に相談しましょう。
旧耐震の不動産の買取を専門としている業者に買取りを依頼すると、最短2日で現金化することも可能です。
5-1.旧耐震を売るならURUHOME
ニッチな不動産”URUHOME”でお馴染みドリームプランニングは、2005年の創業より、東京、神奈川を中心に全国で旧耐震基準の一戸建て、マンションの買取をさせて頂いてまいりました。
旧耐震基準かつ再建築不可、市街化調整区域、傾斜地など売却が困難な条件が揃っていても、他社様で断られた不動産でもお気軽にご相談ください。
最短30分で査定、お問い合わせから最短2日でお買取りさせていただいた実績も多数ございます。お困りの不動産など喜んで査定させて頂きます。
是非一度ご連絡くださいませ。