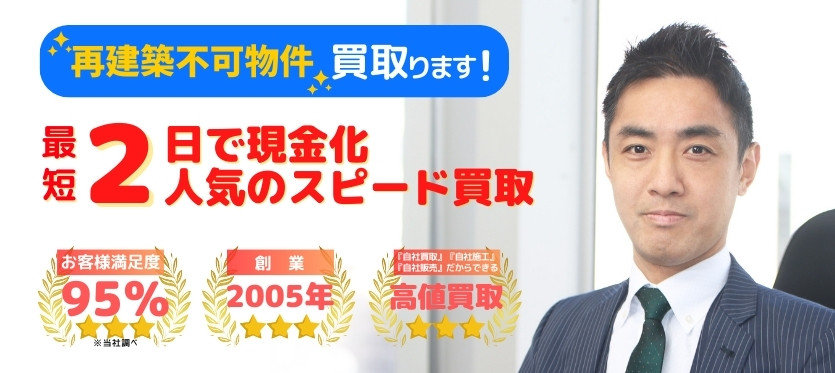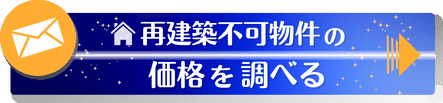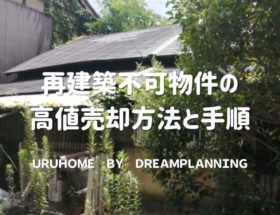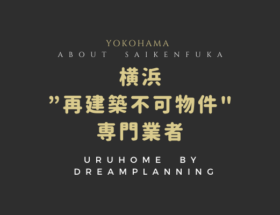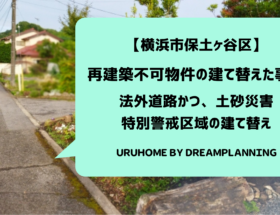「再建築不可物件を、再建築可能に出来ないの?」
再建築不可物件を持て余している地主さんや不動産業者様にとって、再建築を可能にすることは何よりの悲願でしょう。
そこで今回は、数ある再建築不可物件の再生事例から接道が無い物件を接道させて再建築可能にした事例を紹介。再建築不可物件を専門とする不動産業者の社長が、分かりやすく解説します。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」では、2005年の創業より、日本全国の再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウを不動産のお悩みを抱えている方々の問題解決に少しでも役立てばと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 再建築不可物件を再建築可能にした実例1/4相談の経緯
- 再建築不可物件を再建築可能にした実例2/4再建築不可物件の買取
- 再建築不可物件を再建築可能にした実例3/4再建築不可物件の再生
- 再建築不可物件を再建築可能にした実例4/4土地として売却
- 難しい再建築不可物件の売却はURUHOME
1.再建築不可物件を再建築可能にした実例1/4相談の経緯
横浜市鶴見区朝日町で、再建築不可物件のため、売却が難しいという事で仲介業者さんを介してご相談を頂きました。
公図、謄本、測量図を取得して調査してみると、測量図は周辺のものも含めて存在せず、公図上では完全に接道していない事が分かりました。
建築基準法では、基準法道路に2m以上接道していなければならないのですが、接道が全くないため本物件は現状では再建築できない敷地であるということが分かりました。
1-1.現地の調査
公図上では再建築不可ですが、現地を調査してみると敷地から一部舗装されていない専用通路のような部分があり、基準法の道路に出られるようになっておりました。
建物が建っている以上、道路に出られないという事は考えにくいのですが、本物件は2m位の通路が未舗装になっており、本物件側の敷地ではないかとも取れるような形状になっておりました。
1-2.建築計画概要書、建物図面の調査
本物件及び隣接地の建築計画概要書と、建物図面を調べてみると、本物件の建築計画概要書は無く、台帳記載証明はあることは分かりました。
台帳記載証明を確認すると、建築確認が以前に出されていることが分かりました。
また、隣接地の建築計画概要書を見ると、専用通路部分が本物件の敷地であるような図面になっていたため、建築基準法上では本物件は適法に建てられているのではないかと考えました。
更に、建物図面を確認してみても、本物件の敷地が建築基準法の道路に接しているような形状になっておりました。
隣接地に関しても、本物件の敷地が道路に接しているように図面では書かれていました。
1-3.建築計画概要書、台帳記載証明とは?
建築計画概要書も台帳記載証明も一般の方にも公開されていて、建築確認を管轄している市町村町の建築指導課に行けば、基本的に誰でも閲覧できます。
ただ、自治体によって保管されている年数が違うため、建築された年が古いと閲覧はできません。
➤ 建築計画概要書
建築計画概要書とは、建物を建てた際に建築確認が出されている事を証明する書類で、
敷地面積、建物面積、敷地と建物の形状などが記録され、役所に備え付けられているものです。
➤ 台帳規制証明
台帳記載証明は、建築計画概要書と違い、敷地と建物の形状などは記録されいないのですが、
敷地面積、建物面積と建築確認が出された年月日と、建物を適法に建てられたことを証明する検査済証が出された年月日が記載されています。
1-4.建築確認の敷地と、実際の敷地の違い
建築基準法では、建築基準法の道路に2m以上敷地が接していなければなりませんが、道路に接しているのが自分の敷地でなくとも、他人の土地を借りて接道していれば建築確認は取得可能です。
少しイメージが付きづらいとは思いますが、下の図のように他人の土地を借りて接道していれば、建築確認は取得できるのですが、貸した側の土地の所有者が建て替えをするときには貸した土地を建築確認の敷地として含めることは出来ないという決まりになっています。
つまり、自分の土地であるかどうかと、建築確認上の敷地であるかどうかは少し別の問題になるのです。

1-5.境界未確定の通路
今回の土地で言うと、建築確認上の敷地としては本物件に含まれていますが、敷地境界は未確定であり、専用通路部分については誰のものかは不明でした。
実際このような土地でも、境界が未確定の土地を建築確認上の敷地として申請できる可能性はあるのですが、後々トラブルになる可能性が高いことや、販売する際に再建築不可になる可能性が極めて高いため、購入させていただいた後に敷地境界を確定することにしました。
2.再建築不可物件を再建築可能にした実例2/4再建築不可物件の買取
境界確定が上手くいくかは全くわかりませんでしたが、所有者様が近隣の方より防犯上の理由により、建物を解体してほしいと役所を通じて言われおり、解体費も捻出するのも難しいという事で弊社で買取をさせていただきました。
また、一度解体すると再建築できないため、とにかく解体しない方が良いと周りの方に言われていて困っていたようです。
建物にはツタが絡まり、老朽化により倒壊の恐れもありました。
万が一、近年の自然災害によって建物が倒壊して近隣の方に被害を与えるようなことがあれば、所有者責任を問われかねません。
お客様がご納得いただける金額を提示していただき、ご提示金額でお買取りさせていただきました。
底地・借地の同時売買は非常に難しいため、底地・借地の売却に詳しい専門の不動産屋に相談する事をお勧めいたします。
”ニッチな不動産URUHOME”でお馴染み 株式会社ドリームプランニングにお任せくださいませ。

3.再建築不可物件を再建築可能にした実例3/4再建築不可物件の再生
今回の物件の場合、幅員2mの通路部分が本物件の土地であると証明されるために、以下のような条件がそろえば再建築が可能になると考えました。
- 現在の公図が誤っていて、本物件が建築基準法の道路に2m以上接道している。
- 隣地の軒が通路部分に越境しており、越境部分は建築基準法の有効敷地に参入できないため、軒の越境を弊社の費用負担で解消させていただく。
- 万が一、越境の解消が出来ない場合は、通路部分を43条2項2号(但し書き道路)を利用して、再建築をする。
これらをひとつずつ解説してまいります。
3-1.公図が誤っていることを証明し、公図を訂正してもらう
公図が誤っていることを証明するには、法務局の職権で公図を訂正してもらう方法と、隣地所有者より公図の訂正を承認してもらう方法の二つがあります。
3-1-1.公図を法務局の職権で訂正してもらう
旧公図(明治時代に和紙で作られたものが元となっているコンピューター化される前の公図)と、自治体に備え付けられている公図(固定資産税の課税用の公図)を取得し、どちらの公図も本物件が建築基準法の道路に接道している事を証明する方法です。
どちらの図も同じ形状で、本物件が建築基準法道路に接道していれば法務局の職権で公図を訂正してもらえます。
しかし今回の場合、旧公図は建築基準法の道路に接道しておりましたが、自治体の公図と形状が多少異なりました。
3-1-2.隣地所有者より、公図の訂正を承認してもらう
もう一つの方法は、近隣の方より公図が間違っていると承認してもらう方法です。
本物件の通路部分に接する方の皆さんが、公図が間違っていることを承認してもらえれば公図の訂正はできるという法務局の回答でした。
今回は、この方法により公図の訂正を行うことにしました。
3-2.建築基準法の道路に2m接していることを証明する
そして、本物件が再建築可能となるには、建築基準法の道路に2m以上接している必要があります。
この場合、境界確認をすることにより境界確定をするのですが、今回の隣接地の方が主張する境界の位置がころころと変わってしまったため、法務局により筆界を確認してもらう「筆界特定制度」や裁判所に「境界確定訴訟」などを申し立てる必要があります。
その他には、「所有権境確認の調停」を申し立てる方法もあります。

3-2-1.筆界特定制度とは
法務局の職員が専門家の意見を聞いて、現地での境界を特定する制度です。
筆界の位置について行政レベルでの判断を示すものであり、裁判によるまでもなく、6か月程度で迅速に適正な筆界についての判断を得ることができます。
ちなみに、筆界とは、明治初期の地租改正の過程で人為的に区画された土地の境界で、公的な地番界のことをいいます。
これに対して後ほどご説明する所有権境とは両所有者の有する土地の所有権の境界の意味で使われ、民法に由来する私的関係から生じます。
➤ 筆界 ― 明治初期の地租改正の過程で人為的に区画された土地の境界。公的な境界
➤ 所有権境 ― 所有者同士の所有権の境界。私的な境界
3-2-2.境界確定訴訟とは
境界確定訴訟とは、裁判所に申し立て、公法上の境界(原始筆界)を確定するものです。
これとは別に、自分の所有権の範囲を確定するには、所有権確認訴訟をする必要があります。
境界確定訴訟は、訴訟であっても勝ち負けがなく裁判所が境界を確定するだけという特徴があります。
境界確定訴訟を起こすと、原告、被告の主張に基づきますが、これらに拘束されることなく独自に判断します。
原則として、原告、被告が互いに合意したとしても和解や調停により決着することは出来ず、当事者間で公法上の境界を定めることは出来ません。
また、必ず境界確定が行われ、以後境界に関して争うことは出来ません。
以上が原則ですが、境界確定をせずに所有権境を合意して和解を成立させることも実務では多く、筆界(公法上の境界)は未確定のまま訴訟が終了することも多いようです。
3-2-3.所有権確認調停とは
あまり知られていないのが「所有権の範囲を確認する調停」です。
所有権界(私法上の境界)を確認するには、所有権確認訴訟という制度もありますが、訴訟を起こさずに第三者に入ってほしいという場合は、所有権の範囲を確認する調停をすることも可能です。
所有権の範囲を確認する調停による和解によっても筆界確定は出来ない事となっていますが、今回のように旧公図などの本物件が接道していたことを証拠として出して、公図が間違っていることが立証できれば、実務上は所有権の範囲が和解によって確定させて、地籍更正登記も出来ることとなっています。
今回は、この所有権の範囲を確認する調停を起こすことになってしまいました。
3-3.所有権界の確認調停
調停を起こす前に隣地の方とお話しし、通路部分が2mであることで合意していたのですが、なぜか突然言い分が変わってしまい、通路部分全てが隣地の方のものだという主張になってしまいました。
このため、やむを得ず調停を起こさせていただくことになりました。
所有権界については、調停を起こすと意外にもあっさりと通路部分が2mとする事で合意しました。
しかし、通路部分を2mとした場合、隣接地の屋根の一部が越境している事になるため、越境部分については、建て替えまで容認してほしいという意見を頂きました。
それ以外にも、外装工事等の際に通路部分に立ち入ることや、境界上にはお互いにブロック塀などを建てないなどのご意見も頂きました。
弊社も全ての条件をお受けし、円満に和解しました。

後日お話を伺うと、知り合いの司法書士さんから「公図上では通路部分も全てあなたのものだから、全てあなたのものだと主張しなさい」と言われたようです。
たまにこういう事情も何も知らない第三者の方に相談して、的外れなアドバイスを受けて苦労されている方を多くお見受けしますので、誰に相談するかは注意が必要だと思います。
3-4.43条2項2号による建て替えの許可
敷地の境界も無事に確定し、建物も解体しても、隣接地の屋根の越境を容認すると、越境した屋根の部分は建築確認の敷地に参入できないため、本物件は建て替え出来ません。
しかし、横浜市の場合43条2項2号による建て替えの許可を得ることで、再建築が出来るようになります。
これは、建築基準法の道路に2m以上敷地が接道していないと本来は建て替えが出来ないのですが、様々な理由によりこの規定に当てはまらない敷地でも建て替えを容認する救済措置です。
この救済措置にもいくつか基準があり、今回の物件は「建築審査会包括同意基準3-3の2」というもので、通路部分が2m未満であっても条件がそろえば再建築できるという救済措置です。
今回の物件がこの救済措置を利用して再建築が出来るという事を確認した上で、土地を販売することにしました。
4.再建築不可物件を再建築可能にした実例4/4土地として売却
土地として販売すると、相場より安かったため問い合わせが殺到しました。
購入申し込みが3番手まで入り、現金で購入を希望されている方にご購入いただきました。

5.難しい再建築不可物件の売却はURUHOME
ニッチな不動産でお馴染み”URUHOME”を運営するドリームプランニングは、2005年の創業より、再建築不可物件など売買が難しい不動産に特化した不動産の買取を行ってまいりました。
そのため、今回のように他社様で断られた再建築不可の物件でも、高値でお買取りさせていただくことが可能です。
特に、都内の城南地区、川崎、横浜、藤沢などを中心に、全国の再建築不可物件の買取をさせていただいており、最短30分で査定、2日で決済した実績も多数ございます。
相続などでお困りの土地、建物をお持ちの土地所有者様、相続予定のお客様、不動産仲介業者様は、是非一度当社までご相談くださいませ。
売却の難しい底地でお悩みの事がありましたら、お気軽にニッチな不動産”URUHOME”でお馴染みのドリームプランニングまで、お気軽にご相談下さいませ。