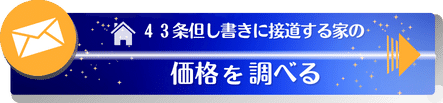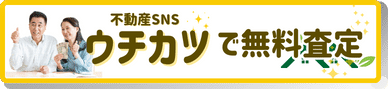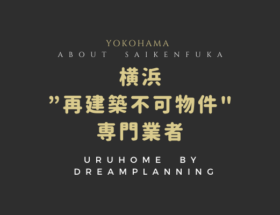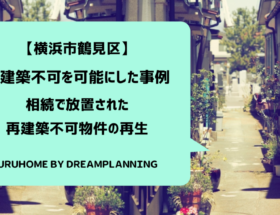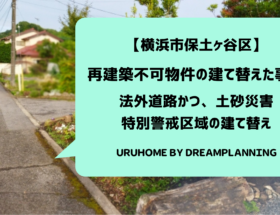家を購入するとき、売却するとき『43条但し書き』という言葉をよく耳にしませんか?
『43条但し書き』は現在『43条2項』の許可・認定と言われ、建築基準法の道路に接道していなくても条件が合えば救済措置として再建築が可能になるものです。
今回「43条但し書き(43条2項)」に接道している不動産の買取業者の社長が、但し書きについてできる限り分かりやすく解説いたします。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の43条但し書き(43条2項)の許可を要する不動産などを専門的に買い取っております。
2005年の創業より、年間300件ほどの但し書きの買取相談を承っており、5000万円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.43条但し書きとは何か?
1−1.43条但し書きとは?
「43条但し書き道路」は、現在「43条2項の許可(もしくは認定)」と呼ばれています。
本来、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建て替え出来ません。
しかし「43条但し書き(道路)」という”建築基準法上の道路ではないが、ある条件を満たした道路”に接していれば建て替え出来る救済措置のような役目を果たしております。

本来であれば、建築物の敷地は、「建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません」
ですが、43条2項の認定または許可が取れれば、再建築が可能になるのです。
ちょっと条文の方を覗いてみましょう。
建築基準法43条2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
※参考:建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)建築基準法 | e-Gov法令検索
特定行政庁?建築審査会?と訳が分からないと思いますが、要は「接道義務を満たしていなくても、条件が合えば再建築できる」という事です。
1-2.43条但し書きの基準は自治体によって異なる
条件があえば再建築できるという事で、その条件って何?と気になるかと思います。
かなりざっくりと説明すると、43条但し書き(現在の43条2項)の許可を受けて建て替える条件の例として、以下のようなものがあります。
- 「但し書き道路を4m確保するため建物を後退させる」
- 「2階建て以下にする」
- 「但し書き道路の所有者全員の同意を得る」
ただ、これはあくまで一例で、他にも厳しい条件が色々とあります。
詳しい条件は、次の2項で説明してまいります。
43条但し書き(2項認定・許可)とは
➤ 一定の条件を満たして建築審査会というという所の同意を得れば、建物を建築できる制度です。
特定行政庁
➤ 都道府県知事や市町村長、区長などを指します
1−3.43条但し書きと建築基準法道路は何が違うの?
ちなみに”42条の道路”と”43条但し書き”とは何が違うか疑問に思いませんか?
要は建築基準法の道路か、そうでないかはどうやって決まるかという事です。
これは、一概には言えませんが、おおざっぱに言うと昭和25年以前から存在していた道路か、国道や市道などの道路か、新設した道路かなどによって決まってきます。
簡単にまとめると以下のように分類されます。
”42条の道路”(一般的にいう建築基準法上の道路)”
➤ ”国道、県道、市道、都市計画法などで作られた道路”や、”位置指定道路や昭和25年11月23日に以前からあった道路”になります。
”43条但し書き(現在で言う43条2項2号)”
➤ ”それ以外の道(道路状の空き地)で特定行政庁が許可したもの”になります。
ただ、東京では基準法が適用される前からあった道路でも、2.7m未満の道は建築基準法の道路として認定されないなどの例外があります。
建築基準法の道路かどうかは、自治体の建築局に確認するようにしましょう。


2.43条但し書きの許可基準
2-1.43条但し書き道路として許可されるには、どんな基準があるの?
「但し書き道路」という名称を使っておりますが、これは正式名称ではありません。
正確には「43条2項1号の認定を受けた道路」とか、「43条2項2号による許可を受けた道路状の空き地」といいます。
非常に分かりにくい言い回しですね(*_*;
そんな話はさておき、43条2項2号による許可は「密集市街地の建て替え促進」のための救済措置であるという事が重要です。
そのため、公平性や客観性を持たせるために特定行政庁(ざっくりいうと地方自治体の長ですね)が、「どんなものであれば43条2項2号として許可を受けられるか」許可基準を作成して公表しております。
2-2.43条但し書きには「路線型」と「専用型」があります。
ここで、「どんなものであれば43条2項2号として許可を受けられるか」を説明したいところなのですが、次の項でご紹介するとして、43条但し書きには「路線型(の道)」と「専用型(の通路)」があります。
これも自治体によって呼び名が変わると思うのですが、以下の様な違いがあります。
路線型(の道) ➤ 建築基準法道路には接していないけど特例で再建築できる
専用型(の通路) ➤ 建築基準法の道路に接しているかどうかに関わらず、間口2m以下
どちらも建築基準法の接道義務を満たしていないので、再建築が出来ません。
しかし、「接している道路が建築基準法の道路ではないか」OR「間口が2m無いか」で、どちらが適用されるか異なるのです。
ちなみに「接道義務って何?」と疑問を持たれた方のために少し話をさせて頂くと、建築基準法では、建築基準法道路に2m以上接していないと再建築できないことになっております。
第四十三条(敷地等と道路との関係) 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
※参考:建築基準法43条 建築基準法 | e-Gov法令検索


2-3.包括同意基準とは何か?
ここで「どんなものであれば43条2項2号の許可を受けられるのか」に話を戻させて頂きますと、その基準をまとめたものが「包括同意基準」と言われるものです。
役所としても一つ一つの案件を、それぞれ特例で建て替えを許可していたら大変なことになります。
そこで、許可件数が大量になるために「包括(一括)同意基準」というものを定め、建築審査会(自治体ある機関で、建築物が適法か審査するところ)の同意を予め特定行政庁で得て、許可ができるようにしているのです。
つまり超簡単に言いますと、この基準を満たせば、「路線型」でも「通路型」でも、再建築不可物件が再建築可能になるという事です。
「えっ!じゃあ43条の許可基準って何?」と気になるかと思いますが、これは自治体によって違ってきます。

2-3-1.横浜市の包括同意基準
例えば、横浜市を例に挙げると以下の表のように、一定の基準があります。
包括同意基準3-3の2を見ると分かるのですが、横浜市は割と柔軟で、場合によっては、間口が1.5mほどの敷地でも建物を建て替えられることがあります。
| 包括同意基準1 | 広場等に接する敷地に建築する建築物 |
| 包括同意基準2 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 |
| 包括同意基準3-2 | 都市計画法第37条の規定に基づく制限解除を受けた建築物、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可を受けた建築物その他これらに類するもの |
| 包括同意基準3-3 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.8m以上、中心後退2m以上」 |
| 包括同意基準3-3の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.5m以上、かつ、延長20m以下」 |
2-3-2.東京都の包括同意基準
一方、東京都では区や市ごとに基準が定められていることもありますが、都内の多くの自治体では基本的に間口1.5mでは建て替えは出来ません。
| 基準1 | 敷地と道路の間に、次いずれか存在する場合で、幅員2m以上の通路が確保されている敷地 一 管理者の占用許可、承諾又は同意が得られた水路 二 地方公共団体が管理する認定外道路等 三 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地 |
| 基準2 | 次のいずれか幅員4m以上の公有地等に、2m以上接する敷地 一 地方公共団体から管理証明が得られた道 二 土地改良法第2条第2項第一号に規定する農業用道路 三 地方公共団体へ移管する予定であることを証明する書面が得られた道 |
| 基準3−1 | 幅員2.7m以上4m未満の道に2m以上接する敷地で、次のいずれかのもの。 一 道の中心線から水平距離2mの線又は道の反対側境界線から水平距離4mの線を道の境界線とし、将来現況の道の部分について不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記することについて、道の部分の所有権、地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。 二 申請者の権原の及ぶ道及び道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。 三 建築物は地上が2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋を計画するもの。 |
| 基準4 | 道路に有効に接続する幅員4m以上の道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。 一 将来にわたって幅員4m以上の道を確保することについて、道の部分の所有権、地上権又は借地権を有する者の1/2以上の承諾が得られたもの。 二 申請者の権原の及ぶ道の部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。 三 建築物は地上2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋を計画するもの。 |
| 基準5 | 「法第43条第2項第2号に基づく許可(改正前の法43条第1項ただし書の許可を含む)を受けた後、計画の変更により改めて許可を必要とするもので、建築物の用途・構造・階数及び敷地と道等の関係に変更のないもの。 |
2-3-3.包括同意基準に適合させるには
包括同意基準に適合していれば、再建築できるようになる訳ですが、最大の難所は「43条2項2号の許可を受けるための通路維持管理の誓約書」を取得する事です。
「誓約書って何?」と思いますが、43条但し書き(2項2号)道路に関しては、もともと建築基準法の道路ではないため、もしかすると私道の所有者が道にブロック塀を立ててしまうかもしれません。
また、私道の所有者が自分の敷地だと言って、建物を建ててしまうかもしれません。
そういう事が無いようにするために、「この道を道路として維持管理して、物を置いたり、築造物を作ったりしないですよ」という誓約書が必要なのです。
ただ、誓約書が必要か、実印を調印の上、印鑑証明も取得するかどうか、自治体によって要件が異なります。

また、東京・神奈川の包括同意基準については各自治体によって異なり、こちらの記事でもう少し紹介しています。
各自治体によって基準が違うので、詳しくは物件が所在する自治体に問い合わせてみましょう。
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでも、42条2項2号の許可を得て建て替えた事例がありますので、良ければ下記の記事も参考にしてみてください。
2-4.個別提案基準とは何か?
ここまで長らく読んでいただいて、「ある一定の基準を満たしていれば、接道義務を満たしていなくても建て替え出来ること」はお分かりいただけたと思います。
しかし、「43条2項2号の建築審査会の同意が得れるか微妙な物件は再建築できないのか」と疑問がわいてきませんか?
自治体によりますが、包括(一括)同意基準に該当しない場合でも、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認め、個別に建築審査会で同意を得て許可したものについても建築可能となります。
ただ全ての案件を建築審査会の審議にかけることは難しいため、「個別提案基準」といって審議にかけるための最低限の決まりがあります。
2-3-1.横浜市の個別提案基準
横浜市を例に上げると、以下のような基準になります。
これらの個別案件については、「環境水準の向上を目指す自治体」「建てかえハードルを比較的低くしている自治体」によって要件が全く異なりますので、ご注意ください。
| 個別提案基準3−4 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物【空地幅員0.9m以上1.8m未満、中心後退2m以上】 |
| 個別提案基準3−4の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地に建築する建築物【空地幅員0.9m以上、かつ、延長15m以下】 |
| 個別提案基準3−5 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物【空地幅員0.9m以上、中心後退1.35m以上2m未満】 |

ちなみに横浜市はかなり再建築不可物件に対して柔軟に対応しているので、詳しくは自治体に確認するようにしましょう。
当サイトURUHOMEでは東京・神奈川の43条但し書きなどの不動産を積極的に買取させていただいております
困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ(^^)/

3.43条の認定と許可って何が違うの?
ここまで読んでこられた方は、なんとなく43条2項2号についてわかっていただけたと思います。
そして詳しい方であれば、43条2項(但し書き)には、下記の”認定”若しくは”許可”があることをご存じだと思います。
ここでは、43条2項の許可・認定について、どういった違いがあるか見ていきましょう!
3-1.43条2項の認定と許可って何が違うの?
43条2項の許可、認定を簡単まとめると以下のような関係になります。
- 43条2項1号認定 ➤ 建築審査会の同意が不要
- 43条2項2号許可 ➤ 建築審査会の同意を予め得て、特定行政庁の許可が必要
つまり、1号だと許可不要、2号だと許可必要という事ですね。
もともと43条但し書き道路と呼ばれていたものは全て許可制でした。
ただ、許可なしでも基準法の道路と同じ扱いにして良いものは「43条2項1号」、許可ありで建て替えを認めようというのが「43条2項2号」に分かれました。
イメージがわきにくいかと思うので、かなりざっくりご説明するとこんな感じです。
- 43条2項1号 ➤ 建築基準法の道路ではないけど、ほぼ道路だから許可不要
- 43条2項2号 ➤ 建築基準法の道路でなく、安全性の確認が取れれば建て替えを認める
1号認定

2号許可

3-1-1.43条2項1号の認定(横浜市)
43条2号2項の許可については今までご説明してまいりましたので、認定については、横浜市を例に上げると以下のような基準になります。
| 認定基準1 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 |
| 認定基準2 | 平成11年5月1日において現に存する路線型の道に接する敷地に建築する建築物 |
3-1-2.43条2項1号認定・43条2項2号まとめ
では、43条2項1号と2項2号についてまとめていましょう。
43条2項1号認定 ➤ 建築基準法上の道路では無いけど、公的機関が管理する4m以上の道路に2m以上接している場合 ➤ 建築審査会の同意不要
43条2項2号許可 ➤ 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたもの ➤ 建築審査会の同意必要
3-2.43条但し書きの許可基準はどのように決められている?水路でも許可される?
43条但し書きの許可の基準として、以下の様な要件があります。
- 「交通上は交通混雑を防止し、円滑な一般通行を確保すること」
- 「安全上は避難及び歩行者の通行の安全を確保すること」
- 「防災上は延焼火災防止や円滑な消防活動に配慮する」
- 「衛生上は日照、採光、通風等の面で支障が無いこと」
以上のことから自治体の街の歴史や、今後のまちづくりも考えた上で、自治体も許可基準を決めていることは分かるかと思います。
自治体によって街の特性が異なるので、許可基準が変わるのはこのためです。
例えば、東京23区など水路の多い地区では、旧水路でも2.7m以上の幅員があり、権利関係者全員の承諾が得られれば、43条2項2号の許可が受けられることがあります。
4.43条但し書き道路のメリット・デメリット
4−1.43条但し書き道路のメリット
43条但し書き道路のメリットというのは、あえて言うと不動産の価格が安い事が挙げられます。
とくに通路を他人が所有している場合などは不動産の価格が低くなります。

43条但し書き(2項2号)については、建築基準法上の道路と異なり、将来にわたって道路状の形態が続くという担保がありません。
そのため、売買価格が安くなってしまうのです。
4-2.43条但し書きのデメリット
43条但し書き道路の最大のデメリットは、担保価値の低さです。
包括同意基準においても、個別提案基準においても融資を受けるのは難しいです。
特に個別提案基準の場合は審査が厳しくなります。
4-2-1.個別審査基準案件の住宅ローンを扱った事例
著者も過去個別提案基準の案件を扱ったことがありますが、その際は地方の信用金庫で融資承認を受けることが出来ました。
ちなみに、当然といえば当然ですが、それ以外のほぼ全ての銀行では断られました。
当時たまたま運が良かっただけで、現在では、地方の信用金庫で個別提案基準の案件を通すのはほぼ不可能では無いかと思われます。
銀行ローンが組みにくいという事は、売却も難しくなります。

4-2-2.43条但し書き道路に接する不動産の評価
包括同意基準であれば、同条件で接道要件を満たしている物件の8~9割位の価格で売却可能です。
しかし、個別提案基準の不動産については、案件数も非常に少ない為、同条件で接道要件を満たしている物件の5~7割程度の価格なってしまう事もあります。
しかも、購入希望者が現れたとしても「ローンが組めない可能性が高く、非常に売りにくい」というデメリットがあります。
5.43条但し書き道路で困ったら
43条但し書き道路の不動産は再建築の手続きが難しいことが分かってきました。
特に難しいのは、自治体によって包括同意基準や、個別提案基準などの要件が全く異なるため、インターネットで検索しても全て違うことを言っているので、混乱してしまうのではないかと思います。
しかし、43条但し書き(2項)で困っても相談する人が居なくて困りませんか?
当サイトウルホーム運営するドリームプランニングでは、43条但し書き(2項2号の許可)を要する不動産でも高値で買取可能です。
ドリームプランニングは、43条但し書きや再建築不可など、売却が難しい不動産の買取業者として2005年に創業しました。
お悩みの不動産がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
また、43条但し書きの査定も可能なおススメ相談サイトもご紹介させて頂きます。
5-1.43条但し書きに接する不動産を売却するには?
以上、43条但し書きについてご説明してまいりました。
43条但し書き道路に接する不動産は、権利関係者から道路の維持管理の誓約書がないと再建築できなこともあり、「誓約書、承諾書などが無いと売却できないこともあります」
しかし、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングが、43条但し書き道路に接道する不動産でも積極的にお買取りさせていただいております。
当社は43条但し書きの物件を多数買取させていただいており、自治体による包括同意基準の違いなどにも精通しております。
そのため、誓約書、承諾書が無くても、43条2項の認定を受けていなくても、どんな物件でも買い取らせていただいております。
43条但し書きに接する不動産の売却をお考えの際は、ドリームプランニングへご相談くださいませ。


5-2.43条但し書きに接する不動産の相談サイト
43条但し書きに接道する不動産については、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにご相談いただければお買取り可能でございます。
しかし、買取査定の前に不動産の相談をしたいという事はありませんか?
そんな時にお勧めなのが「不動産ウチカツ」です。
ウチカツは43条但し書きなどを専門とする不動産業者に匿名で相談ができるうえ、一括査定を複数の不動産業者に依頼する事が可能です。
また、不動産業者様も無料で利用できるという事で、全国の不動産業者が利用しているのが特徴です。
査定するまでではないとお考えでしたら、ウチカツから相談してみましょう!