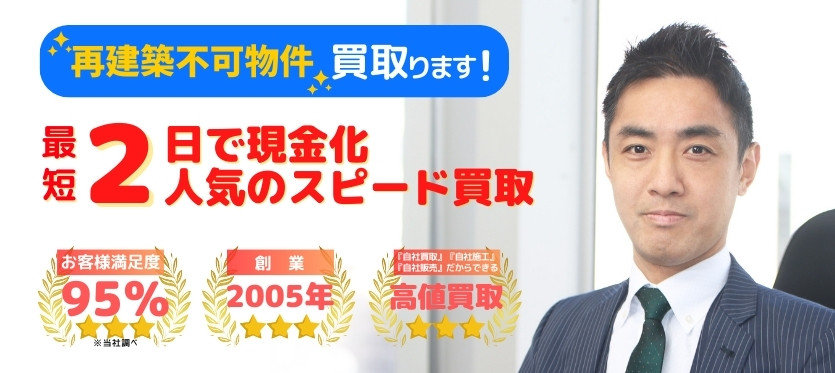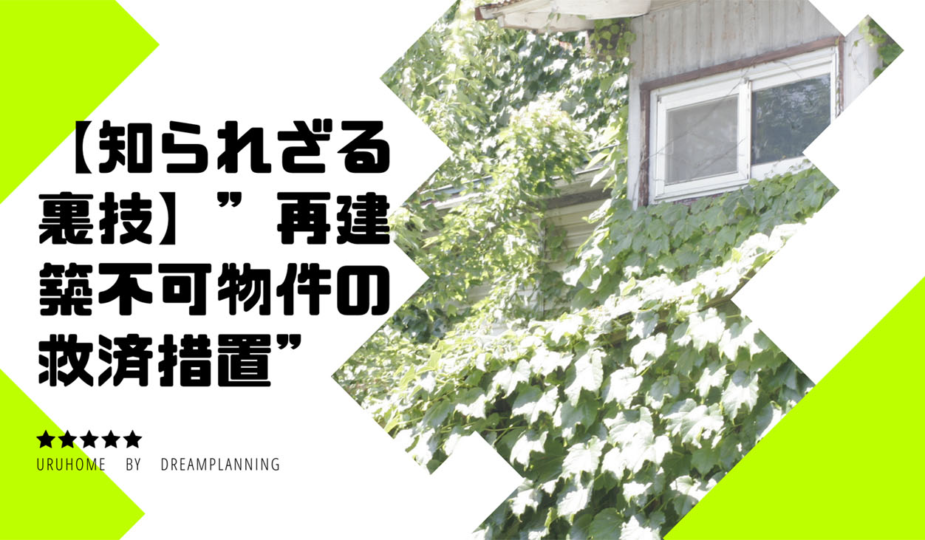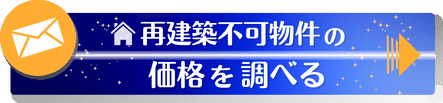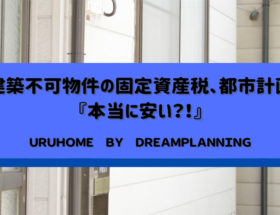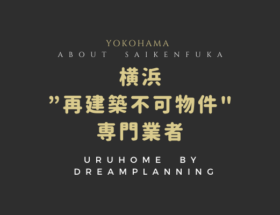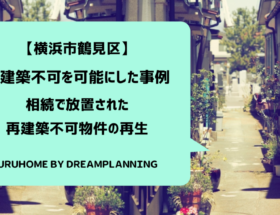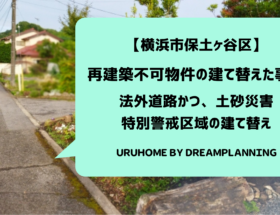「再建築不可物件を何とか建替えたいんだけど、建替える方法はある?」
「救済措置ってよく聞くけど、それってなに?」
↑これ本当によく相談を頂きます
再建築不可物件を所有や相続されて困っていらっしゃる方、ココでご紹介する ”裏ワザ” を使えば、建て替え可能になることがあります。
今回は、接道義務を満たさない時の救済措置である43条2項(旧但し書き)の許可・認定について、数々の再建築不可物件を再建築可能にしてきたプロがご説明します。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年に創業し、日本全国の再建築不可物件の買取をしてまりました。
再建築不可物件を再建築可能にする様々なノウハウもあるため、2000万円位までの再建築不可物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。
ご売却にお困りの再建築不可物件がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 再建築不可って何?
- 再建築不可物件の救済措置である裏ワザ・抜け道って何?
- 再建築不可物件の救済措置(裏ワザ・抜け道)には何がある?
- 43条2項2号の許可、個別提案基準、個別案件は特にローンが難しい
- 再建築不可物件を売却するならURUHOME
1.再建築不可物件って何?
再建築不可物件には、幾つかの種類がありますが、建築基準法や都市計画法等の規制によって敷地上の建物が建て替え出来ない物件を言います。
主に建て替え出来ない理由は下記の2つのケースによるものがほとんどです。
- 建築基準法の接道義務を満たしていない
- 都市計画法で建築をしてはいけないエリアに指定されている
今回は「建築基準法上の再建築不可物件」と、裏ワザと世間では呼ばれている再建築不可物件の”救済措置”について解説してまいります。
1-1.接道義務って何?
建築物の敷地は建築基準法第 42 条に規定する道路に2m以上接しなければならないことが規定されています建築基準法第 43 条第1項)。
この2mの基準が意外と厳しく、例えば2mの通路を含む旗竿地の場合、以下のようなものは全て道路に2m接していないと見なされ、基本的に再建築が出来ません。
- 一部2m未満の箇所を含む旗竿地
- 2mの通路内に隣地の屋根など建物の一部が越境している旗竿地
- 建築した当時は2mあったが、測量しなおすと2m未満であることが発覚した旗竿地
特に昭和の時代に区割りされた敷地に建てられた建築物は、2.00mで分筆された旗竿地が多く、測量技術の向上や、隣地から屋根の空中越境などで再建築できないことが少なくありません。
(※隣接地の建築物が越境している場合、越境している部分は敷地として算入できません)

1-2.建築基準法42条に規定する道路って何?
では、道路に2m接道してれば全て建て替え出来るかというと、「実はそうではない」のです。
接している道路が「建築基準法42条で規定する道路」に接していないと再建築が出来ないのです。
また、建築基準法42条で規定する道路には以下のようなものがあります。
- 1項1号道路:道路法の道路(例:国道、都道府県道、市町村道)
- 1項2号道路:都市計画法の開発許可、土地区画整理事業などによって造られた道路(例:大規模開発分譲地内の道路)
- 1項3号道路:基準法が施行された昭和25年11月23日と、都市計画法の区域の指定を受けた時点のいずれか遅い時点で存在する幅員4m以上の道路(例:昭和25年以前にある道路)
- 1項4号道路:道路法等による新設等の事業計画があり、2年以内にその事業が執行される予定の道路(例:新設予定道路)
- 1項5号道路:土地の所有者が築造する幅員4m以上の道路(例:位置指定道路)
- 2項道路:③に当てはまる幅員4m未満の道路(例:2項道路)
読んだだけで分かる方はあまりいらっしゃらないと思いますが、実際私たちが見ている多くの道路はこれら「42条で規定された道路」に当てはまります。
しかし、農道や勝手に造られた道路などはこれに該当せず、他にも見た目だけでは全く判定できない道路も沢山あります。
ですので、建築基準法42条の道路に当てはまるかどうか調査が必要なのです。

1-3.建築基準法42条の道路か調べる方法
まず、再建築可能かどうか調べるためには、不動産が接している道路が建築基準法42条の道路か調べなければなりません。
建築基準法42条何項の何号の道路かを『建築基準法道路種別』と言いますが、自治体で道路種別などを提供している地図がインターネットで検索出来るところもあります。
インターネットで「行政名+道路種別」と検索しても出てこない場合、各自治体の建築指導課などで道路種別を確認することができます。

1-4.間口が2mあるか調べる方法
再建築不可かどうか調べるには、不動産が建築基準法42条の道路に接道しているだけでなく、接道が2m無ければ再建築できません。
しかも、通路部分などを含んでいる場合、一部分でも2m未満の箇所があると再建築できず、通路部分に空中越境がある部分は建築確認の敷地に含まれないので、越境により2m未満の箇所があっても再建築出来ません。
接道が2mあるかどうかは、土地家屋調査士などに測量をしてもらい確認します。
さすがに土地家屋調査士の知り合いはいないという方は、「日本土地家屋調査士会連合会」のホームページでも検索可能です。
2.再建築不可物件の救済措置である裏ワザ・抜け道って何?
建築基準法42条の道路に2m以上接していないと再建築できないことが分かりました。
でも、何とかする方法はないのかと思いますよね?
今回ご紹介する裏ワザとは違うのですが「隣接地の一部を借りて建築確認を取得したりする」など、再建築不可を可能にする方法は幾つかあります。
しかし、「隣接地の一部を借りたりせずとも再建築不可物件を再建築可能にする方法」があるのです。
今回私達がご紹介する裏技、救済措置と言われるものは、これらの方法とは違い「43条2項の許可」「包括同意基準」「個別提案基準」などという自治体の特例による建て替え方法です。
それでは、43条2項の許可や包括同意基準とはどのようなものか、ここから本題に入ってまいります。
2-1.再建築不可の裏ワザ・抜け道の「43条2項の認定・許可」って何?
建築基準法では、建築基準法の道路に2m以上接していなければ再建築が出来ない事を説明してまいりました。
しかし、建築基準法の制定や、建築確認時の慣習の変化、時代の変化による建築確認の厳格化などにより、再建築できない土地があります。
そのため、建築基準法の43条2項では、再建築不可物件の救済措置として、市長や県長などが安全上など問題ないと認めて建築審査会の同意を得て、許可したものなどについては、再建築が行えることとしております。

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
建築基準法 | e-Gov法令検索
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
1号 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
2号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2-2.再建築不可物件が出来た背景
再建築不可物件が出来た背景には建築基準法の制定や、建築確認時の慣習の変化、時代の変化による建築確認の厳格化など幾つかの要因がありましたが、一番大きな要因はやはり「建築基準法の制定」です。
建築基準法が制定されたのは昭和25年、それ以前は市街地建築法(大正9年制定)という建築基準法の前身となる法律がありました。
しかし、少なくとも昭和の初め位までは「間口が2m無いと建物が建てられない」などという基準はありませんでした。
太平洋戦争が終戦したのが昭和20年、当時の住宅事情はひっ迫していたため、終戦から建築基準法が出来るまでに都心部では自由にバラックを建てていた方も多かったようです。
こうした時代の背景がある中で、昭和25年に建築基準法が制定され、接道義務が明文化されたことにより、それ満たさない建物が出来たことが再建築不可物件の始まりなのです。


3.再建築不可物件の救済措置(裏ワザ・抜け道)には何がある?
再建築不可物件を救済する措置として、43条2項による認定、許可があるとご説明しましたが、手続きが幾つかの方法に分かれます。
ここで「再建築不可が建て替え出来るなら何でも良いじゃん」と思うかもしれませんが、この認定や許可の手続きの難易度が物件ごとに全く異なり、どの手続きが必要かによって、金融機関の担保評価、不動産としての価値が全く違うのです。
そして、どのように認定・許可を受けるかは物件の接する道路や、物件や周辺環境の状況によって異なるのです。
そこで、ここではこの救済措置を受ける方法や難易度について、ご説明いたします。

3-1.43条2項1号の認定
■ 建築許可難易度 ★☆☆☆☆
■ 担保評価難易度 ★★★★★
43条2項1号の認定の場合、建築審査会の同意を経て市長や県庁などが許可をするものと違い、市長や県庁など安全上問題ないとして定めている基準に合えば再建築が可能になります。
43条2項1号の認定により再建築が出来る物件であれば、再建築可能な物件とそこまで大きく変わりません。
しかし、この基準に合致するかどうかが一番大事で、自治体によっては、「接する道に雨水・汚水が処理できる施設がある」「幅員4m以上で道路上に整備されている」「境界が明示されている」「道の勾配が9%以内」など、独自に要件を定めており、その自治体が定めた要件に合致して初めて再建築可能になるのです。
例えば横浜市では以下のような要件があります。
| 基準 | 概要 | 要件 |
| 認定基準1 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 | 道の管理者との協議が終了しているなど |
| 認定基準2 | 平成11年5月1日において現に存する路線型の道に接する敷地に建築する建築物 | 前面の道に雨水排水処理施設が適切に設けられている。3階以下の建築物など |

3-2.43条2項2号の許可・包括同意基準
■ 建築許可難易度 ★★☆☆☆
■ 担保評価難易度 ★★★☆☆
43条2項2号の許可を得る際に、建築審査会の同意を経て市長や県長などの許可を得ることになりますが、建築審査会は5~10名程度の委員と専門調査委員1~3名程度で構成され、1か月に一回程度しか開催されません。
しかも、43条2項2号の許可以外にも、やむを得ずに建築基準法に適合できない建物の新築や用途変更などに対する判定をしています。
そのため、建築審査会で一つ一つの案件に関して同意をするのも難しいため、43条2項の2号の許可に対して同意すべきか基準(これを「包括同意基準」と言います)を設けており、この基準に合致したものは再建築できるとしております。

3-2-1.横浜市を例にした43条2項2号の包括同意基準
横浜市を例にすると、包括同意基準として下記のようなものがあります。
| 基準 | 概要 |
| 建築審査会包括同意基準1 | 広場等に接する敷地に建築する建築物 |
| 建築審査会包括同意基準2 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 |
| 建築審査会包括同意基準3-2 | 開発分譲地の工事完了公告などが行われるまでに特例として建築が認められたものなど |
| 建築審査会包括同意基準3-3 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.8m以上、中心後退2m以上」 |
| 建築審査会包括同意基準3-3の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.5m以上、かつ、延長20m以下」 |
横浜市の建築審査会包括同意基準のうち、1.2.3-2に該当する「広場等に接する敷地に建築する」「公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する」「開発分譲地の工事完了公告などが行われるまでの特例」などで建築される場合は、多くの自治体で認められているため問題ありません。
しかし、「横浜市建築審査会包括同意基準3-3([路線型]と言います)」や「横浜市建築審査会包括同意基準3-3の2([専用通路型]と言います)」に該当する所の基準が自治体によって大きく異なります。
特に多いのは、間口が2m無い専用通路型の再建築不可物件で、このタイプは間口が何メートル以上あれば特例で建て替えられる可能性があるのか、自治体によって大きく異なるのです。
3-2-2.東京・神奈川の43条2項2号、包括同意基準
自治体によって建て替え出来る間口の広さが異なる事はご説明してまいりました。
そこで、本項では専用通路型に絞って自治体別の「専用通路部分の間口」と「包括同意基準」の関係について見ていきましょう。
東京・神奈川で見ていくと、間口1.5mでも大丈夫な自治体から間口が2m無いと再建築出来ない自治体まであり、条件にもばらつきがあります。
包括同意基準自体が定められたのが、平成11年以降であることが多く、包括同意基準の内容を見る事で、再建築不可物件に対しどの位柔軟な対応をしているかと、今後の街づくりの方向性が見えてきます。

神奈川県内
| 自治体 | 専用通路部分の最低の間口の広さ | その他条件 |
| 横浜市 | 1.5m以上 | 延べ面積100㎡以下、2階以下、通路部分20m以下、終端に2m四方の空地など |
| 川崎市 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分35m以下など |
| 藤沢市 | 1.8m以上 | 3階以下、通路部分20m以下、終端に2m四方の空地など |
| 鎌倉市 | 1.5m以上 | 2階以下、通路部分20m以下、終端に4m四方の空地など |
東京都内
| 自治体 | 専用通路部分の最低の間口の広さ | その他条件 |
| 大田区 | 2m以上(最低2m) | 管理者の占有許可が得られた水路など |
| 世田谷区 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分20m以下、一戸建て、最高高さ8m以下など |
| 杉並区 | 2m以上(最低2m) | 管理者の占有許可が得られた水路など |
| 渋谷区 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分20m以下など |
| 新宿区 | 1.5m以上 | 2階以下、通路部分20m以下、主要な出入り口から道路まで1.5m以上の避難通路など |
| 豊島区 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分20m以下など |
| 北区 | 1.5m以上 | 通路部分20m以下など |
| 足立区 | 2m以上(最低2m) | 管理者の占有許可が得られた水路など |
| 葛飾区 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分20m以下など |
| 港区 | 1.8m以上 | 2階以下、通路部分20m以下、75cm以上の避難通路など |
3-3.43条2項2号の許可・個別提案基準
■ 建築許可難易度 ★★★★☆☆
■ 担保評価難易度 ★★☆☆☆☆
実は、43条2項2号の許可には、「包括同意基準」とは別に「個別提案基準」というものがあります。
個別提案基準という名称は自治体によって異なりますが、「包括同意基準」が事前に同意を得ているため市長、県庁などが許可処分後に建築審査会に報告するのに対し、「個別提案基準」は、包括同意基準には当てはまらないけれども、個別に建築審査会に提案して許可された定型的なものになります。
✅包括同意基準-事前に纏めて建築審査会の同意⇒市長・県長などの許可⇒建築審査会に報告
✅個別提案基準-一つ一つ建築審査会の同意⇒市長・県長などの許可
つまり、包括同意基準は事前に審査会の同意を得ているので簡単に許可が出るのですが、個別提案基準は一つ一つの案件に対して、1ヶ月に1回程度の審査会の同意を得なければならないという事で時間がかかる上、必ずしも同意が得られるという訳ではないのです。
そして、多くの自治体では個別提案基準が設けられておりません。

3-3-1.横浜市を例にした43条2項2号の個別提案基準
横浜市を例にすると、個別提案基準として下記のようなものがあります。
横浜市では個別に建築審査会に提案するための最低限の基準として「建築審査会個別提案基準」を設けています。
| 基準 | 概要 |
| 建築審査会個別提案基準3-4 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物「空地幅員0.9m以上1.8m未満、中心後退2m以上」 |
| 建築審査会個別提案基準3-4の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地 に建築する建築物「空地幅員0.9m以上、かつ、延長15m以下」 |
| 建築審査会個別提案基準3-5 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物「空地幅員0.9m以上、中心後退1.35m以上2m未満」 |
個別提案基準においても「建築審査会個別提案基準3-4、3-5」のように[路線型]と呼ばれるタイプと、「建築審査会個別提案基準3-4の2」のように[専用通路型]と呼ばれるものがあります。
多くは[専用通路型]になりますので、次の項では[専用通路型]における他の地域の個別提案基準について見ていきましょう。
3-3-2.全国の43条2項2号、個別提案基準
個別提案基準は、包括同意基準以外の建築審査会に上げられる許可案件のうち定型的なものについて、許可できる基準を定めたものです。
個別提案基準を設けている自治体は少ないですが、もし現在再建築不可で悩まれている物件の所在する自治体に提案基準があり、条件が合致していれば再建築できる可能性が高まります。
個別提案基準では、一つ一つの案件に対し、個別に建築審査会に提案し、同意を得た上で許可されることになっていますが、個別提案基準がある自治体で提案基準に条件が当てはまらない物件の場合、再建築はほぼ不可能になります。
| 自治体 | 専用通路部分の最低の間口の広さ | その他条件 |
| 横浜市 | 0.9m以上 | 2階以下、通路部分15m以下、終端に2m四方の空地など |
| 兵庫県 | 0.6m以上 | 2階以下、通路2か所が道路に接道かつ合計2mなど |
| 大阪府 | 1.5m以上 | 2階以下、通路部分35m以下など |
3-4.43条2項2号の許可、個別審査
■ 建築許可難易度 ★★★★★
■ 担保評価難易度 ★☆☆☆☆
個別提案基準を設けている自治体では、物件が基準に当てはまらなければ、建築審査会に付議するのも難しいですが、個別提案基準が設けられていない自治体の場合、包括同意基準に当てはまらなくても個別の審査で再建築できるようになることが稀にあります。
余談ですが、建築審査会では「間口2mが無い物件の建替え」(法43条)だけでなく、「用途地域によって建てられる建物の緩和」(法48条)、「低層住居専用地域の高さの限度の緩和」(法55条)等についても審査しております。
つまり、かなり特殊な案件を個別で扱っており、建築審査会で審査する事は多岐にわたるため、「包括同意基準」にも「個別提案基準」にも当てはまらない場合、ほぼ再建築は難しいと覚悟する必要があります。

4.43条2項2号の許可、個別提案基準、個別審査は特にローンが難しい
「包括同意基準」についてはある程度不動産屋や金融関係者の間では知られておりますが「個別提案基準」というものは裏技中の裏技のようなもので、ほとんど知られておりません。
理由は、物件の担保評価も低くなり、ローンを借りれる金融機関も限りなく少なくなるためです。
個別提案基準や個別審査の案件は、建築審査会の同意を得ることはもとより、ローンを組むのも難しいので気を付けましょう。

5.再建築不可物件を売却するならURUHOME

再建築不可物件の救済措置に関しては、自治体によっても異なります。
面倒なのでいっそのことどこかにお任せしたいとお考えでしたら、是非当サイト「URUHOME」を運営する「株式会社ドリームプランニング」までこちらからお気軽にご相談下さい。
相談・査定は無料で、ご相談から最短2日で決済可能でございます。
ドリームプランニングは創業18年の実績とノウハウがあり、購入からリフォーム、売却まで自社で一貫して行うため、他社様より高くお買取りさせていただきます。
再建築不可物件の売却でお困りでしたら、お気軽にご連絡くださいませ。