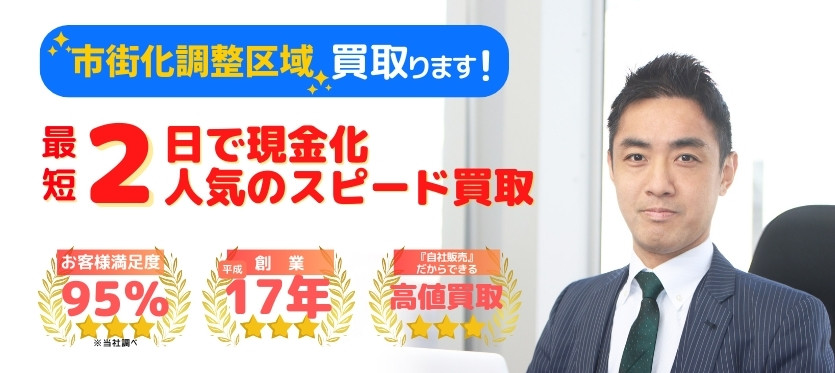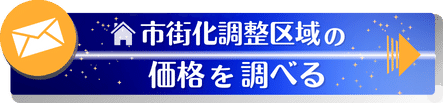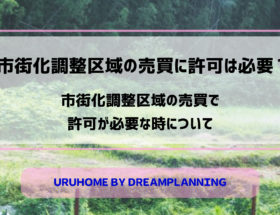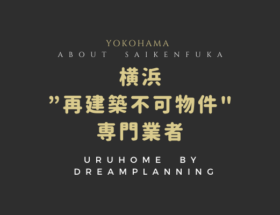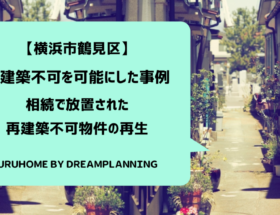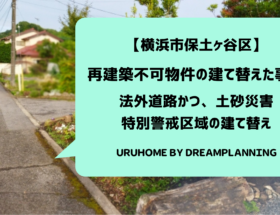市街化調整区域に家を建てようとする時、斜線制限(高さ制限)が気になる方は多いと思います。また、日影規制(にちえいきせい)も気になるところでしょう。
そこで今回は、市街化調整区域にかかる斜線制限について、不動産取引のプロフェッショナルが初心者向けに徹底解説いたします。
みなさんが市街化調整区域に家を建てる時など、ご参考になること請け合いです。
【この記事は、こんな方におすすめです】
- 市街化調整区域の斜線制限について知りたい方
- 市街化調整区域の日影規制について知りたい方
- 市街化調整区域の不動産でお悩みの方
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
1.市街化調整区域とは(区域区分とは)
このページにたどり着いた方の多くは、斜線制限という言葉をすでにご存じかと思います。
その段階であれば市街化調整区域はじめ、都市計画や建築関係の用語について、すでに初歩的知識はお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、中にはふんわりしたイメージのままで話を進めてしまっている方も、少なくないのではないかと思います。
なのでまずは予備知識として、市街化調整区域など区域区分について再確認しておきましょう。
1-1.市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法に定められた区域区分の一つ。都市計画法では、以下のとおり定義されています(第7条第3項)。
都市計画法
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
第七条(区域区分) 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
(中略)
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
ちょっと気取った言い回しですが「市街化を抑制すべき区域」と言うのは、つまり「なるべく市街化=開発しない方がいい区域」という意味ですね。
いちいち解説しなくても、雰囲気で分かりそうな市街化調整区域。
しかし、なぜ街の発展を抑えようとするのでしょうか。
街が発展するのはいいことのはずなのに……。
無秩序に市街地が広がっていくと、そっちの方もインフラ(道路や電気ガス上下水道等)を整備してあげなくてはなりません。
それらの維持コストがバカにならないため、行政としてはなるべく街をコンパクトにしておきたい事情があります。
だから市街化調整区域に家を建てるのはもちろんのこと、もろもろの開発行為には厳しい制限がかけられており、不動産取引でも敬遠されてしまうという訳です。
皆さんも、市街化調整区域の不動産をお持ちであれば、売却や活用の大変さは日々実感されているのではないでしょうか。
1-2.市街化区域とは
一方、市街化区域についてはこのように定義されています(都市計画法 第7条第2項)。
都市計画法 第7条
※参考:都市計画法|e-Gov法令検索
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
今度は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画に市街化を図るべき区域」とのこと。
ざっくり言えば(1)もう市街地として栄えている場所、(2)今後10年くらいの間に優先的&計画に発展させたい場所、といったところでしょう。
そういう行政的な事情があるため、市街化区域の開発行為(家を建てる等)については、市街化調整区域に比べてケタ違いにスムーズなはずです。
なので不動産を持っていても売却しやすいし、活用の幅も広いので、あまり悩まずにすむと思います。
1-3.非線引き区域とは
市街化調整区域でも市街化区域でもない。そんなどっちつかずの状態にある区域。
それが非線引き区域です。
線引きとは区域区分を定めること。線引きしていないから非線引き区域。
それだけの話になります。
ちなみに非線引き区域とは正式名称ではなく、都市計画法の上では「区域区分が定められていない都市計画区域内」と呼ばれています(実務では、わざわざこんな言い方はしないので、覚えなくて大丈夫です)。
市街化調整区域でも市街化区域でもないので、市街化調整区域ほど制限は厳しくないですが、市街化区域ほど開発ウェルカムでもありません。
1-4.区域区分まとめ
以上の区域区分をまとめると、以下の通りになります。
【区域区分まとめ】
都市計画法で定められている(第7条)
◎市街化調整区域…なるべく開発させたくない場所(第3項) ➤ 制限が厳しめ
◎市街化区域………積極的に開発してほしい場所(第2項) ➤ 制限が緩め
◎非線引き区域……どっちでもない場所 ➤ 制限はケースバイケース
(制限厳しめ) 市街化調整区域>非線引き区域>市街化区域 (制限緩め)
これを踏まえて、斜線制限の解説に移りましょう。
2.斜線制限(高さ制限)とは
さて、区域区分についてイメージをつかんだところで、今回の本題である斜線制限の解説に入ります。
斜線制限とは、建物の建築にかかる高さ制限の一つで、建築基準法によって定められたものです(第56条)。
一定の基準から斜線を想定して、その中(下)に収まるように建てねばなりません。
斜線制限には、基準ごとに(1)道路斜線制限(2)隣地斜線制限(3)北側斜線制限の3種類があります。
2-1.道路斜線制限とは
建築基準法
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
※別表は割愛
いきなり該当する条文を出してみましたが「……何のこっちゃ?」と思われた方がほぼ全員でしょう。
大丈夫、筆者がかみ砕いて解説します。
要するに、道路斜線制限とは建物を建てる敷地が接している「前面道路と対面敷地の境界線」を起点に斜線をひくものです。
図にすると直感的に理解できるでしょう。
斜線の角度は用途地域によって、それぞれ定められています。
しかし、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません(都市計画法第13条第1項第7号)。
そのため、市街化調整区域の斜線制限は「用途地域の指定のない区域」の基準が適用され、気になる斜線の角度(傾斜勾配)は道路幅に対して1.25倍もしくは1.5倍(※)となります。
(※)1.25倍か1.5倍のどちらが適用されるかは、ケースバイケースで判断されるそうです。
こうして道路斜線制限がかかるのですが、そのままずっとどこまでも斜線が続くわけではありません。
起点からの水平距離が一定の基準に達すると、そこから道路斜線制限は垂直になります。
つまり高さ制限が実質解除されるのです。
この一定の基準を適応距離もしくは適用距離と言い、その長さは建物の容積率によって異なります。
【用途地域の指定のない区域の適応距離】
- 容積率200%以下…………………20mまで
- 容積率200超~300%以下……25mまで
- 容積率300%超……………………30mまで
なので今回の市街化調整区域にかかる道路斜線制限は、現地の状況を見て測ることができますね。
2-1-1.道路斜線制限の後退緩和措置(セットバック緩和)
道路斜線制限には、後退緩和措置が適用されます(建築基準法第56条第2項)。
建築基準法 第56条
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
これはセットバック緩和と呼ばれることもありますが、いわゆるセットバック(自分の建物敷地を後退させ、その土地を道路として提供すること)とは違うものです。
建物を前面道路との境界線から離して建てた距離の分だけ、道路斜線の起点を向こう側へ移動できるようになります。
そうすると、角度は同じなので起点が下がった分だけ制限が緩和されました。
現実的には敷地ギリギリまで建物を建てることはあり得ないため、大なり小なりこの後退緩和措置が適用されていることになります。
ただ、このセットバック緩和についても、例えば角地であったり、向かいが水路や公園であったりなどで自治体によって異なる基準を運用している事もあります。
2-1-2.道路斜線制限の高低差による緩和(高低差緩和)
斜線制限を適用すると、道路より敷地が高くなっている場合、敷地を後退させないと道路斜線制限を厳しく受ける事になります。
そのため、道路からの高低差が1m以上になると高低差緩和が使えます。
高低差緩和とは「道路と敷地の高低差から1mをマイナスした数値の1/2」高い位置を起点にして道路斜線制限が適用される緩和措置です。
建築基準法施行令 第百三十五条の二
※参考:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
また、高低差緩和についても、自治体によって特例を設けており、「敷地の地盤面から1m低い位置を基準とする」など、緩和される自治体もあります。
2-2.隣地斜線制限とは
▶建築基準法
第56条第1項第2号
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に……(クリックで全文表示)
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ 略
ロ 略
ハ 略
ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
全文を読んだ方は頭上に?マークが飛び交っている方が多いのではないでしょうか。
こちらもかみ砕いて解説していきます。
(1)住居系地域なら20m以上、商工系地域なら31m以上の建物が制限の対象。
(2)斜線の起点は、住居系建物なら隣地との境界線から上空20m、商工系建物なら隣地との境界線から上空31m。
(3)斜線の角度は、住居系建物なら水平1:垂直1.25。商工系建物なら水平1:垂直2.5。
(4)建物の高さ限度は、住居系建物で建物外壁から隣地境界線までの距離×1.25+20mまで。商工系建物なら建物外壁から隣地境界線までの距離×2.5+31mまで。
市街化調整区域にかかる隣地斜線制限は、建てようとする建物の位置や形状によって変わってきます。
ただ、住居系で高さ20mと言えば、地上6~7階に相当する大きさです。
つまり、マンションでも建てない限り、ほとんどの方には関係ない規制ですので、ご安心ください。
2-2-1.隣地斜線制限の後退緩和措置(セットバック緩和)
多くの方には関係ないと思いますが、隣地斜線制限にも緩和措置があるので紹介します。
指定された高さ(住居系なら20m、商工系なら31m)を超えた部分について、隣地境界線より後退(セットバック)させることで、後退させた距離だけ斜線制限の起点を後退させることが可能です。
しかし、指定された高さより下の部分については後退させてもこの緩和措置は適用されないので注意しましょう。
2-2-2.隣地斜線制限の高低差の緩和(高低差緩和)
また、こちらも多くの方には関係ないのですが、建物が隣接地より1m以上低い場合、高低差から1m引いて、1/2の位置を基準にする緩和措置もあります。
▶建築基準法施行令 第百三十五条の三 (クリックで全文表示)
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
二 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。※参考:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索
2-3.北側斜線制限
詳しい方であればご存じだと思いますが、基本的に用途地域の定めのない市街化調整区域では北側斜線制限はかかりません。
ただ、自治体によって第一種や第二種などの住居専用地域に準する場合、北側斜線制限がかかる事があります。
基本的には、14種類(※1)ある用途地域のうち、5種類(※2)についてのみ北側斜線制限が設けられていますが、調整区域でも北側斜線がかかることもあるという事をご承知おきください。
(※1)全13種類+「用途地域の指定のない区域」で14種類。
(※2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の5種類。
敷地の北側=相手から見れば南側は太陽光を受けるために重要な方向ですから、南側の敷地にかかる制限は、より他の斜線制限よりも大きくなるのです。
▶建築基準法 第56条第1項
三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居…(クリックで全文表示)
三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
今度もややこしい条文ですので、こちらもかみ砕いて解説しますからご安心ください。
(1)隣地との境界線から一定の(5mまたは10m)上空を起点に、水平1:垂直1.25の角度で伸ばしていきます
(2)第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域は5mが起点
(3)第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域は10mが起点
(4)第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域は絶対高さ10mまたは12m以下(絶対高さは自治体の都市計画で決められます)
(5)北側斜線制限の計算方法
◎低層住居専用地域・田園住居地域 ➤ 水平距離×1.25+5m≧建物の高さ
◎中高層住居専用地域:水平距離 ➤ 1.25+10m≧建物の高さ
市街化調整区域に家を建てようとする時は、これまで解説してきた道路斜線制限・隣地斜線制限ともども北側斜線制限も意識しておきましょう。
自治体の担当職員に確認すれば大丈夫です。
2-3-1.北側斜線制限の緩和措置(高低差緩和)
北側斜線制限にも緩和措置が適用されることがあります。
ただし、これまでの緩和措置と違ってセットバック緩和ではなく、土地の高低差によって制限が緩和されるものです。
北側の土地が高くなっている場合、その高低差から1mを引いてから2で割った数値だけ、起点を底上げすることができます。
例えば北側の敷地が2m高かった場合は、2m-1m=1m÷2=0.5m(50cm)高い場所が起点となるのです。

3.市街化調整区域には日影規制も適用される
市街化調整区域の高さ制限は、斜線制限のほかに日影規制も適用されます。
建物の影が隣の土地になるべくかからないよう、かかる場合も最低限にとどめるよう規制するもので、建築基準法に規定されているものです。
ちなみに読みは「にちえい」規制です。
実務では通称「ひかげ」規制と言う方もいます(実は「ひかげ」が正式だと思っている方が、意外といます)。
ともあれこの日影規制、具体的にはどういう規制なのでしょうか。
3-1.日影規制とは(建築基準法第56条の2)
▶建築基準法(日影による中高層の建築物の高さの制限)……クリックで全文表示
建築基準法
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五十六条の二 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。
2 同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
4 対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
5 建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
これまた長くてややこしい条文を引っ張り出してしまいました。
それでは例によって、じっくりかみ砕いていきましょう。
(1)冬至日の真太陽時(午前8:00~午後4:00の8時間。北海道の場合は午前9:00~午後3:00の6時間)に、敷地外の一定範囲に一定時間以上の日影が生じるような建物を建ててはいけません。
(2)一つの敷地内に2軒以上の建物がある場合は、それらの建物をすべて1軒と見なします。
(3)建物の敷地が道路や河川・海などに接している場合、適用を緩和することがあります。
(4)対象区域外にある高さ10m超の建物の影がのびて、冬至日でも対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、(1)の規定を適用します。
(5)建物が日影規制の基準が異なる区域をまたいでいる場合、日影規制の適用については別途に定めます。
要は、建物を建てるときに、一定以上の日影を生じさせない規制で、設計をするときに建築士の方が計算してくれます。
※実際に日影規制で建物に大きな影響が出る事はほぼないので、ご安心ください。
3-1-1.日影規制の対象となる建物条件と用途地域
日影規制の対象となる建物は、次の通りです。
市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)についても日影規制が定められています。
【A.軒の高さが7m超、または地上3階以上の建物が規制対象となる地域】
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
【B.高さが10m超の建物が規制対象となる地域】
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
【日影規制が適用されない地域】
- 商業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
【自治体が条例で定める地域】
- 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)
条例で定めるといっても自由に決められるわけではなく、A.かB.のどちらかを適用するか選ぶことになります。
3-2.【具体例】横浜市の市街化調整区域に適用される日影規制は?
ここまで日影規制について解説してきたので、今度は具体例として神奈川県横浜市のケースをとりあげてみましょう。
横浜市の市街化調整区域にかかる日影規制は、一般区域と沿道区域に分類されます。
※参考:横浜市建築基準条例第4条の4「日影による建築物の高さの制限に関する地域等及び日影時間の指定」
※参考:日影規制の取扱い 横浜市
※参考:市街化調整区域の建築物の制限(建築基準法第52条第1項第8号ほか) 横浜市
3-2-1.横浜市の市街化調整区域にかかる日影規制(一般区域)
横浜市の一般区域で定めている日影規制の基準は以下の3点です。
(1)日影の測定は地上から1.5mの場所で行います。
(2)敷地境界から5~10m範囲では、一日3時間を超えて日影になってはいけません。
(3)敷地境界から10mを超えた範囲で、一日2時間を超える日影ができてはいけません。
3-2ー2.横浜市の市街化調整区域にかかる日影規制(沿道区域)
沿道区域というのは幹線道路(幅員18m以上。都市計画法施行規則第7条第1号)に沿って50m以内の地点を差します。
こちらも日影規制の基準を確認しましょう。
(1)日影の測定面は地上4.0mの高さとします。
(2)敷地境界から5~10mの範囲にできる日影は1日4時間以内です。
(3)敷地境界から10mを超える範囲の日影は1日2.5時間以内でなくてはなりません。
4.市街化調整区域の斜線制限でお悩みならURUHOMEへご相談を
以上、市街化調整区域にかかる斜線制限などについて解説してきました。
冒頭にもふれた通り、斜線制限について調べているということは、市街化調整区域に家を建てることをお考えの方が多いのではないでしょうか。
また、市街化調整区域の売却で、相談した不動産会社から斜線制限の話をされた方もいらっしゃるかと思います。
市街化調整区域の不動産を売却したいとお悩みであれば、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社はニッチな不動産取引のエキスパートとしてご好評をいただいており、2005年の創業以来、市街化調整区域など訳アリ不動産のお悩み相談を多数承ってまいりました。
これまで培ってきた不動産知識や取引ノウハウで、今回もお客様のお役に立てるかと思います。
皆様が持て余している市街化調整区域の不動産がありましたら、きっと当社でお買取りさせていただけると思います。
査定はもちろん完全無料、最短ではご連絡から2時間で査定完了、2日間で売却できたケースもございます。
市街化調整区域の不動産でお悩みの時は、お気軽にドリームプランニングへご相談くださいませ。