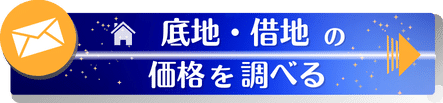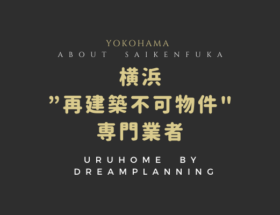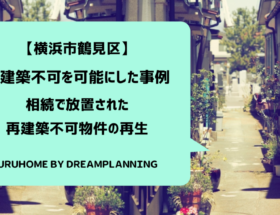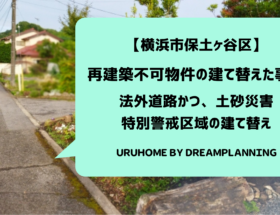借地権を取得したけど、借地権が存在しているという事をどうしたら証明できるか、考えたことはありますでしょうか?
借地権付き建物を取得したと思っていたら、地主が所有している底地が競売になり競売で土地を取得した人から「借地権は存在しない」と言われる。
そんな嘘みたいな話が本当にあります。
今回はそんな自分の借地権を主張する方法について、底地買取業者の社長が詳しく解説いたします。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の借地などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな借地でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.借地権借家法第10条【借地権の対抗力とは】
- 1-1.借地借家法10条1項の対抗要件とは
- 1-2.借地借家法10条2項の対抗要件とは
- 1-3.借地人に対抗要件が無い場合
1-1.借地借家法10条1項の対抗要件とは?
民法の特別法でもある借地借家法は、主に借地人や借家人の権利を保護するために制定された法律です。
第一章から第四章までで構成されております。
本来は土地を借りている場合には、その借りている旨を借地権の登記することで、その土地を取引する際に現れた第三者に対抗することが可能となります。(民法605条)

第605条 不動産の賃貸借は、これを登記たときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
引用:WIKIBOOKS 民法605条
こんなことが問題になるもの、地主と借地人間において、借地の登記をせずに地主が底地を手放さなくてはならなくなった場合です。
地主が底地を手放すと、地主から譲り受けた譲受人が借地人が存在することを知らないケースがあった場合、借地人が譲受人に対して借地権を主張できるかが問題になってくるのです。
こんな時に重要になってくるのが、借地借家法10条1項による対抗要件です。
1-1ー1.借地借家法10条1項とは
借地借家法10条の1項では、借地権の登記が無くても、借地上の建物が登記されていれば借地権を第三者に対抗できます。
つまり、借地権を誰にでも自分のものだと主張できるとされておりますが、登記されている建物の所在が、実際の地番と異なった為、裁判となったケースもあります。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
第十条(借地権の対抗力)借地借家法 | e-Gov法令検索
1-1-2.登記されている住所も大事
建物の登記がされていると言っても、建物が登記されている住所も大事になってきます。
実際に平成17(オ)48建物収去土地明渡等請求事件(高松高判)では、「相続により借地を取得した相続人」と「競売により地主より底地を取得した底地の取得者」が争う事になってしまいました。
この裁判においても、借地人の主張が認められましたが、登記をする際は建物の所在と土地の地番が異なっていないか注意するようにしましょう。
また、建物の登記名義人は借地人と同じ名義でないといけません。
借地権者の奥さんや兄弟名義での登記では、対抗要件になりませんので、注意しましょう。

1-2.借地借家法第10条2項とは?
他にも建物は建設された以上、状況によっては倒壊し滅失する危険性があるものです。
その場合でも借地借家法第10条によれば、建物が滅失した場合は看板を掲げておけば、それによって土地を譲り受けた第三者にも対抗することができるとされます。
対抗力を生じるためには、滅失があった日・新たに建物を築造することを記載した看板を土地の見やすいところに掲げておく必要があります。
2.前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
第十条2(借地権の対抗力)借地借家法 | e-Gov法令検索

また滅失した日より二年までに新たな建物を築造することが求められ、それ以降となると第三者に対しての対抗力が失われる可能性が高いです。
1-3.借地人に対抗要件が無い場合
借地上の建物も登記しておらず、滅失後に建物の築造をする旨の掲示をしていないなど、借地人が土地を取得した第三者に対する対抗要件を備えていなかった場合はどうなるのでしょう?
この場合は、借地権者が建物登記等を行っていなかった特別な事情があり、土地を取得した第三者が利益を得る為に悪意を持って取得し、明渡を求める場合などは権利濫用として認められない事もあります。


2.地主の借地人に対する対抗要件
底地権が売買されたとき、取得した第三者が新しい地主になります。
取得した事を借地人に主張する場合、新しい地主は土地所有権の登記をしていなければなりません。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
引用:WIKIBOOKS 民法177条
この場合、借地人は新しく地主となった第三者が土地の所有権登記を行ったうえで地代を請求してくるまで、元の地主に地代を支払う事になります。
借地上の建物が登記されていないまま土地所有権が第三者に移転してしまうと、取得した第三者に借地権を対抗できなくなることもあるので、建物登記だけでもするようにしましょう。
3.底地・借地で困ったらURUHOME
借地権を第三者に対抗するには、建物登記などが必要な事を解説してまいりました。
しかし、底地や借地が面倒になってきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんなときは、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにお任せください。
URUHOMEを運営するドリームプランニングでは、日本全国の底地・借地を積極的にお買取りさせていただいており2005年に創業して以来様々な底地・借地を買い取ってまいりました。
私共は年間300件ほどの底地相談を受けており、「再建築不可の底地」「50mの崖下の底地」「借地人110名居る底地」など、様々な底地の買取を行ってきた実績がございます。
もし、底地・借地の売却をお考えの際は、ニッチな不動産URUHOMEでお馴染み底地買取の専門業者ドリームプランニングへご相談くださいませ。