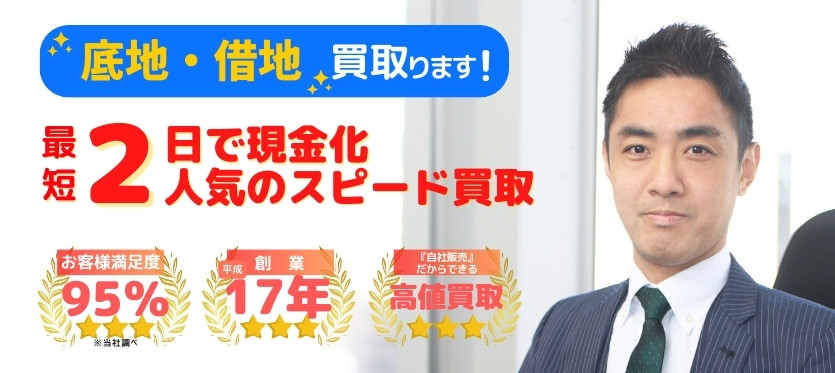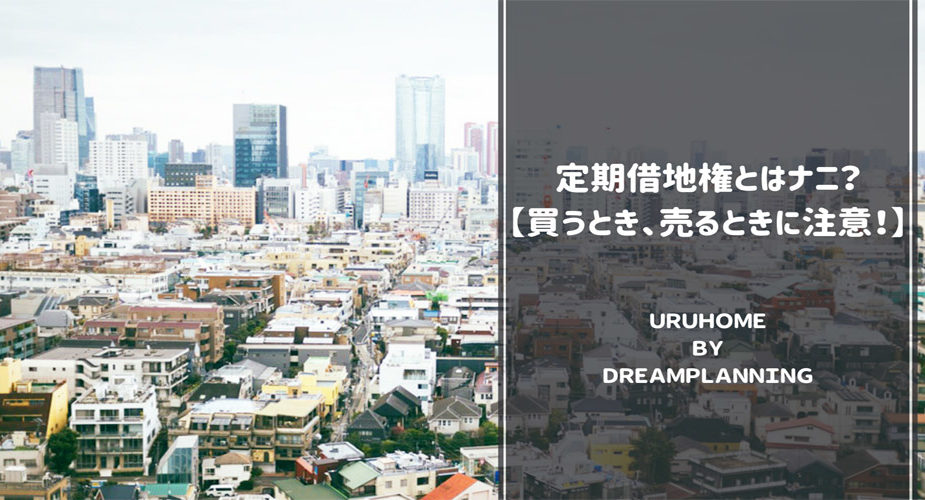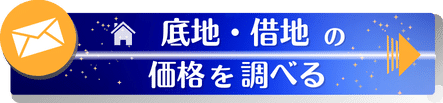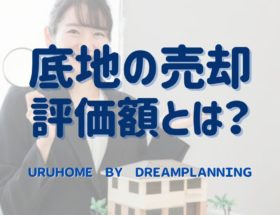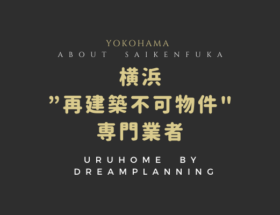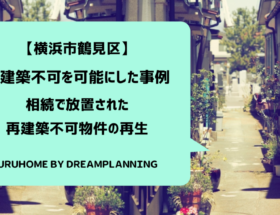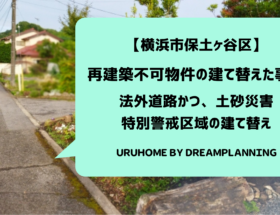「借地契約を結ぶとき、定期借地権という言葉が出たけど、どういう意味なんだろう?」
定期借地権とはどんな権利契約で、どんな種類があるのでしょうか。
また、定期借地権のメリットやデメリットも気になるところです。
そこで今回は、ニッチな不動産でお馴染みドリームプランニングの社長が、定期借地権について分かりやすく徹底解説!定期借地権つきの底地を持っている地主さんは必見です!
【この記事は、こんな方におすすめです!】
- 定期借地権について詳しく知りたい方
- 定期借地権はじめ不動産の知識を深めたい方
- 定期借地権つきの底地を売却したい方
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の定期借地などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな定期借地でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 定期借地権とは何か(借地借家法)
- 定期借地権は3種類(借地借家法第22~24条)
- 定期借地権のメリット・デメリット
- 定期借地権の根拠となっている借地借家法とは何か
- 定期借地権付き底地を売却するには?
- 定期借地権付き底地でお悩みならURUHOMEへご相談を
1.定期借地権とは何か(借地借家法)
定期借地権とは、読んで字のごとく「期間を定めて土地を借りる権利」のことです。
土地を借りる権利、すなわち借地権とは借地借家法第2条により、以下のとおり定義されています。
借地借家法 第2条
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者 借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
(以下略)
第2条第1号によれば、借地権とは「建物を所有する=建てて住むために土地を利用する権利」と言えるでしょう。
土地の借り主(借地人)を借地権者、土地の貸し主(地主)を借地権設定者と言います。
それを踏まえて、定期借地権と他の借地権の違いについて、分かりやすく解説していきましょう。
1-1.定期借地権は契約更新がないのが最大の特徴
定期借地権が他の借地権と異なる最大の特徴として、契約更新(借地期間の延長)がないことが挙げられます。
定期借地権が設定されるまでは、一度土地を貸してしまうと更新を繰り返されて拒絶できず、半永久的に土地が返ってこない状況でした。
それを防ぐために、期限が来たら延長なしで土地を返還する定期借地権が設定されたのです。
1-1-1.定期借地権の残存期間終了後は建物を解体、更地で返還
定期借地権は契約期間(残存期間)が終了すると、原則として建物を解体して更地で地主に返さなければなりません。
※例外として、建物譲渡特約付借地権は土地を建物付きで引き渡します。
1-1-2.定期借地権の契約終了に正当事由は不要、立退料も不要
定期借地権は残存期間が終了したら、ただちに借地契約が終了します。
通常の借地権だと必要になる更新拒絶の正当事由は必要ありませんし、借地人に対して立ち退き料を支払う必要もありません。
※正当事由とは、地主が自分でその土地を使う必要がある場合などです。
1-1-3.定期借地権に建物買取請求権はなし
通常の借地権だと、契約終了時に借地上の建物を地主に買い取ってもらう建物買取請求権が設定されています。
しかし定期借地権の場合は建物買取請求権がありません。
地主は建物を買い取る義務がなく、建物が不要ならば借地人に解体させ、更地で返してもらえるのです。
1-2.普通借地権とは(借地借家法第3~8条)
契約期間の更新延長がない定期借地権に対して、普通借地権は借地借家法第6条に規定される正当の自由(更新拒絶の要件)がない限り借地契約を更新できます。
借地借家法 第3~8条 【長いため、クリックで全文表示】
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第七条 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第八条 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
条文をまとめると契約の存続期間は原則として30年以上。更新する時は最初が20年以上、2回目以降は10年以上の期間を設定しなければなりません。
土地利用目的や契約方法(口頭・書面・電磁的記録・公正証書など)に制限はなく、返還する時は原則更地にしますが、建物買取請求権も定められます。
普通借地権では地主よりも借地人が保護されており、借地借家法第9条に借地人に不利な特約を無効とする強行規定が定められているのも特徴的です。
借地借家法 第9条
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
1-3.一時使用目的の借地権とは(借地借家法第25条)
借地人と地主のバランスをとるように努めている借地借家法ですが、明らかに一時使用目的の借地権については強い規定の対象外としています。
借地借家法
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
(一時使用目的の借地権)
第二十五条 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
つまり誰がどう見ても「ちょっと貸すだけ・借りるだけ」なら細かいことは別にいいよ、ということでしょう。
ちなみに「一時使用とはどのくらいの期間なのか?」という疑問については最高裁が判決(昭和42・1967年3月28日)を出しています。
※参考:判決全文
長いのでかみ砕くと「お互いが一時的な貸借であると合意が成立し、かつ客観的に見て合理的と判断できれば一時使用に当たる」程度に解釈すれば大丈夫でしょう。
1-4.旧法借地権とは(借地法)
借地借家法は1992年に改正されたもので、それ以前の借地関係は借地法という法律で管轄していました。
この借地法は現在使われていないため、旧法とか旧借地法と呼ばれています。
ただし、借地借家法が成立する以前の借地契約については旧借地法が適用されているため、完全に無効となった訳ではないので注意しましょう。
借地法
(借地権の存続期間)
第二条
借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス
但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
二 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付三十年以上、其ノ他ノ建物ニ付二十年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス
昔の法律は、カタカナ表記で読みにくいですよね。こちらも条文をかみ砕いておきましょう。
借地権の存続期間は、堅固な建物(石造・土造・レンガなど)の場合は60年以上、その他の材質(木造など)の場合は30年以上となります。
これより長く設定するのは大丈夫ですが、短くしてはいけません。
第2項は定期借地権についての規定です。堅固な建物であれば30年以上、その他の建物について20年以上の期間を契約で定めた場合、期間満了をもって借地権が消滅します。
2.定期借地権は3種類(借地借家法第22~24条)
一口に定期借地権と言っても、その内容は(1)一般定期借地権(2)事業用定期借地権(3)建物譲渡特約付き借地権の3種類があります。
ここでは、それぞれについて詳しく解説していきましょう。
- 2-1.一般定期借地権とは何か(借地借家法第22条)
- 2-2.事業用定期借地権とは何か(借地借家法第23条)
- 2-3.建物譲渡特約付借地権とは何か(借地借家法第24条)
- 2-4.定期借地権・普通借地権・旧法借地権のまとめ
2-1.一般定期借地権とは何か(借地借家法第22条)
一般定期借地権とは、その名のとおり定期借地権の基本となるもので、借地借家法第22条に規定されています。
借地借家法
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
なお、借地借家法の条文に一般定期借地権という言葉はなく、厳密には定期借地権のみ。他の定期借地権と区別する関係で一般とつけていることを覚えておいてもいいでしょう(今回は便宜上、一般定期借地権で統一)。
一般定期借地権の存続期間は50年以上、土地の利用目的に制限はありません。
契約方法については書面または電磁的記録とされ、言った・言わないでトラブルになりがちな口頭では無効となります。
2-2.事業用定期借地権とは何か(借地借家法第23条)
事業用定期借地権とは、こちらも文字通り事業用に土地を貸し出す定期借地権で、借地借家法第23条に規定されているものです。
借地借家法 第23条 【クリックで全文表示】
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満。他の定期借地権と異なり、最長限度が定められているのが特徴ですね。
事業用定期借地権における土地の利用目的は事業用建物の所有だけが認められ、居住用の建物は認められません。
また、契約方法は公正証書に限られます。普通のペーパー書面や電磁的記録(メールやpdfなど)ではダメなのですね。覚えておきましょう。
2-3.建物譲渡特約付借地権とは何か(借地借家法第24条)
借地借家法 第24条 【クリックで全文表示】
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間が終了した後に土地を建物付きで返す特約を設けた定期借地権です。
通常の借地権や定期借地権が、契約終了後に建物を解体して更地で返すのに対して、建物を取り壊さずに引き渡す特約がつけられている点に特徴があります。
名称中に定期という言葉は入っていませんが、れっきとした定期借地権の一種。
契約の存続期間は30年以上、土地の利用目的や契約方法については制限がありません。
2-4.定期借地権・普通借地権・旧法借地権のまとめ
以上、各種の定期借地権について解説してきました。ここではそれぞれの違いについて一覧表にまとめています。
| 一般 定期借地権 | 事業用 定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 普通借地権 | 旧法借地権 | |
| 契約期間 | 50年以上 | 10年以上 50年未満 | 30年以上 | 30年以上 | 堅固建物60年以上 それ以外30年以上 |
| 契約更新 | なし | なし | なし | 最初20年以上 2回目以降10年以上 | 堅固建物30年以上 それ以外20年以上 |
| 利用目的 | 制限なし | 事業用建物のみ | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 建物買取 請求権 | なし | なし | 建物譲渡特約あり | あり | あり |
| 契約期間 終了時 | 更地で返還 | 更地で返還 | 建物付きで返還 | 契約更新可能 | 契約更新可能 |
| 契約方法 | 書面又は 電磁的記録 | 公正証書に限る | 制限なし | 制限なし | 制限 |

3.定期借地権のメリット・デメリット
ここでは定期借地権の性質を踏まえた種類別のメリット・デメリットを解説していきましょう。
ただメリット・デメリットと言ってはいますが、状況によって違ってくるため、一概には言えません。デメリットをなるべく抑えつつ、メリットを最大限に引き出せる活用を考えたいですね。
3-1.一般定期借地権のメリット・デメリット
一般定期借地権は存続期間が50年以上の長期となっているため、借地人としてはしっかり利活用することが出来ます。
地主としても決まった期間が経過すれば更新なしで確実に返還されるので、土地の利用計画を立てやすいメリットがあると言えるでしょう。
ただし、定期借地契約で定めている期間中は移動が難しいデメリットもついて回ります。
期間満了前に借地人が「別の土地を借りたい」と思ったり、地主が「土地を返して欲しい」と思っても、双方の合意がない限りは制限がかかってしまうのです。
3-2.事業用定期借地権のメリット・デメリット
事業用定期借地権は、土地の用途が事業用建物に限られるため、地主とすれば土地が変な(あらかじめ定められていない)ことに使われにくいメリットがあります。
また、期間が最低10年と短めなので、早めに返してもらえる点も地主から見てメリットと言えるでしょう。
デメリットとしては、借地人が事業に失敗しても撤退が難しく、また事業に成功しても同じ借地での継続が難しい点が挙げられます。
3-3.建物譲渡特約付借地権のメリット・デメリット
建物譲渡特約付借地権は貸した土地が建物付きで返してもらえるため、地主とすれば建物が土地の利息のような気分で貸し出せるでしょう。
ただし、借地人がどのような建物を建てるかまで指定することはできないため、土地活用次第では建物がかえって邪魔になってしまうケースも考えられます。
借地人の立場で考えれば、契約期間終了後は建物を解体して更地で返さねばならないところを、建物付きということでそのまま返せる点はメリットと言えますね。
4.定期借地権の根拠となっている借地借家法とは何か
定期借地権は借地借家法が根拠となっています。ここでは、借地借家法の歴史についてごく簡単にふれておきましょう。
4-1.借地法+借家法+建物保護に関する法律=借地借家法
借地借家法は平成3年(1991年)9月30日に成立。同年10月4日に公布され、平成4年(1992年)8月1日から施行されました。
それ以前は借地については借家法(1921年成立)、借家のことは借家法(1921年成立)、また建物自体については「建物保護に関する法律(1909年成立)」とそれぞれ分かれていました。
これらの法律を統合したのが借地借家法というわけです。
4-2.借地借家法の歴史・地主と借地人の力関係
土地を貸し借りする借地の歴史をたどると非常に長くなってしまうので、ざっくり近代以降に焦点を絞りましょう。
先ほど紹介した借地法・借家法・建物保護に関する法律が出来る前は地主の力が非常に強く、借地人はいつ追い出されても不思議ではない不安定な状態でした。
それがこれらの法律ができたことによって、借地人が持つ居住・建物保護などの権利が認められるようになります。
すると今度は借地人の権利が強くなりすぎてしまい、地主たちは「一度土地を貸したら最後、半永久的に戻ってこない」などと嘆くことに。
これを解消するために、借地借家法の導入で地主と借地人の権利関係を調整。互いの力関係が対等に近づいたのでした。
今後も時代の移り変わりによって法律が見直され、よりよい形が模索されていくことでしょう。

5.定期借地権付き底地を売却するには?
ここまで定期借地権について解説してきましたが、定期借地権付きの底地を持て余している地主さんも少なくないかと思います。
では定期借地権付きを売却する上で気になる売却相場や売却先について、詳しく解説していきましょう。
5-1.定期借地権付き底地の売却相場は?
定期借地権付き底地の売却相場は、定期借地権の残存期間=自分の手元に土地が戻ってくるまでの期間が短いほど高くなります。
【定期借地権付き底地の売却相場】
定期借地権の残存期間が5年未満………約80~90%
定期借地権の残存期間が10年未満……約75%
定期借地権の残存期間が15年未満……約60%
定期借地権の残存期間が15年以上……約50%以下
※特別な権利関係のない更地価格を100%とした場合。
※不動産取引に携わってきた中での肌感覚なので、ご参考まで。
その他、様々な条件によって実際の売却相場は大きく変動します。詳しくはドリームプランニングまでご相談くださいませ。
5-2.定期借地権付き底地の売却先は?
定期借地権付き底地が上記の相場で売却できるとして、それでは誰に・どのように売却しましょうか。
その候補としては一般的に(1)個人間(2)不動産会社の仲介(3)買取専門業者などが考えられます。
5-2-1.定期借地権付き底地の個人間売買はトラブルの温床
一番シンプルなようで、一番トラブルを抱え込みやすいのが個人間売買。
権利関係が複雑にからみ合っている不動産、今回の定期借地権付き底地などは法律知識がないと、後から面倒ごとを惹き起こしかねません。
ここは多少のコストを支払ってでも、不動産取引のプロに入ってもらうことを強くおすすめします。
5-2-2.定期借地権付き底地は不動産会社にも敬遠されがち
では、不動産会社の仲介によって定期借地権付き底地を売却するのはどうでしょうか。
やはり餅は餅屋、不動産取引に必要な法律知識や交渉ノウハウで地主の心強い味方になってくれるはず……ですが、中には面倒な定期借地権付き底地の仲介を嫌がる不動産会社も少なくありません。
手続きが面倒な割にもらえる仲介手数料が限られているため、だったら少しでも楽でコスパのいい仕事を選んでしまうのが人情というもの。
「この定期借地権付き底地は取り扱いが難しいですね……」
既にそう言われてしまい、途方に暮れている方も、少なくないのではないでしょうか。
5-2-3.定期借地権付きの底地は専門業者の買取りがおすすめ
定期借地権付き底地をどうしても売却したいのであれば、専門業者による買取りがおすすめです。
一般的な不動産会社と異なり、買取専門業者は定期借地権付き底地の取り扱いに慣れていることから、快く引き受けてくれることでしょう。
仲介手数料がかからないのも魅力ですが、自社買取りをしていない会社が他の買取専門業者を仲介していると、仲介手数料が発生してしまいます。
なので定期借地権付き底地の売却を検討している時は、自社で買取りをしている業者かどうか確認しておきましょう。
6.定期借地権付き底地でお悩みならURUHOMEへご相談を
以上、定期借地権の性質や定期借地権付き不動産の売却などについて解説してきました。
定期借地権がついている不動産は残存期間が終了するまで土地が返って来ず、非常に取り扱いが煩雑です。
もし定期借地権付きの不動産でお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを契約しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年の創業以来、神奈川・東京を中心に定期借地権付きの不動産取引を数多く手がけており、私たちのノウハウを今回もお悩み解決に役立てられると思います。
定期借地権付き底地の買取り査定は完全無料、お急ぎの方には最短でご依頼から2時間で査定&2日間で買取りできたケースもございました。
持て余している定期借地権つき底地のスピード売却&現金化をご希望の方は、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。