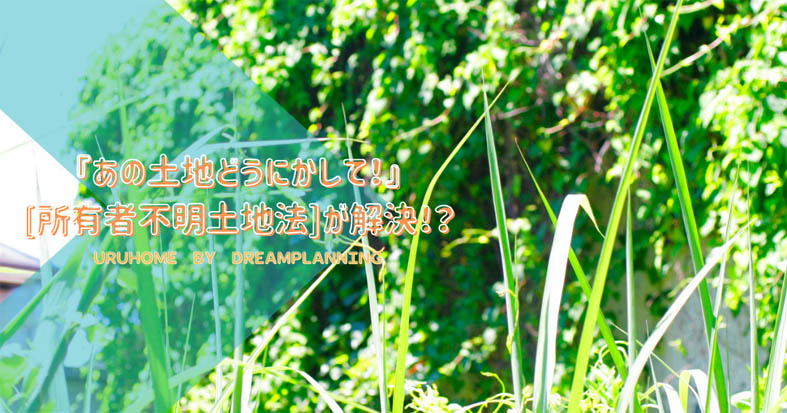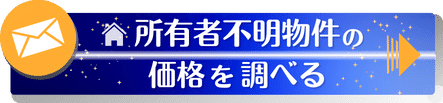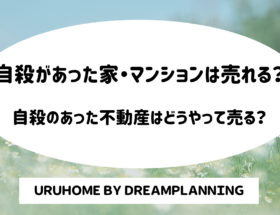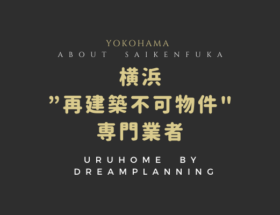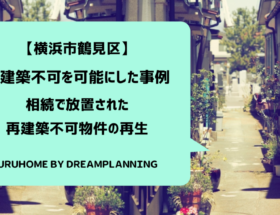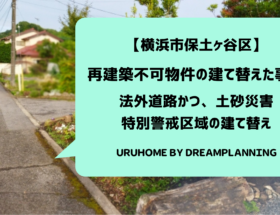「あの荒廃した空き地、空き家どうにかならないの?」
近所で誰の土地かわからない、整備がされていない土地はありませんでしょうか?
これらの土地を解決に役立つかもしれないのが「所有者不明土地法」と「所有者不明土地の関連法」です。
今回は「所有者不明土地法」や「関連法」とはどんな法律か、ニッチな不動産に詳しいURUHOMEが解説いたします。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の所有者の分からない土地や共有持分、底地、借地など特殊な不動産を専門的に買い取るため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達のノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てたく思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.所有者不明土地法が制定された背景
所有者不明土地法は、正式名称『所有者不明土地の円滑化に関する特別措置法』と言います。
制定の背景には、人口減少・少子高齢化が進み、都市部以外では土地の利用ニーズと所有意識が低下しており、相続などが発生しても登記を行わないことなどから、所有者不明の土地が増えています。
こうした所有者不明土地の活用や、適正管理を円滑に行うため、所有者不明土地法が制定されました。
まずは、所有者不明の土地の現状や、我が国の所有者不明土地の対策についてみていきましょう。
1-1.所有者不明土地法の背景①所有者不明土地が全国的に増加しております
【所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法】(所有者不明土地法)は当初平成30年6月6日に成立しました。
その後、令和4年4月27日に改正され、改正所有者土地法は11月1日に施行されました。
平成18年では所有者不明土地は12.2%でしたが、平成28年では約22.9%と約2倍になりました。
ちなみに、所有者不明土地の面積は410万haで、増加防止策が進まない場合、2040年には720万haに増加と推計されます。(それぞれ九州[367万ha]、北海道[780万ha]に相当)
これは登記簿上の所有者が確認できない土地の割合で、探索をすれば所有者を特定出来ない土地は減るのですが、10年の間で所有者と連絡が取れない土地が2倍にもなってしまったのです。
この背景には人口減少、少子高齢化の問題が関わっており、土地利用ニーズが低下し地方から都心部への人口移動が進んだため、特に地方で所有者不明土地が増加しました。
所有者不明土地問題研究会最終報告によると、所有者不明土地の経済的損失は、機会損失や管理不全のコストで単年で約1,800億円/年(2016年)、2040年までの累積で約6兆円に相当すると試算されています。
所有者不明土地は、都市開発やインフラ整備で多大な時間・費用・労力を要する上、進捗の遅れや区域変更を余儀なくされるなど、円滑な事業実施に大きな支障があること、美観や防災、防犯の面からも所有者不明土地問題の利用の案決かと管理の適正化が重要になっています。
1-2.所有者不明土地法の背景②所有者特定のための費用削減と、土地の円滑利用
平成28年に所有者不明土地が22.9%あるとご説明しましたがこれは「不動産登記簿謄本で所有者が確認できない、若しくは連絡が取れない土地」であって、厳密に言うと、何をどうしても所有者が特定できないわけではありません。
実際に探索の結果、最終的に所有者が不明な土地については0.41%程度になります。
しかし、所有者特定のためには膨大なコストを要するため、円滑な土地利用の大きな障壁となっていました。
そして、この問題を解決するため「所有者不明土地」を利用して地域のために事業を行うことを可能とする「地域福利増進事業」が創設されました。
地域福利増進事業によって、地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO法人、自治会など誰でも空き地を地域住民の福祉や利便の増進のための施設を整備できるようになりました。
1-3.所有者不明土地法の背景③所有者不明土地対策の経緯
所有者不明土地法の改正までに、以下のような流れをたどりました。
大きくは、土地利用の円滑化、管理の適正化による『所有者不明土地法の制定・改正』と所有者不明土地を減らすための対策として『関連法[民事基本法制の見直し]』が行われました。
〇平成30年1月 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議 立ち上げ
〇平成30年 所有者不明土地法 制定
・地域福利増進事業の創設
・土地収用手続の合理化・円滑化
・所有者探索のための公的情報の利用等の特例 等
〇令和元年2月 土地基本法改正
・土地の「適正な管理」を土地政策の基本理念として明確化
・土地所有者等の責務を規定
〇令和3年 民事基本法制の見直し
・【民法・不動産登記法等 改正】相続登記の申請義務化/管理不全土地管理制度の創設 等
・【相続土地国庫帰属法 制定】相続土地国庫帰属制度の創設
〇令和4年 所有者不明土地法 改正
・地域福利増進事業の拡充(対象事業等)
・管理不全所有者不明土地の管理適正化の措置
.jpg)
2.所有者不明土地法の概要
所有者不明土地法では、「地域福利増進事業」といって、都道府県知事が所有者不明土地に対して使用権設定をして、最大20年地域住民等の福祉や利便の増進を図る施設を整備できる制度や、「管理不全の土地」に対して行政代執行ができる権限を市町村長に付与するなど、土地の利活用や管理を円滑化するための仕組みづくりがされました。
- 2-1.所有者不明土地法とは①所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
- 2-2.所有者不明土地法とは②所有者探索を合理化する仕組み
- 2ー3.所有者不明土地法とは③所有者不明土地を適切に管理する仕組み
- 2-4.所有者不明土地法とは④所有者不明土地対策の推進体制の強化
2-1.所有者不明土地法とは①所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
所有者不明土地法では、所有者不明の土地を円滑に利用できるようにするため、反対する権利者がいない、利用されていない土地について、以下の仕組みが構築されました。
- 公共事業における収用手続の合理化・円滑化(令和元年6月1日施行)
国や都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に変わり都道府県知事が裁定する。
審理手続きを省略、土地取得裁決・明け渡し裁決を一本化 - 地域福利増進事業の対象事業の拡充、事業期間の延長
都道府県知事が公益性を確認、一定期間の公示、市区町村長の意見を聞いた上で、広場、公民館、災害関連施設として利用できるほか、購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合、都道府県知事が最大20年の利用権を設定(令和4年11月1日施行)
「地域福利増進事業」とは
- 所有者不明土地を利用して、地域住民等の福祉や利便の増進を図る施設を整備できる制度です
- 一定希望以上の建築物がなく、利用されていない所有者不明土地で行うことが出来ます
- 土地使用権の取得の裁決を受けることで、令和4年の法改正によって最長20年間所有者不明土地を利用可能
- 民間企業やNPOなど誰でも事業可能です
2-2.所有者不明土地法とは②所有者不明土地を適切に管理できる仕組み
所有者不明土地については、荒廃した土地利用の他に、「どのような管理をするか」も大きな問題となっております。そこで土地管理をしやすくするために、以下の制度を創設しました。
- 土地等権利者関連情報の利用及び提供(平成30年11月15日施行)
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設 - 管理適正化のための勧告・命令・代執行(令和4年11月1日施行)
管理不全の所有者不明土地に関して、災害発生等を防止するため、勧告・命令・代執行の権限を市町村長に付与 - 所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度に係る民法の特例(令和5年4月施行)
地方裁判所に対して、地方公共団体の長が土地管理命令や管理命令の請求権を付与
2-3.所有者不明土地法とは③所有者の探索を合理化する仕組み
所有者不明土地法の制定の背景には、所有者不明土地の増加以外にも、所有者特定に膨大な費用がかかることはご説明しましたが、不明土地の所有者を特定しやすくするために、以下のような仕組みが創設されました。
- 土地等権利者関連情報の利用及び提供(平成30年11月15日施行)
土地所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設 - 長期相続完了等未了土地にかかる不動産登記法の特例
長期間相続登記がされていない土地について、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録出来る制度を創設
2-4.所有者不明土地法とは④所有者不明土地対策の推進体制の強化
所有者不明土地の問題は、地域を挙げて着実に取り組む仕組みづくりが必要と考えられています。
そこで、所有者不明土地などの活用に取り組んでいる特定非営利活動法人等に対して、市町村の補完的な役割を担うような仕組みづくりを進めました。
- 所有者不明土地対策に関する計画及び協議会(令和4年11月1日施行)
市町村が、所有者不明土地の利用や管理の適正化のため、所有者不明土地対策協議会の設置が可能になりました。 - 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度(令和4年11月1日施行)
市町村長は、特定非営利活動法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定が可能になりました。
3.所有者不明土地法と新しい関連法
所有者不明土地法では、所有者不明土地の利活用や、管理に関する円滑化を目的としていますが、それだけでは所有者不明土地自体を減らすのは困難です。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するための関連法として、「改正不動産登記法」「相続土地国庫帰属法」「改正民法」など、民事基本法制の見直しが行われました。
- 3-1.所有者不明土地法の関連法①改正不動産登記法【相続登記を義務化】
- 3-2.所有者不明土地法の関連法②相続土地国庫規則法 【管理できない土地を国庫に】
- 3ー3.所有者不明土地法の関連法③改正民法【所在不明の共有者のいる土地を売却可能に】
3-1.所有者不明土地法の関連法①改正不動産登記法【相続登記を義務化】
所有者不明土地法に関連する法律で、不明土地の解決のためにいくつかの関連法案も改正、制定されました。
1つ目は『不動産登記法の改正』です。
これは2024年を目処に施行される事になっておりますが土地や建物の相続を知ってから3年以内の登記を義務付けるものです。
また、相続の際の手続きも簡素化され、相続人のうち1名の申し出で簡単に相続登記手続きを出来るようにするものです。
相続登記には所有者全員の戸籍などの書類が必要でしたが、手続きを簡素化することで登記をしやすくすれば、所有者不明土地も減るはずです。
全国には所有者が分からないために開発事業の妨げになっていることも多いのですが『改正不動産登記法』では、相続登記を義務化、簡素化することにより、所有者不明土地の発生を抑えることを目的としております。
「改正不動産登記法」のポイント
- 相続登記・住所変更登記の申請義務化
取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付け、住所等の変更から2年以内に登記の申請を義務付ける - 相続登記・住所変更登記の手続の簡素化
1⃣ 相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたことになります
2⃣ 特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行
3⃣ 登記官が、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報、死亡等の情報を取得し反映出来るようになります
3-2.所有者不明土地法の関連法②相続土地国庫規則法 【管理できない土地を国庫に】
所有者不明土地関連法案の2つ目は「相続土地国庫規則法」(令和5年4月27日施行)です。
この法案によって望まない土地や利用価値が乏しい土地を相続や遺贈によって取得した人は不要な土地を国庫に納付できるようになります。
法務局による審査を経て、10年分の管理費相当額を払えば国に納められることになります。
ちなみに、納付したい土地が共有地の場合、共有者全員で申請しなければなりません。
納付された土地は国が公共の用途に利用できるよう一般競争入札などを通じて売り、成立しなければ国が管理することになります。
下記のような土地はこの制度は利用できません
・通路など他人によって使用される土地
・建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
3-3.所有者不明土地法の関連法③改正民法【所在不明の共有者のいる土地を売却可能に】
- 所在不明の共有者を除外して共有地を利用、売却可能(令和5年4月1日施行)
共有不動産を利用、売却しやすく仕組みとして、所在不明である共有者等以外の共有者の同意を取ることにより、共有物を造成したり、管理できるような制度が創設されました。
それ以外にも、裁判所の許可を得て相当する金銭の供託により、「所在不明な共有者の持分を取得して、不動産の共有解消する仕組み」が創設されました。 - 所有者不明土地の財産管理制度の創設
長期間放置されている土地と建物について他人の権利が侵害される恐れがある場合、裁判所が管理人を選任することができる制度が創設されました。
また、裁判所が選任した管理人が、裁判所の許可を得て、所有者不明土地と建物を売却出来るようになります。 - 長期間経過後の遺産分割の見直し(令和5年4月1日施行)
相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる分割の利益を消滅させ、法定相続分で簡潔に遺産分割を行う仕組みを創設
- ライフラインの設備設置権等の規律の整備(令和5年4月1日施行)
ライフラインを自己の土地に引き込むため「給排水管等の設備を他人の土地に設置する権利」を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備
当サイト「URUHOME」を運営する「株式会社ドリームプランニング」では所有者不明土地の所有者を探すお手伝いをさせていただく場合や、共有者と連絡が取れない共有持分などの買取も行っております。
共有者と連絡が取れない土地でも買取いたしますので、こちらからお気軽にご相談下さいませ。
相談・査定は無料でございます。
.jpg)