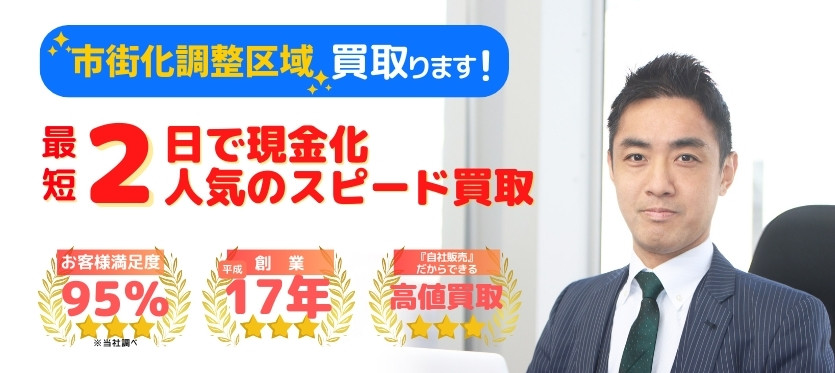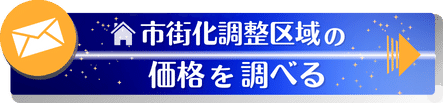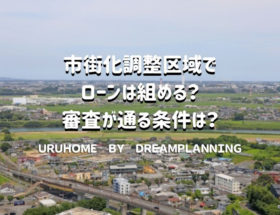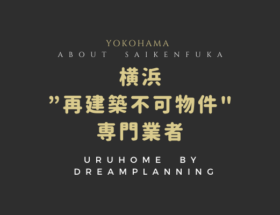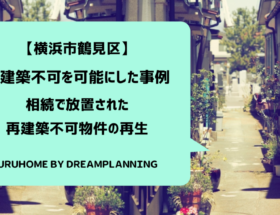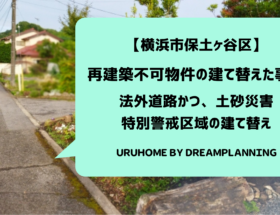市街化調整区域の不動産は、市街化区域の不動産に比べて色々と制約がかかってしまいます。
「市街化調整区域が、制約の少ない市街化区域になってくれないかな……」
なんて思った方も少なくないと思います。でも、そんな事があるのでしょうか。
実は、都道府県が行う「線引き見直し」によって、市街化調整区域が市街化区域に変更される事例が少なからず存在します。もちろんその逆もなくはないのですが……。
そこで今回は、市街化調整区域が市街化区域に変わるチャンス「線引き見直し」について、不動産のプロフェッショナルが徹底解説いたします。
【この記事は、こんな方におすすめです】
- 線引きの基本と「線引き見直し」について知りたい方
- 市街化調整区域が解除され、市街化区域になる可能性を知りたい方
- 市街化調整区域の不動産でお悩みの方
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より市街化調整区域などの売却の難しい不動産を専門的に買い取ってまいりました。
大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、無料査定を行い、1億円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 1.区域区分について(都市計画法第7条)
- 2.区域区分(線引き)の見直しについて
- 3.神奈川県で行われたケース(第7回線引き見直し)
- 4.線引き見直しで、あなたにできることはある?
- 5.市街化調整区域の不動産でお悩みなら、URUHOMEへご相談を
1.区域区分について(都市計画法第7条)
それではさっそくはじめましょう。
まずは予備知識として、市街化区域と市街化調整区域の「線引き(区域区分)」について、基本的な用語などをおさえていきます。
線引きは都市計画法という法律をもとに決められており、都市計画区域を以下の3つに区分しています。
1-1.市街化区域とは(第7条第2項)
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
※都市計画法第7条第2項
いきなり法律の条文を持ち出してみましたが、地主さんみんなの憧れ?市街化区域はこのように定義されています。
小難しい文章をかみ砕くと、要するに「すでに街として賑わっている場所や、今後10年間で積極的に開発したい場所」という程度の意味です。
行政としては積極的に開発して欲しいからこそ、許可基準が比較的緩め。だから地主が自分で活用(建築・増改築など)したり、活用してくれる人に売却したりが比較的自由にできます。
1-2.市街化調整区域とは(第7条3項)
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
※都市計画法第7条第3項
一方、市街化調整区域の方はなんだかあっさりしていますね。
「市街化を抑制」なんてカッコよく言っていますが、要するに「なるべく開発したくない&してほしくない場所」程度の意味です。
なるべく開発したくないって……街がどんどん発展するのはいいことじゃないの?と思われるかも知れません。
しかし街が無計画に広がってしまうと、辺境の方までインフラ(道路や電気ガス水道など)を整備しなければならず、維持コストがかさんでしまいます。
だから、行政としてはなるべく市街地をコンパクトにとどめておきたいのです。
なるべく開発してほしくない事情があるから、あえて市街化調整区域を開発・売買しようという人には様々な嫌がらs……もとい制限をかけるのです。
自分で活用するのはもちろんのこと、誰かに売却するのも一苦労することでしょう。
地主の皆さんが市街化調整区域の不動産を持て余してしまうのは、こういう事情によります。
1-3.非線引き区域とは(区域区分が定められていない都市計画区域内)
市街化区域でもなければ、市街化調整区域でもない……それが非線引き区域。
要するに「どっちでもない、線引き(指定)されていない場所」ということです。
ちなみに、非線引き区域という呼び方は都市計画法で定められたものではなく、行政の手続きや不動産取引における慣習の中で根づいたものでした。
都市計画法の表現では「区域区分が定められていない都市計画区域内」となります。
この呼び名についても厳密な定義はされておらず、条文の中で「どっちにも線引きされていない場所」をそのように呼んでいるから、そうなったという程度です。
※実務的には「非線引き区域」で十分通用しますから、正式名称?は覚えなくて問題ないでしょう。
ちなみにこの「区域区分が定められていない都市計画区域内」という言葉は、都市計画法の全体で4ヶ所登場します(第13条八号、十三号、十四号、第57条……これも覚えなくて大丈夫です)。
非線引き区域は文字通り線引きがされていない(区域区分が定められていない)ので、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。
そのため、市街化調整区域よりは制限が緩めな印象を受けます。
ただし市街化区域と決まったわけでもありませんから、市街化区域よりは許可などの判断基準が微妙な感じです。
ケースバイケースなので、開発許可などを求める際は自治体に確認しましょう。

2.区域区分(線引き)の見直しについて
さて。基本的な用語をおさえてきましたが、そもそも線引き制度とはどのようなものでしょう?
また、線引き見直しに関する専門用語も出てくるため、その辺りも解説してまいります。
2-1.線引き制度とは?
線引きとは都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備・開発及び保全の方針)に基づき、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市計画区域を区分するものです。
※都市計画区域マスタープラン:概ね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について都市計画の目標、区域区分の決定の有無などを示したもの。
また、社会・経済の情勢変化を踏まえ、下記2つの基本的基準により区域区分の見直しを決めています。
- 都市計画区域のマスタープラン等の基本方針
(都市計画の目標・主要な都市計画の決定方針) - 区域区分を行うための技術基準
(市街化区域への編入基準・市街地調整区域への逆線引き基準)
線引きは数ヶ月・数年という短期的な目線ではなく、概ね10年後の変化を見据えた中長期的な都市計画をもとに見直されるものです。
防災強化や自然保護など、魅力的な街づくりを進める上で線引きを見直す必要があるか、将来的に支障が出ないかなどが厳格に審議されることになります。
2-2.線引き見直しにおける専門用語
線引き見直しにおける用語には、以下のようなものがあります。
知らなくても問題ありませんが、自治体の職員などが口にした際「こういう意味だな」と話を理解しやすくなるでしょう。
言うまでもなく、分からないことがあったら用語の意味も含めて確認するのが鉄則です。
2-2-1.線引き見直しにおける「編入」とは
➤【市街化調整区域 → 市街化区域】
市街化調整区域を市街化区域に変更することを言います。
「君(区域)も市街地に入れてあげるよ」みたいにイメージすると覚えやすいでしょう。
2-2ー2.線引き見直しにおける「逆線引き」とは
➤【市街化区域 → 市街化調整区域】
こちらは逆で、市街化区域だった場所が市街化調整区域に変更されることを言います。
線引きに「逆」を冠するのは、線引きという行為自体が「線を引いて囲った中が市街化区域だよ」という意思表示であるためでしょう。
つまり線引きによって囲い込むのではなく「逆にしめ出されてしまった」イメージですね。
2-2-3.線引き見直しにおける「保留制度」とは
これは何らかの原因で人口が急激に増加して、市街化区域のキャパシティをオーバーしてしまった場合等に適用される制度です。
増えすぎた人口に対する受け皿として、市街化調整区域の中に保留区画を設定。
将来的に(次回の線引き見直しで)市街化調整区域が解除され、市街化区域に編入できるよう保留しておきます。
保留制度には区域範囲を特定する「特定保留」と、受け入れる人口等の枠を示す「一般保留」があり、どちらを採用するかは都道府県の判断次第です。
【特定保留】この範囲に人口を受け入れますよ。
【一般保留】何人分(人口等)まで受け入れますよ。
少子化の昨今なかなかないとは思いますが、もしあなたの不動産が保留区画に設定されたら、市街化区域になる又とないチャンスと言えるでしょう。
※参考:線引き見直しで決定(変更)する都市計画について-神奈川県ホームページ
3.神奈川県で行われたケース(第7回線引き見直し)
線引きやその見直しについては都道府県が行うものです。
今回は神奈川県(政令指定都市3市を除く)のケースを例にみていきましょう。
【注意】政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)は行政的に神奈川県から半ば独立しているため、線引き見直しはまったく別系統で実施されます。
ここではそれ以外の自治体で行われた線引き見直しを紹介しています。
最新で行われたのは2016年(平成28年)に実施された第7回見直しですね。
3-1.線引き見直しスケジュール
線引き見直しでは、以下のようなスケジュールが組まれます。
(1)都市計画素案の閲覧…線引き見直しの素案をみんなに見てもらう
(2)都市計画の公聴会……素案について、みんなから意見をもらう
(3)都市計画案の縦覧……意見を踏まえた案をみんなに見てもらう
(4)都市計画審議会………固まってきた都市計画案を審議する
(5)都市計画変更の告示…決定内容をみんなにお知らせする
線引き見直し(都市計画)の素案が閲覧に供されてから変更の告示がされるまで、どのくらいの期間がかかるのか見ていきましょう。
※参考:第7回線引き見直しに係る都市計画変更手続について‐神奈川県ホームページ
3-1-1.都市計画素案の閲覧
政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)を除く29市町の26都市計画区域について取りまとめた第7回線引き見直し素案を、2015年(平成27年)9月4日~25日まで、広く県民に閲覧させました。
3-1-2.都市計画の公聴会
閲覧した線引き見直し素案について、意見がある県民や利害関係者が意見を述べる(公述する)場として公聴会が開かれます。
2015年(平成27年)10月16日~11月26日まで、県内14市町において公聴会が開かれました。
※意見を述べたい方(公述人)がいなかった場合、公聴会は中止となります。
3-1-3.都市計画案の縦覧
公聴会で聴き取った意見(公述)を元に、素案を練り直して案とします。
これを再び県民に広く縦覧させました。
期間は2016年(平成28年)5月13~27日まで。
これについても意見が求められたと言います。
ところでさっきは閲覧という表現でしたが、今度は縦覧(じゅうらん)。
何か違いがあるのかと調べてみたら、こんな違いがあるそうです。
➤ 閲覧:書物や書類などを調べたり読んだりすること。
➤ 縦覧:自由に見ること。思うままに閲覧すること。
※『大辞林 第三版』より
ほとんど同じながら、何となく閲覧の方が積極的にアプローチしているニュアンスが強く感じられます。
縦覧は流し読みや軽いチェック程度でしょうか。
「前にしっかり閲覧してもらったから、概略はつかんでいるはず。
今度は出てきた意見を踏まえて、変更した部分だけ縦覧すればいいんじゃない?」と言った使い分けを感じます。
また自治体によっては、閲覧は「請求して見せてもらう」、縦覧は「開示してあるものを自由に見る」といったニュアンスで使い分けもしているようです。
3-1-4.都市計画審議会
こうして意見もあらかた出そろったところで、線引き見直し案(都市計画案)を都市計画審議会にかけます。
「都市計画審議会」は都市計画法第77条にもとづいて1969年(昭和44年)6月14日に設置されたものです。
県央・県西地域の16市町にある14都市計画区域については第229回都市計画審議会(2016年8月30日)で審議されました。
また三浦半島地域と湘南地域の13市町にある12都市計画区域については、第230回都市計画審議会(2016年9月6日)の審議を経て、最終決定となりました。
3-1-5.都市計画変更の告示
こうしてすべての手続きを終えると、神奈川県内の政令指定都市を除く29市町26都市計画区域の線引き見直しが完了。
2016年(平成28年)11月1日に、都市計画の変更が告示されたのでした。
ちなみに神奈川県内の自治体数は全部で33。
政令指定都市が3つと16市13町1村があります。
県内唯一の清川村については、その全域が都市計画区域の外。
つまり線引きが存在しない(※)ため、線引きの見直しも関係ないというわけです。
(※)都市計画区域外のほか、準都市計画区域についても区域区分を定めることができません。
3-1-6.線引き見直しにかかる期間は約1年強
【2015・平成27年】
- 9月4日~25日 都市計画素案の閲覧
- 10月16日~11月26日 都市計画の公聴会
【2016・平成28年】
- 5月13~27日 都市計画案の縦覧
- 8月30日 第229回都市計画審議会
- 9月6日 第230回都市計画審議会
- 11月1日 都市計画変更の告示
以上、神奈川県を例に線引き見直しのスケジュールを見てきました。
素案の閲覧から都市計画変更の告示まで、1年以上の月日を要するのですね。
みんなの慎重に意見を取り入れていく都合上、止むをえないところでしょう。
とは言え日ごろから意識していないと、気づいたら手続きが終わってしまいます。
もし市街化調整区域の不動産を持っているなら、こうした情報にアンテナを張っておくのがおすすめです。
3-2.線引き見直し周期と今後の見通し
神奈川県のホームページによると、次の第8回線引き見直しは2025年(令和7年)を目標年次に予定しています。
そしてこれまでの線引き見直しがどのくらいの周期で行われてきたのか、データをまとめてみました。
- 最初の線引き:1970年(昭和45年)
- 第1回線引き見直し:1979年(昭和54年)……9年後
- 第2回線引き見直し:1984年(昭和59年)……5年後
- 第3回線引き見直し:1992年(平成4年)……8年後
- 第4回線引き見直し:1997年(平成9年)……5年後
- 第5回線引き見直し:2003年(平成15年)……6年後
- 第6回線引き見直し:2010年(平成22年)……7年後
- 第7回線引き見直し:2016年(平成28年)……6年後
- 第8回線引き見直し:2025年(令和7年)……9年後(予定)
こうして見ると、第1回から第8回(予定)まで、5~9年の周期で線引きの見直しが行われてきた(いく)ことが分かります。
平均すると約6.9年、しばらく待っているたら(あるいは市街化調整区域の不動産を持て余している内に)線引き見直しのチャンスが巡ってきそうですね。
そしていよいよ線引き見直のタイミングにめぐり合えたら、好機を逃さないよう行動しましょう。
※参考:これまでの取組み状況・線引き見直しと「かながわ都市マスタープラン」の経緯
※参考:第8回線引き見直しに向けた取り組みについて(報告)
4.線引き見直しで、あなたにできることはある?
さて、ここまで線引きの見直しについて解説してきました。
線引きにせよ見直しにせよ、すべては行政当局の都合次第であることが分かります。
「何か自分にできることはないの?」
残念ながら、個人レベルで行政の線引き見直しにアプローチできることはほとんどありません。
が、まったくないという訳でもありません。
一言で表すなら「声を上げること」これにつきます。
4-1.都市計画の公聴会で公述人として参加する
都市計画素案が出されたら、しっかりと閲覧して公聴会に参加。公述人として意見を述べましょう。
公述人なんて聞くとなんだか緊張してしまいますが、これは「意見を言いたい人」くらいの感覚でOKです。
神奈川県の例では、都市計画決定により多くの住民参加を求める観点から、公聴会が開催されています(都市計画法第16条、神奈川県都市計画公聴会規則による)。
その時に公述人も募集されるので、この機をのがさず応募して、しっかりと忌憚のない意見を述べましょう。
4-1-1.公述人の資格
公述人には、作成しようとする都市計画案に関係する対象区域内の住民、または利害関係者がなれます。
その場所に住んでいるか、不動産を持っているなど何かしらの利害がからんでいる方ですね。
4-1-2.公述の申し込み
公述の申し込みは各市町の都市計画を管轄している部署へ、必要事項を記入した公述申出書を提出してください。
※参考:第1号様式 公述申出書
4-1-3.公述人の選定など
公述希望者が多い場合は抽選となり、10名程度が選ばれます。
よほど注目を集めている案件でなければ、そんなに集まることは少ないですが……。
また、公述人1名あたりの公述時間は約15分間(公述人数によって短縮される事もあり)なので、意見はなるべく簡潔にまとめておきましょう。
4-1-4.公聴会の傍聴
公聴会は傍聴することもできます。予約は不要ですが、当日満席の場合は断られてしまう可能性もあります。
なるべく多く支持者を動員して、行政に暗黙のプレッシャーをかける手も使えそうですね(そこまでつき合ってくれる仲間がいる場合)。
ちなみに手話通訳サービスもあるので、ご希望の方は申し込み期間中に神奈川県の都市計画課へ事前予約してください。
4-1-5.意見の公述は公益性を強調する
基本的に、公聴会では都市計画に関するなら自由に発言できます。
ただし「自分の所有不動産がある市街化調整区域を市街化区域に変更してほしい」などの私欲ありきでは、行政当局もその意見を取り上げようとは思わないでしょう。
自分の不動産がある市街化調整区域を市街化区域に編入すべき理由と、公的なメリットを訴えなければ、文字通り単なるガス抜き(鬱憤晴らし)に終わってしまいます。
公述された意見はあくまで参考に過ぎないものの、参考に値する「住民・利害関係者の声」に高めてこそ、公述する甲斐があろうというものです。
4-2.縦覧した都市計画案について意見を出す
公聴会で意見を公述したら、今度は公述された意見を採り入れ、都市計画素案から案に練り上げられたものが縦覧に提供されます。
「さてさて、私の意見はどのくらい反映されたかな?」
自分の不動産に関係がある部分をしっかりとチェックして、なおも意見がある場合はその意見を出しましょう。
「公聴会であれだけ言ったのだから、もういいや」と思ってしまうかも知れませんが、たとえ同じ主張であっても、通っていないなら繰り返すべきです。
今度は書面なので、公聴会に比べると影響力は小さいものの、それでも形には残ります。
意見は簡潔にまとめた上で提出しましょう。線引き見直しに際して、個人レベルで出来ることはこれで全部です。
4-3.日ごろから行政に意見する
しかし、他にもまだ出来ることはあります。
これも結局「声を上げる」一環ですが、線引き見直しが行われる前から(何なら見直しに関係なく、ずっと)地道に訴え続けるのです。
なぜあの場所を市街化区域に変えるべきか。
それによってどんなメリットがあって、公共の利益を見込めるか。
そういうことを伝えていきましょう。
管轄する行政職員でも、地元の議員でも有力者でも構いません。
あくまで「公益のため」に訴えるのです。
一回あたりの時間や話す量は短くても、積み重ねによって相手が次の行動(口をきいてくれる等)に移してくれる可能性もあります。
決して焦ってはいけません。
そうして線引き見直しが近づいたら、素案の段階から採り入れてくる可能性もあるでしょう。
素案の段階で採り入れてもらえればしめたもの。
あえてそれに反対して波風を立てる物好きはまずいませんから、あなたの市街化調整区域はめでたく市街化区域に編入されるはずです。
時間も手間も膨大にかかりますが、もし線引き見直しが近いのであれば、タイミング次第ではスムーズに目的を達成できる可能性も見えてきます。
5.市街化調整区域の不動産でお悩みなら、URUHOMEへご相談を
以上、市街化調整区域が市街化区域に編入されるチャンス「線引き見直し」について徹底解説してきました。
しかし線引き見直しは短期間にそう何度もある訳でもないし、いざ見直しが行われたとしても、個人レベルで行政の意思決定に食い込むのは至難の業です。
ならば線引き見直しをあてにするより、市街化調整区域のままで活用・売却してしまう方がより現実的ではないでしょうか。
市街化調整区域の不動産でお困りごとがございましたら、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年の創業より神奈川・東京を中心に、市街化調整区域をはじめとする訳あり物件など、売却しにくい不動産の取引を数多くサポートしてまいりました。
数々の取引経験を通して蓄積してきた知識やノウハウが、今回あなたのお悩み解消に役立てられるかも知れません。
他社様より「市街化調整区域だから買取りできない」と言われてしまった物件でもお任せください。
査定は無料、最短ではご連絡から1時間で査定、2日で売却できたケースもございます。
市街化調整区域の不動産をなるべく早く現金化したい方は、お気軽にご相談くださいませ。