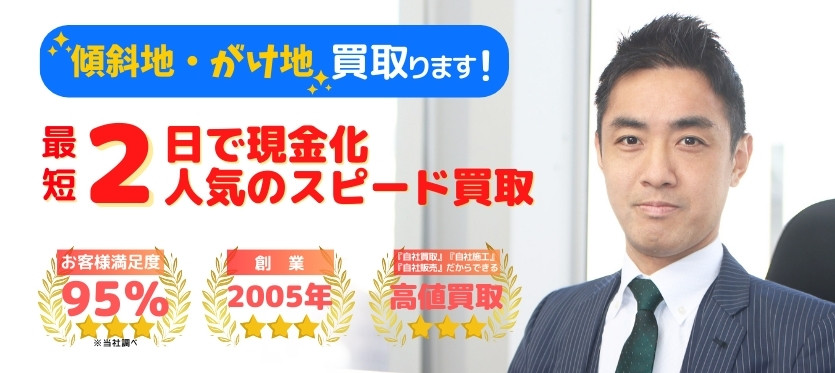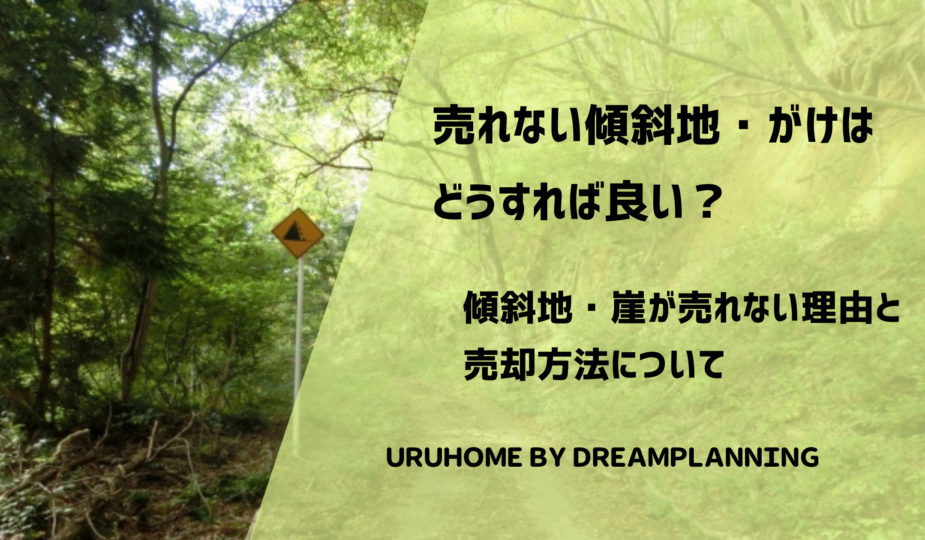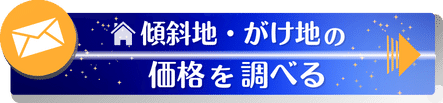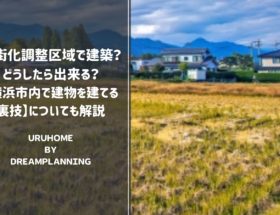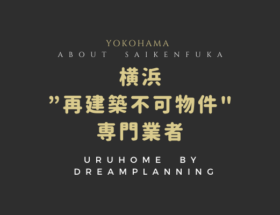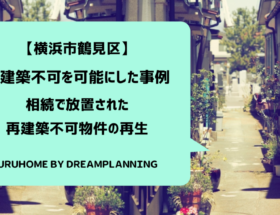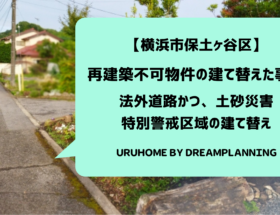「傾斜地や崖を相続した」「傾斜地・崖を売りたいけど売れなくて困っている」
こんな悩みを抱えていらっしゃる方も多いかと思います。
今回、傾斜地など、売却が難しい不動産を専門とする不動産会社社長が
「なぜ傾斜地やがけ地は売れないのか」「傾斜地、がけ地をどうやって売ればよいか」
について、詳しく解説してまいります。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より傾斜地・がけ地などの特殊な不動産を専門的に買取りしてまいりました。
当サイトURUHOMEは、私たちのノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
持て余している不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.傾斜地・がけ地とは
「傾斜地」とはそのままで傾斜している土地を指します。
「崖」とは、不動産関連の法律では、都市計画法施行規則第16条や、宅地造成等規制法施行令第1条で定義されていて、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものを指します。
自治体によって、崖は2m若しくは3mを超えるものと定義している事がほとんどです。

2.傾斜地・がけ地が売れない理由
傾斜地・がけ地はそのままでは宅地として利用できないため、売却が難しい不動産の一つです。
利用用途なども限られ、造成がかかる事も売却が難しい原因です。
他にも、傾斜地やがけ地が売却しにくい理由があるのですが、ここではその理由について詳しく解説いたします。
- 2-1.売れない理由①傾斜地・崖地は利用方法が限られる
- 2-2.売れない理由②傾斜地・崖地は住宅などが建てにくい
- 2-3.売れない理由③傾斜地・崖地は造成の難易度が高い
- 2-4.売れない理由④傾斜地・崖地は様々な法律により建築が制限されている
2-1.売れない理由①傾斜地・崖地は利用方法が限られる
傾斜地やがけ地は利用用途がかなり限られます。
なだらかな傾斜地であれば「太陽光発電用地」「農業用地」などで利用ができます。
また、土地が広ければ「キャンプ場」などとしても利用することも可能ですが、都市部で傾斜地やがけ地を持たれている方は、ほとんどが1000㎡以下の土地であるため、キャンプ場などの広い土地を要する用途として利用するのは困難です。
また、傾斜が急な崖地となると土地が広くてもほとんど利用が出来なくなります。
2-2.売れない理由②傾斜地・崖地は住宅などが建てにくい
傾斜地は造成をしないと住宅が建てにくいというのも売却が難しい理由の一つです。
造成をしないでも「鉄骨基礎工法」などを利用すれば建物が建てられますが、鉄骨も経年劣化があるので、長く住むことを考えると造成するのがベストです。
また、1990年代位までは、傾斜地マンションが流行していましたが、バブル崩壊以降は販売価格が下がる一方で、平坦地よりも工事費が高くなるこのようなマンションが新築されることは、ほとんど無くなってしまいました。
また、新型コロナウイルス、円安、ロシアのウクライナ侵攻などによって、資材高騰も続いており、国土交通省「建設工事費デフレーター」によると、2020年の建設資材物価指数を100として場合、2022年は126.3と上昇を続けており、マンションの建設費用や造成費が高騰していることもあり、今後よりいっそう傾斜地の売却は難しくなると考えられます。
2-3.売れない理由③傾斜地・崖地は造成の難易度が高い
傾斜地やがけ地でも鉄骨の基礎を組んで建物を建てることも可能ですが、住宅として長く利用するには、造成をしないと宅地として利用することは難しいです。
また、傾斜地やがけ地の造成工事は以下のような理由から簡単には出来ません。
- 土地家屋調査士による高低測量図が必要
- 設計士による擁壁の設計が必要
- 場合によっては構造計算事務所に構造計算を依頼必要がある
- 多額の宅地造成工事が必要
造成工事については、上記のように擁壁の設計に専門性が求められるという事と、造成費用が高く、費用負担が高いという意味でも難易度が高いと言えます。
2-4.売れない理由④傾斜地・崖地は様々な法律により建築が制限されている
傾斜地やがけ地を造成しても、他の様々な法令や条例で建築の際に制限を受けることがあります。
住宅を売買したことがある方であれば聞き覚えがあるかと思いますが、「宅地造成工事規制法」や、土砂災害防止法にかかる区域内で建築する際に、土地利用や建物建築で制約を受けることがあります。
このため費用的にも平坦地に建物を建てるより高くなる上、心理的な不安も大きくなるのも、売買が難しい要因の一つです。
次の項では、これらの傾斜地やがけ地にかかる法律についてご紹介してまいります。

3.傾斜地・がけ地にかかる法律
傾斜地、がけ地で無秩序な開発行為が行われると自然環境の破壊や、土砂災害などの二次被害も起こりかねないため、様々な法令や条例が関わります。ここでは、どんな法律や条例があり、建築の際にどのような制限があるかをご紹介してまいります。
- 3-1.傾斜地・がけ地の法律①宅地造成工事規制法
- 3-2.傾斜地・がけ地の法律②土砂災害防止法
- 3-3.傾斜地・がけ地の法律③森林法
- 3-4.傾斜地・がけ地の法律④急傾斜法
- 3-5.傾斜地・がけ地の法律⑤がけ条例
3-1.傾斜地・がけ地の法律①宅地造成工事規制法
「宅地造成等規制法」とは、宅地造成による崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するための規制を行う法律で1961年に施行されました。
災害の生ずるおそれのある市街地などとして行政が指定した宅地造成工事規制区域内で次のいずれかに当てはまる工事を行う場合には、市長の許可を受けなければなりません。
- 切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える『崖』ができるもの
- 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える『崖』ができるもの
- 切土と盛土を同時にする場合で、盛土の部分に高さが1メートル以下の『崖』が生じ、かつ、切土と盛土を行った部分に、高さが2メートルを超える『崖』ができるもの
- 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

また、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者には、崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があり、市長が災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
宅地造成工事規制区域内で造成工事をする場合、簡易的なコンクリートブロック積による土留めでは無く、間知ブロックや鉄筋コンクリートで擁壁を築造し、基準をクリアしなければ宅地造成工事の許可が出ません。
そのため、宅地造成工事規制法のかかる土地での擁壁工事は、そうではない所と比べて擁壁の設計、工事で2倍程度の金額差が出ることがあります。
3-2.傾斜地・がけ地の法律②土砂災害防止法
「土砂災害防止法」とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
がけ崩れや土石流などの土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)の指定を行っています。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、後述するように建物を建築する際に土砂災害に耐えうる建築物を建築しなければならないという構造規制が生じるため、設計費や建築費が割高になります。
尚、土砂災害警戒区域や特別警戒区域に指定されるのは、次のような災害が想定される区域です。
土石流
山腹が崩壊して生じた土石等または渓流の土石等が一体となって流下する自然現象です。
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域に指定されます。
地すべり
土地が地下水等に起因して滑る自然現象で、次のような区域が指定されます。
ア 地すべり区域
イ 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域
急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)
傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象で、次のような区域が指定されます。
ア 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
イ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ウ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

3-2-1.土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)に指定されるとどうなる?
土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域が指定されます。
尚、土砂災害警戒区域に指定されると以下のような義務が生じます。
- 宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと
- 要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施すること等が義務づけられます。
3-2-2.土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されるとどうなる?
土砂災害特別警戒区域は、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域が指定されます。
特別警戒区域に指定されると次のように建築の際の許可や、建築の際に一部若しくは全部を鉄筋コンクリート造などにしなければならないなどの構造規制、移転勧告がされることがあります。
下記のように、土砂災害警戒区域と違い、かなり厳しい制限がされることになります。
- 特定の開発行為に対する許可制
- 建築物の構造規制
- 建築物の移転勧告

3-3.傾斜地・がけ地の法律③森林法
「森林法」とは森林の保護・培養と森林生産力増進に関する基本的事項を規定する法律です。
森林法では、全国森林契約・地域森林計画などの森林計画制度、林地開発許可制度、保安林制度などが規定されています。
そして、樹木の伐採などに許可や届け出が必要です。
- 地域森林計画の対象森林を取得した場合に届け出が必要になります。
- 保安林の指定を受けている場合は開発が制限されます。
ア 立木の伐採制限
保安林内で立木を伐採する場合には、都道府県知事の許可または届け出が必要となり、指定された方法および限度に従って伐採をしなければなりません。
イ 土地形質の変更制限
保安林の適切な保全を図るため、保安林内において土地の整地や掘削などの形状変更、立木の損傷といった土地の形質変更などの行為をする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けることが必要になります。
ウ 伐採後の植栽義務
森林所有者などが保安林の立木を伐採した場合は、あらかじめ定められている植栽の方法、期間および樹種に従って植栽を実施しなければなりません。
3-4.傾斜地・がけ地の法律④急傾斜法
「急傾斜法」は急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、人々の生活の安定と国土の保全とに役立てることを目的としています。
正式名称は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」と言います。
台風や集中豪雨の際に発生する急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護することを目的として、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により危害が生ずるおそれのあるものに、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として都道府県知事が指定します。
急傾斜地崩壊危険区域では、がけ崩れを防止するための工事を実施するとともに、盛土や切土、立木の伐採、その他急傾斜地の崩壊を助長し、誘発するおそれのあるものなどに一定の行為が制限されます。

3-5.傾斜地・がけ地の法律⑤がけ条例
「がけ条例」とは通称で、崖上やがけ下で建築する際の構造などの制限が定められたもので、各自治体の建築基準条例で規定されています。
建築基準法第 19 条では、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定されており、この基準が、通称がけ条例と呼ばれていて自治体毎に定められているのです。
がけ条例では、がけの上部、崖下で土地利用をする際に、擁壁や防護壁の築造をしなければならない事などについても規定されていて、どういった場合に擁壁や防護壁が必要かなどについての基準は自治体によって全く違い、崖被害の大きい自治体ほど条例が厳しい傾向があります。
4.売れない傾斜地、がけ地をどうすればよいか?
売れない傾斜地やがけ地、どうすれば良いか悩ましいところです。
そこで、活用方法や売却方法について解説してまいります。
4-1.売れない傾斜地・がけ地を太陽光発電用地として利用する
傾斜地やがけ地の利用方法の一つは、太陽光発電の用地として賃貸することです。
基本的には300坪以上のまとまった土地で、道路に面している方が価値が高い土地となります。
傾斜が急ながけ地や、樹木を伐採できない保安林などは、太陽光発電用地として利用できないため、注意が必要です。
広くて、地盤が固く、近隣住民からの反対がない土地が向いているので、地方の余っている土地などは、太陽光発電の用地として利用しやすいと言えます。
ただし太陽光発電パネルに使用されている有害物質はいまだ処理法が確立されておらず、太陽光パネルの寿命が来る10~30年後に深刻な環境破壊や土壌汚染のリスクが指摘されていることはご留意ください。
また山林の乱開発によって保水力が失われ、近年多発している土砂災害や水害との関連性も指摘されています。合わせて、棲息環境を失った野生動物(クマ、シカ、イノシシ等)の被害増加も見過ごせません。
4-2.売れない傾斜地・がけ地をキャンプ場として利用する
多少の傾斜で、時間的な余裕があればキャンプ場経営などもお勧めです。
ただ、宿泊業や飲食店、酒類販売の営業許可など、許可が必要になることがあるので事前に確認しましょう。
4-3.売れない傾斜地・がけ地をURUHOMEで売却する
太陽光発電の用地として賃貸や、キャンプ場や農地として活用する以外は、売却するのも方法の一つです。
ニッチな不動産”URUHOME”でお馴染みドリームプランニングは、2005年創業で、傾斜地やがけ地などの売却が難しい不動産を専門として、積極的にお買取りしています。
最短30分で査定、お問い合わせから最短2日でお買取りさせていただいた事も多数ございます。
お困りの不動産がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。