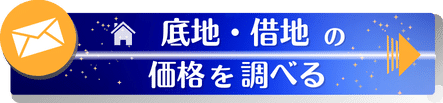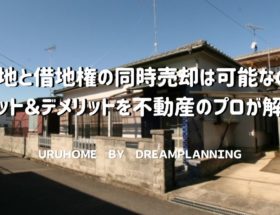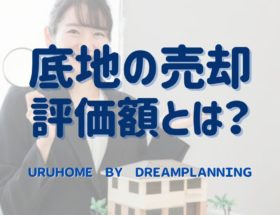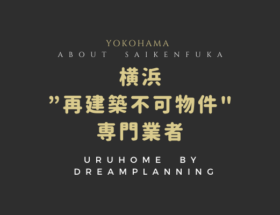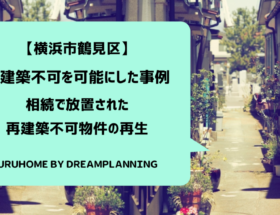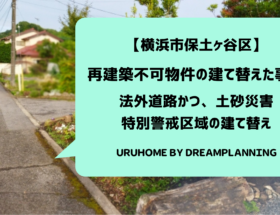借地権の土地を所有しているけど、旧法借地権、新法借地権って何?
これから購入する不動産は全て新法借地権が適応されるの?
適用範囲や民法との関係、契約期間など借地借家法の全てを底地買取会社の社長が分かりやすく解説いたします。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
1.借地借家法とは?
1-1.民法と借地借家法の関係
法律には、一般的な規定を設けた「一般法」と、その一般法が対象とする分野内で更に狭い範囲(一定の期間、一定の地域、一定の対象など)に適用される「特別法」があります。
一般法と特別法では、特別法が優先されます。
民法は一般法であり、借地借家法は、建物所有を目的とする借地契約と建物の賃貸を目的とする借家契約について適用される「特別法」です。
つまり、賃貸借契約については、原則的には民法の規定が適用されますが、借地借家法の対象となる借地契約や借家契約は借地借家法が優先して適用されます。
1-2. 借地借家法の適用を受ける土地
借地人や借家人を強く保護する借地借家法ですが、借地に関していえば「人に貸している土地」すべてに適用されるわけではありません。
借地借家法で適用を受ける土地とは「建物を建てて所有するため」に借りる契約を結んだ土地に限られるのです。
ただ、「貸している土地」といってもさまざまな種類のものがあり、駐車場や畑など、建物を所有する事が目的でなければ借地借家法ではなく、民法や農地法の適用を受けます。
判断のポイントは「土地を借りる目的が建物を所有する事かどうか」になります。
また、借地借家法の適用を受けるには、賃料が発生しているかも重要な要件の一つとなります。
無償で人に使わせている使用貸借の土地は、そこに家を建てていたとしても、借地借家法の適用外となります。
2.借地借家法はいつから出来た?
借地借家法は1991年公布、1992年8月1日に施行されました。
しかし7月31日以前に締結された借地契約については、基本的には借地借家法の前身となる旧借地法、旧借家法が適用されます。
借地借家法では、従前の借地法、借家法を統合したほかに、更新を認めない定期借地権等の規定が創設されました。
借地借家法では、借地権や借家の存続期間や効力について、借地人や借家人に不利にならないよう一定の制限が定められております。
2-1.借地借家法以前の旧借地法とは?
現行の借地借家法の前身となった法律で、大正10年成立、平成4年に廃止された法律です。
借地人を保護する目的で制定された借地法(大正10年法律第40号)、借家法(大正10年法律第40号)、建物保護法(明治42年法律第40号)の3法が統合され、借地借家法になりました。
2-2.旧借地法の特徴
旧借地法では、借地人の保護に重点が置かれ、地主さんから土地を借りると、借地人が希望する限り契約更新を続けることで半永久的に契約を継続することが可能です。
大正10年の借地法制定当時は、契約満了後の更新拒絶も可能でしたが、昭和16年の借地法改正により正当な事由がなければ更新拒絶が出来ないようになり、借地人の権利がより強固になりました。
時代背景としては、戦前の土地の価格は安く、土地を所有するという概念も希薄で、東京都市部では90%が借地、借家住まいだったことがあり、その後の太平洋戦争の開戦により、多くの男性が家を離れる事があったので、留守中に借地契約の満了などによって家族が追い出されることが無いようにするという配慮があったためです。
2-3.旧借地法と借地借家法の違い
借地借家法が新たに設けられたのは、住宅不足を緩和することや、借地権者の保護が強すぎるために新たな借地権設定を地主がしないため、不動産の流通を阻害していたことなどが挙げられます。
そこで、旧借地法が借地人保護だったのに比べ、借地借家法では地主と借地人が平等に扱われるようになりました。
しかし、借地借家法が施行された平成4年8月1日より前に設定されていた借地権については、現在も旧借地法が実質的に適用されます。
主に違うのは借地の契約期間や、更新後の建物滅失は、借地借家法では借地を解約できるようになった事(旧法では解約出来ません)など、借地人保護寄りだった旧借地法から、対等な契約関係を結べるようになりました。
借地法の場合、契約の存続期間が建物の構造によって違い、木造などの非堅固建物は20年以上、マンションなどの堅固建物期間は30年以上と定められましたが、堅固な建物の例はマンションやビルなど鉄筋コンクリート造の建物や、ブロック、レンガ、石、コンクリート造りの建物などであり、それ以外は堅固でないものと分類されています。
また、判例では軽量鉄骨は非堅固(東京高裁昭和59年12月27日)、重量鉄骨は堅固に該当する事が多いようです。
| 旧借地法 (旧借地権) | 借地借家法 (普通借地権) | |
| 定めが無かった場合の存続期間 | 堅固な建物:60年 非堅固な建物:30年 | 一律30年 |
| 更新後の存続期間 | 堅固な建物:30年 非堅固な建物:20年 | 20年 (2回目の更新以降10年) |
| 建物の朽廃による借地権の消滅 | 消滅する | 消滅しない |
| 建物の再築による期間の延長 | 堅固な建物:30年延長 非堅固な建物:20年延長 | 一律20年延長 |
| 更新後の建物滅失による解約 | 不可 | 可 |
3.借地借家法の特徴とは?
ここまでは旧借地法と借地借家法の違いについて触れてまいりましたが、借地借家法の詳細についてご紹介いたします。
3-1.借地借家法の期間
借地権の存続期間は30年となりますが、30年以上で長い期間で当事者間で合意した場合はその期間となります。
また、借地契約が更新された場合にはさらに10年以上(最初の更新時は20年以上)、借地権を存続させなければならないと定められています。
このように、借地権については、存続期間を長くすることで借地人の生活基盤を安定させることを図っています。
反面、土地所有者にとっては負担が大きいことから、借地権が長期間にわたり継続することを前提に借地契約を締結する必要があります。
3-2.借家借家法の適法範囲
借地借家法には適用範囲があり、”建物所有を目的とする賃貸借契約”『借地の契約』と”建物賃貸借を目的と賃貸借契約”『借家の契約』が適用範囲になります。
また、全ての建物に適用されないのが特徴で、以下に関しては借地借家法は原則として適用されません。
- 建物の所有を目的としないもの
- 一時使用目的のもの
- 無償で貸しているもの
また、居住用・事業用といった用途を問わず建物所有目的の借地や借家を目的としたものであれば借地借家法が適用されます。
ただ、立体駐車場については「建物」にあたらないとして、借家法の適用を否定した判例もあるなど、解釈が難しいこともあります。
なぜ適用範囲が大事かというと、借地借家法は民法の賃貸借よりも優先され、借主が保護されるからです。
そのため、借地借家法が適用されるかどうかが争われることも少なくありません。

4.普通借地権・定期借地権とは何か?
1992(平成4)年8月1日に借地借家法が施行され、借地権を普通借地権と定期借地権に区分しました。
普通借地権は、旧法借地の借地契約が改正されたもので、借地権の存続期間が満了しても、地主側に正当事由がなければ、借地人が更新を望む限り借地契約が更新されるものです。
一方定期借地権は、新たに創設された制度で、借地権の期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。
| 借地権 | 存続期間 | 契約方法 | 借地関係の終了 | 契約終了時の建物 |
| 一般定期借地権(法22条) | 50年以上 | 公正証書等の書面で行う。 [1]契約の更新をしない [2]存続期間の延長をしない [3]建物の買取請求をしない という3つの特約を定める。 | 期間満了による | 借地人は建物を取り壊して土地を返還する |
| 事業用定期借地権(法23条) | 10年以上50年未満 | 公正証書による設定契約をする。 [1]契約の更新をしない [2]存続期間の延長をしない [3]建物の買取請求をしない という3つの特約を定める。 | 期間満了による | 借地人は建物を取り壊して土地を返還する |
| 建物譲渡特約付借地権(法24条) | 30年以上 | 30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。 口頭でも可 | 建物譲渡による | [1]建物は地主が買取る [2]建物は収去せず土地を返還する [3]借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる |
| 普通借地権 | 30年以上 | 制約なし 口頭でも可 | [1]法定更新される。 [2]更新を拒否するに は正当事由が必要。 | [1]建物買取請求権がある。 [2]買取請求権が行使されれば建物はそのままで土地を明け渡す。借家関係は継続される。 |
4-1.普通借地権とは?
普通借地権とは、平成4年8月1日に施行された借地借家法で改正された借地の形態の一つで、旧借地法の内容を引き継いだものです。
契約更新がない「定期借地権」とは違い、契約期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されます。
借地権の存続期間を当初30年とし、更新すると第1回目のみ20年、以後10年となっております。
契約満了後に、(地主が更新を許可しない場合は)建物の買取を請求することができるのも、普通借地権の特徴です。
4-2.定期借地権とは?
旧借地法には、所有している土地でも一度貸すと返ってこないという問題がありました。
戦後地価が高騰し、住宅取得コストが上昇する一方、都市部では住宅用地が不足していたため、この「一度貸したら返ってこない旧借地法」を見直す必要があったのです。
こうして、社会実態に適用した形に借地法・借家法を見直した結果、平成4年8月1日に借地借家法が施行され、定期借地権が創設されるに至ったのです。
定期借地権の創設により、貸した土地が必ず戻ってくることや、期間満了により立退料の給付の必要もなくなったため、地主が安心して土地を貸し出せるようになりました。
また、定期借地権では、次の3つの特約を認めました。
- 契約の更新がないこと―契約の更新が一切なく、確実に契約関係が終了する
- 建替による借地期間の延長がないこと―契約期間中に建替えがあっても当初定めた契約期間が満了すれば土地が返ってくること
- 建物買取請求権がない―旧借地法では、地主が更新を拒絶した場合、借地人が建物を買い取るように地主に請求出来ましたが、定期借地権では建物買取請求が出来ないこととする特約をつけることが認められました。
5.借地借家法の改正とは?
2022年5月の改正によってオンライン化が可能になった本法上の契約は、「定期借地権契約」「定期建物賃貸借契約」の2つです。
今回の改正で借地借家法22条2項が設けられ、定期借地権とする内容の「特約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなす」とされ、オンラインでの契約締結も有効とされるようになりました。
また、借地借家法38条2項に「前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する」との条文が追加され、電子契約を締結できるようになりました。
6.借地・底地でお困りならURUHOME
借地借家法が難しい事が分かってきましたが、底地・借地の事でお困りではありませんか?
当サイトURUHOMEを運営する株式会社ドリームプランニングでは、皆様の底地や借地を買い取りさせて頂いております。
借地借家法が適用されるか分からない使用貸借の底地や、定期借地権の底地、トラブルがある底地など、様々な底地の買取実績があります。
査定から最短2日で現金化させて頂いた実績もあり、特に横浜・川崎・都内城南地区をメインに全国で不動産の買取をさせて頂いております。
お困りの底地・借地などがございましたら、当社で買い取らせて頂きますのでお気軽にご相談くださいませ。