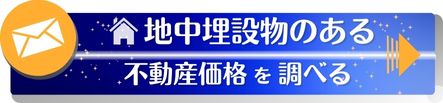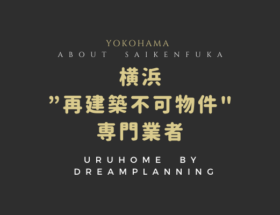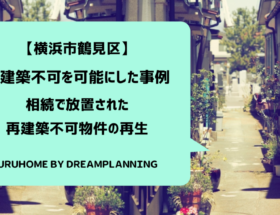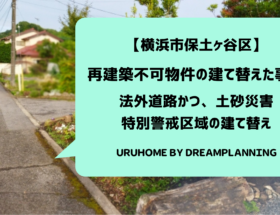「地中埋設物がある不動産は売却できるの?」
ドリームプランニングでは、日々そんなお悩み相談をいただきます。
地中埋設物を放置した場合は法的責任を問われるの?
地中埋設物を撤去する場合にかかる費用は?
……などなど、悩みはつきることがありません。
そこで今回は、ドリームプランニングの社長が地中埋設物の売却ノウハウを徹底解説!
皆さんのお悩み解決に役立ててください!
【この記事は、こんな方におすすめです】
- 地中埋設物がある不動産を売却したい方
- 地中埋設物のリスクについて知りたい方
- 地中埋設物について悩みを抱えている方
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より地中埋設物のある不動産の買取専門業者として日本全国で訳アリ物件を買取してまいりました。
大変ありがたいことに神奈川・東京をはじめ日本全国から不動産のご相談を頂いており、5,000万円位までの不動産であれば最短2日で買取りさせていただくことも可能です。
地中埋設物のある不動産のご売却で困っている不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 地中埋設物とは何か
- 地中埋設物を放置するリスク
- 地中埋設物の法的責任・よくある質問
- 地中埋設物の法的責任(売主)
- 地中埋設物の法的責任(不動産会社)
- 地中埋設物のトラブルを回避する方法
- 地中埋設物のある不動産でお悩みならURUHOMEへご相談を
1.地中埋設物とは何か
地中埋設物とは、読んで字のごとく「地」面の「中」に「埋設」した「物」のことです。
埋設(埋めて設置する意味)という言葉から人間が積極的に埋めたものをイメージしがちですが、放置していて自然に埋もれたものなども含まれることがあります。
要は「地面から出てきた不都合なもの、かつ簡単には片づけられないもの」程度に理解しておけばいいでしょう。
1-1.人工物
ここでは、地中埋設物としてよく出てくるものを紹介していきます。
他にも色んなパターンがあると思いますが、すべては網羅しきれないため似たようなものに当てはめて考えてください。
1-1-1.使わなくなった浄化槽
地中埋設物でよくあるのが、下水道が整備されたことによって使わなくなった浄化槽。
撤去には数万円から十数万円の費用がかかるため、面倒だからそのまま埋めておくケースがあるのです。
1-1-2.建築・解体廃材
建物を建てる時や解体した時に発生する廃材(コンクリート片、木材片など)を、敷地内に埋めてしまう悪質な業者も残念ながらいます。
業者に連絡できるならただちに回収させ、応じなければ消費者庁の消費者ホットライン(電話番号188)へ通報しましょう。
1-1-3.古い水道管・ガス管など
建物敷地内に設置されている水道管やガス管は地権者の所有物です。そのため、使用を中止した後も放置しているケースがあります。
1-1-4.古い井戸
使わなくなった井戸は、お祓いをしてから埋め戻すことが多いです。
その時、地中に埋設したままの土管などが出てくるケースもあります。
あるいはまだ埋め戻されていない古井戸が、草木を伐採したら姿を見せたパターンもありました。
こういう「思わず出てきたもの」についても、おおむね地中埋設物と同じように取り扱います。
1-1-5.家庭ゴミや産業廃棄物など
これは埋設というより不法投棄ですが「自分の土地だからいいだろう」と家庭ゴミを埋めたり、事業を営んでいる方が産業廃棄物を埋めてしまったりといったケースも後を絶ちません。
後ほど紹介する通り、たとえ自分の土地であっても、みだりにゴミを捨てると法律で罰せられます。絶対にやめましょう。
1-1-6.遺跡や埋蔵文化財など
日本には遺跡が埋まっているとされている埋蔵文化財包蔵地が約40万ヶ所も指定されているそうです。遺跡も大昔の人々による地中埋設物と言えるでしょうか。
一度遺跡が出土してしまうと、発掘調査に約2ヶ月以上もかかるばかりか、調査費用も負担させられます(自治体によっては補助金あり)。
特にその可能性が高い埋蔵文化財包蔵地でなくても、遺跡が発掘されたケースは少なくないため、注意が必要です。
1-2.自然物(岩石・湧水など)はどうなるの?
地中埋設物というからには、人の手が入っている人工物がほとんどです。
しかし中には巨大な岩や湧水など、不動産取引の目的をさまたげるものについては自然物であっても地中埋設物と同様の契約不適合責任を追及される可能性があります。
例1)地面を掘削したら、地中に岩盤があって工法の変更が必要になった。
例2)地面を掘削したら水が湧き出し、地盤補強工事が必要になった。
……などなど。
契約不適合責任を問われる判断基準は、現場の地形や売主の予測可能性など、ケースバイケース。自然物だからと必ず免責されるわけではないので、注意しておきましょう。
2.地中埋設物を放置するリスク
土地所有者にとって、頭が痛くなる地中埋設物。撤去するにも費用がかかりますし、出来れば放っておいて、そのまま土地を売却したい気持ちは解ります。
しかし、地中埋設物を放置すると大きなリスクを抱え込むことになるのです。
「あの時、地中埋設物を撤去しておいた方がまだよかった……」
そんなことにならないよう、まずは地中埋設物を放置するリスクを把握しておきましょう。
2-1.法的責任を追及されるリスク
後ほど詳しく解説しますが、地中埋設物を放置した不動産を売却することで、買主から法的責任を追及されるリスクがあります。
「地中埋設物を撤去してください」⇒履行の追完請求(民法第562条)
「代金を減額=埋設物を除去した差額を返金してください」⇒代金減額請求(民法第563条)
「損害を賠償してください」⇒損害賠償請求(民法第564条など)
「売買契約を取り消します」⇒売買契約の解除(民法第564条など)
他にも買主からではありませんが、不法投棄(廃棄物処理法第16条違反)で処罰されるリスクも見逃せません。
2-2.建物の建築に支障が出るリスク
地中埋設物の性質や形状にもよるものの、地中埋設物が放置されたままでは建築工事が上手く進まないケースも少なからずあります。
地中は目に見えないぶんイメージしにくいと思いますが、暮らしを支えるインフラ関係(水道管・ガス管など)は多くが地中に埋設されているのです。
地中埋設物が発見されると、そのたびに工事を中断し、工期もコスト(人件費、撤去費用など)もかさんでいきます。
不動産を売却する時は、そのリスクを織り込まなければならないので、売却価格≒資産価値は市場の相場より大きく下がってしまうでしょう。
2-3.地盤が軟弱になるリスク
地中埋設物は一般的な土砂と違って密度が低いです。
たとえ外見はキレイに取り繕えたとしても、その中身がスカスカであれば当然地盤は緩くなってしまいます。
軟弱な地盤の上に建てた建物が地震に強いはずもなく、災害などが発生した場合、大きな被害を出してしまうリスクは否めません。
2-4.土壌汚染による健康被害のリスク
これは地中埋設物の性質にもよりますが、例えば有害な薬品や医療廃棄物などが埋められていた場合、土壌が汚染されている可能性があります。
よくあるのが元々ガソリンスタンドだった土地が、石油などで汚染されていると言ったケースですね。
地中埋設物の性質等によって一概には言えないし、直ちに影響はないかも知れません。
しかし一度購入した土地を数十年単位で利用することを考えると、中長期的な健康被害は軽視できないでしょう。

3.地中埋設物の法的責任・よくある質問
さて、地中埋設物についての法的責任は、原則的として売主にあります。
それでは、売主が負うべき地中埋設物の法的責任とは、地上からどこまでの範囲(深さ)を指すのでしょうか。
他にも「地中埋設物の時効は引き渡しから何年?」「地中埋設物の所有権は誰が持つの?」などなど、よくいただく質問をまとめました。ご参考にどうぞ。
- 3-1.地中埋設物の法的責任を負う深さはどこまで?
- 3-2.発見された地中埋設物はいつまでに契約不適合責任を追及する?
- 3-3.発見された地中埋設物の時効は?(引き渡しから何年?)
- 3-4.発見された地中埋設物の所有権は?(買主が貰ってもいい?)
3-1.地中埋設物の法的責任を負う深さはどこまで?
【回答】一般的には地下2m程度まで、特別な事情があればその深さを取り決めします。
地中埋設物とは読んで字のごとく「地中に埋設されている物」です。だから土地に埋まっていたものなら、何でも地中埋設物と言えなくはありません。
しかし法的責任を負う地中とは、どこまでの深さを指すのでしょうか。
極端な話「地球の中心まで掘り進めたらマグマが噴き出したぞ!どうしてくれる!」なんて事も……さすがにないとは思いますが。
そんなの常識で分かるでしょ?と言いたくなるものの、その「常識」が人によって違うから、世の中トラブルが絶えないのです。
調べてみたところ、地中埋設物の深さについて、法律などで規定されているわけではありませんでした。
というわけで各社の施工事例などのデータを独自にまとめたところ、概ね一般住宅の建築を前提として、約1~2mまでというのがいわゆる「常識」となっているようです。
ただし「以前、地下3mの深さまでモノを埋めたことがある」「埋め戻した古井戸の土管が地下4~5mに達しているはず」など、より深い場所まで埋まっているケースがあります。
そういう時は売買契約前の重要事項説明で買主にしっかり告知して、どうするかを取り決めておくといいでしょう。
こうした事から、例えば「地下2mくらいまでは責任を負い、そこから先は免責」など、事前に取り決めておくのが一般的です。
3-2.発見された地中埋設物はいつまでに契約不適合責任を追及する?
【回答】売主が宅建業者なら引き渡しから2年以内とするケースが多い、など
民法では、売買した不動産に地中埋設物が見つかり、売主に対して契約不適合責任を追及するには、対象物が契約の内容に適合しないとわかってから(地中埋設物が発見されてから)、1年以内に売主に通知しなければなりません。
ですが、契約不適合に関しての請求そのものを1年以内に行う必要は基本的になく、地中埋設物が発見された場合、買主はそれを知った時から1年以内に通知しておけば、1年が過ぎても修補請求や損害賠償請求などができます。
ただ、売主が宅建業者の場合は宅建業法より、「引き渡しより2年以内」とすることが多く、一般の方が売主の場合は、「引き渡しから3カ月」と任意規定で契約不適合責任の期間を短くするケースも多くあります。
民法とは異なる任意規定を定めるのは、売主の責任が重くなりすぎるためであり、任意規定で定めた内容の契約も有効になります。
3-3.発見された地中埋設物の時効は?(引き渡しから何年?)
【回答】契約不適合を知った時から5年以内、もしくは引き渡しから10年以内
「それでは時効は1年もしくは、任意で決めた期間?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は違います。
契約不適合は知った時(地中埋設物を発見した時)から5年以内(若しくは引き渡しから10年以内)に契約不適合責任に対して権利を行使すれば良い事になっております。
つまり、1年以内(若しくは任意で定めた期間)に地中埋設物を発見して相手方に通知し、地中埋設物を発見した時から5年以内、(若しくは引き渡しから10年以内)に損害賠償請求などをしないと時効となり、契約不適合責任を追及する権利を失うのです。
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(以下略)
また、損害賠償の請求は地中埋設物や土壌汚染を発見してから1年以内に行わなければなりません。
3-4.発見された地中埋設物の所有権は?(買主が貰ってもいい?)
地中埋設物と聞くと、不動産業界の方なら「うへえ……面倒だなあ……」と思わず眉間にシワが寄ってしまうかも知れません。
しかし地中に埋まっているのは必ずしも厄介なモノばかりとも限りません。例えば徳川埋蔵金など、嬉しいものが発見された場合の所有権はどうなるのでしょうか。
地中埋設物の法的責任が売主にあるなら、売主の権利になるのでしょうか。それとも買主の土地にあるのだから、買主の権利になるのでしょうか。
ここでは発見した地中埋設物が価値あるものだった場合で考えていきます。
3-4-1.所有者が不明の場合(民法第241条)
【回答】落とし物のように取り扱い、6ヶ月間持ち主が現れなければ自分のものに
民法第241条によると、地中埋設物の所有者が分からないときは「こんなモノが見つかったが、心当たりはないか」と公告を行う必要があります。そして6ヶ月間が経っても持ち主が現れなかった場合、地中埋設物は自分のものとなるのです。
手続きの流れは落とし物の場合(民法第240条)と同じですが、落とし物の場合は期間が3ヶ月間と短くなります。
民法
(埋蔵物の発見)
第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
他人の土地で発見したならその人と折半、自分の土地なら100%自分のモノにできますね。
3-4-2.所有者が判明した場合(遺失物法第28条1項)
【回答】返還しなければならないが、時価5~20%の報労金を請求できる
地中埋設物の公告をしたところ、持ち主(大抵の場合は売主)から「それは私が埋めたものだ。売った覚えはないから返してもらおう」などと言われた場合、買主はすべて返還しなければならないのでしょうか。
そういう時は、残念ながら持ち主に返さなければなりません。
しかし遺失物法第28条1項の規定に従って、発見した報労金を請求することができます。金額は発見したものの時価5~20%ですね。
遺失物法
(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 以下略
ただ、モノによりますが発見した地中埋設物の時価がいくらなのか、それを請求して人間関係が大丈夫か?は気になるところです。
筆者個人的には、後々のトラブルを考えると、見つけ次第進んで売主に返還してあげるのが一番気持ちいいと思います。
4.地中埋設物の法的責任(売主)
さて、地中埋設物を放置した場合の法的責任が売主にあることは解説してきました。
それでは具体的に、どんな法的責任を問われるのかを見ていきましょう。
- 4-1.履行の追完請求(民法第562条)
- 4-2.代金減額請求(民法第563条)
- 4-3.損害賠償請求(民法第564条、第415~417条)
- 4-4.売買契約の解除(民法第564条、民法第541~542条)
- 4-5.その他の法的責任(廃棄物処理法第16条など)
4-1.履行の追完請求(民法第562条)
購入した土地に地中埋設物があることを知らずに(ないという前提で)土地を取引して、地中埋設物があるために取引目的が達成できない場合、買主は売主に対して地中埋設物の撤去などを要求できます。
民法
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
【今回の取引ケースに合わせた意訳】
(1)購入した土地の品質(地中埋設物のない状態)が契約に適合しなかった(つまり予期せぬ地中埋設物があった)場合、買主は売主に対して(一)地中埋設物の撤去(二)代わりの土地を提供(三)不足した土地の提供、のどれかによる埋め合わせを要求できます。
(2)ただし、売主は必ずしも買主が要求した通りの方法でなくても大丈夫です。
よくあるのが「掘り返したら、事前に確認していない浄化槽が出てきた。撤去しないと家が建てられないから、撤去費用を負担しなさい」などといったケース。
代わりの土地を……とか、不足分の土地を……と言った要求はまず聞きません。
地中埋設物を撤去すれば事足りるならまだマシな方で、例えば土壌汚染の場合などは心理的なものもあるため、問題が複雑化するリスクも考えられます。
4-2.代金減額請求(民法第563条)
地中埋設物が発見され、撤去を求めたにもかかわらず期間内に撤去されなかった場合、買主は土地の代金減額を請求できます。
民法
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
【今回の取引ケースに合わせた意訳】
(1)買主が十分な期間を決めて地中埋設物の撤去を求めたのに、期間内に撤去してもらえなかった場合は土地代金の減額を請求できます。
(2)以下のケースでは前置き(撤去の要求)なしですぐに代金減額を請求できます。
(2-1)地中埋設物の撤去が不可能なケース
(2-2)売主が地中埋設物の撤去を拒絶したケース
(2-3)一定の期間より早く、地中埋設物を撤去しないと契約目的を果たせないケース
(2-4)その他、地中埋設物の撤去を要求してもムダだと明らかなケース
(3)仮に地中埋設物の問題が明らかに買主の責任であった場合は、売主に対して代金減額を請求できません。
ちなみに「一定の期間」とは何日間なのか、法律上は具体的に決められていません。一般に取引上必要とされる期間と解釈され、通例では1週間前後とみられるようです。
そして土地代金をどのくらい減額するのか、については地中埋設物の存在による不都合度合いによって変わります。
例えば「地中埋設物によって土地の30%がちゃんと使えない状態だから、1週間以内に撤去するか、土地代金の30%を減額して下さい」などのように、ある程度の根拠をもって要求してくるでしょう。
4-3.損害賠償請求(民法第564条、第415~417条)
地中埋設物の存在によって損害が生じてしまった場合、買主は売主に対して損害賠償を請求してくるケースが考えられます。
損害賠償請求について規定している民法第564条を確認しましょう。
民法
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
【今回のケースに合わせた意訳】
要するに買主は「見つかった地中埋設物について、その撤去や代金減額を要求する権利があります。それらと合わせて損害賠償請求や、契約を解除する権利もあります」という話です。
(個人的感想ですが、どうして法律の条文って、こういう回りくどい書き方をするんでしょうね)
損害賠償については、民法第415~417条に規定されています。
民法 第415~417条【クリックで全文表示】
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
【今回のケースに合わせた意訳】
第415条 売主が地中埋設物の撤去をしない時orできない時、買主は地中埋設物の存在によって生じた損害の賠償を売主に請求できます。ただしそれが売主の責任と言えない場合は別です。
2 地中埋設物の問題が売主の責任と言える場合、次のケースに当てはまれば地中埋設物の撤去に代わって損害賠償を請求できます。
(2-1)地中埋設物の撤去が不可能なケース
(2-2)売主が地中埋設物の撤去を明確に拒絶したケース
(2-3)地中埋設物の問題により土地の売買契約が解除されたor解除できるケース
第416条 損害賠償を請求する権利は、地中埋設物の問題で発生した損害の埋め合わせを目的としています。
2 仮に地中埋設物の発見について特別な事情があったとしても、売主が想定しておくべきだったケースでは、買主が売主に損害賠償を要求できます。
第417条 損害賠償の方法は、特に取り決めをしない限り金銭で支払うものとします。
具体的な金額についてはケースバイケースで、地中埋設物によってどのくらいの損害をこうむったのか、ある程度の根拠を示してくるでしょう。
4-4.売買契約の解除(民法第564条、民法第541~542条)
地中埋設物がどうにもならない場合において、買主は売主に対して売買契約を解除することがあります。
契約解除については民法の第541条と第542条に規定されているので確認しましょう。
民法 第541~542条【クリックで全文表示】
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
【今回のケースに合わせた意訳】
第541条 売買契約の当事者が契約を果たさない場合、もう片方の者は予告してから一定期間の後に契約を解除できます。
例えば地中埋設物が発見され、1週間以内の撤去など問題が解決されない場合、買主は売主に対して契約を解除可能です。買主がきちんと代金を支払わないなどのケースでも解除できます。
ただし常識的に見て、あまりに些細な不具合(言いがかりレベル)については解除する権利を認めません。
第542条 次の場合については、予告なしで契約解除が可能です。
(1)地中埋設物をすべて撤去できない場合
(2)売主が地中埋設物の撤去を明確に拒絶した場合
(3)売主が地中埋設物の撤去を一部拒絶して、残り部分では契約目的を果たせない場合
(4)一定の期間より早く、地中埋設物を撤去しないと契約目的を果たせない場合
(5)その他、地中埋設物の撤去を要求してもムダだと明らかな場合
2 次の場合は、買主が予告なしで売買契約を一部解除できます。
(1)地中埋設物の撤去が一部できない場合
(2)売主が地中埋設物の一部について撤去しないと明確に意思表示した場合
「まぁそりゃそうですよね」と思われた方が多いでしょうが、こういうこともきちんと決めておかないとトラブルになるのが人間というものです。
決めておいてさえ、法律の解釈をめぐって争いは絶えないのですから……。
4-4-1.買主に責任がある場合は解除できない(民法第543条)
ところで言うまでもありませんが、地中埋設物に問題について買主側に責任がある場合は解除できません。民法543条を見てみましょう。
民法
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
【今回のケースに合わせた意訳】
買主が原因で地中埋設物が撤去できない場合は、買主から契約解除することができません。
民法の条文が個別に作られているということは、悪質な買主が自分の責任を棚に上げて言いがかりをつけるケースがよほど多かったのでしょうね。
地中埋設物について、そういうケースは考えにくいと思いますが。
4-4-2.契約解除は全員が、全員に対してしかできない(民法第544条)
売買契約の当事者が1対1なら関係ありませんが、売買契約の当事者が片方または両方とも複数の場合があります。
例えば土地を共有しているなど売主が複数だった場合、契約解除は売主の全員に対して行わなければなりません。
また買主が複数名だった場合、買主の一人だけで契約解除することはできません。
民法
(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
一部だけ契約解除を認めてしまうと、権利関係が複雑になってしまうから、当たり前と言えば当たり前ですね。
4-4-3.売買契約が解除されるとどうなるの?(民法第545条)
売買契約が解除されると、そもそも売買契約が存在しなかった状態になります。
契約解除の効果については民法第545条に規定されているので確認してみましょう。
民法
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
【今回のケースに合わせた意訳】
第545条 売買契約が解除された時は、買主も売主も契約がなかった元通りの状態に戻さなければいけません。ただし元通りと言っても、第三者の権利を侵害することはできません。
2 売買契約の解除で金銭を返す時は、受け取った時からの利息を追加しなくてはいけません。
3 金銭以外のものを返す時は、受け取った時から収穫した「果実」も返さなくてはいけません。
4 契約を解除しても、損害が発生しているなら損害賠償も請求できます。
「果実」と聞いてフルーツを想像するかも知れませんが、法律的に果実という場合は以下の2パターンがあります。
(1)天然果実……例えば農地で採れたフルーツや鶏が生んだ卵など、いわゆる自然の恵みです。自然果実と呼ぶ方もいますが、同じ意味になります。
(2)法定果実……例えば家賃収入や貸金利息のように、法律的に生み出される権利や利益を指します。
基本的にはこれらも返さねばなりません。ただ今回は地中埋設物が原因で土地の売買契約を解除するケースなので、そこまで深く考えなくて大丈夫でしょう。
4-5.その他の法的責任(廃棄物処理法第16条など)
地中埋設物の問題について、買主から問われる法的責任のほか、不法投棄などの法律責任を問われる可能性も否定できません。
例えば廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)には、こんな条文が定められています。
廃棄物処理法 第16条
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
地中埋設物が廃棄物であるか否かは廃棄物処理法第2条の定義を確認してみましょう。
廃棄物処理法 第2条
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 (以下略)
条文中「その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」とあるため、常識的に捨てられたと見なされる価値のないor極端に低いものを包括しています。
4-5-1.地中埋設物の放置≒不法投棄のペナルティは?
【回答】5年以下の懲役刑か1,000万円以下の罰金刑。悪質なら両方の刑罰を科せられることも
今回の地中埋設物が廃棄物に当てはまる場合、正式な手順を経ず(みだり)に捨てた場合、罰則が設けられているので注意しましょう。
廃棄物処理法 第25条
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
(中略)
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
【今回のケースに合わせた意訳】
みだりに廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役刑か1,000万円以下の罰金刑、またはその両方の刑に処します。
みだりに廃棄物を捨てようとしたけど、未然に防がれた者についても、同様に罰します。
地中埋設物の放置が不法投棄と見なされた場合、こうした思いペナルティが用意されているのです。
「そんなのバレやしないから大丈夫」などとタカをくくらず、地中埋設物があると知っているなら早めの撤去を心がけましょう。

5.地中埋設物の法的責任(不動産会社)
地中埋設物の責任については、売主だけでなく土地の売却を仲介した不動産会社も問われることがあります。
どんな責任が問われるのか、見ておきましょう。
5-1.信義則上の調査義務(民法第1条2項)
これは法的責任と微妙に違うかも知れませんが、民法にこんな条文があります。
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
【意訳】個人の権利は、社会に迷惑がかからない範囲で行使しなければいけません。
2 権利を主張したり義務を果たしたりする時、信頼関係を壊してはなりません。
3 権利をみだりに主張してはいけません。
この第1条2項を「信義則(しんぎそく。信義誠実の原則)」と呼び、仕事の上で求められるプロ意識やクオリティの原則となっています。
今回の地中埋設物に当てはめるなら「土地に地中埋設物があることを、なぜちゃんと調査しなかったのか?」などと買主から追及されるかも知れません。
基本的に、売買した物件の契約不適合責任は売主が負うのですが、仲介した不動産会社も信義則から責任を問われるケースが考えられます。
5-2.宅地建物取引業法上の重要事項説明義務(宅地建物取引業法第35条)違反
不動産取引を仲介する宅地建物取引士(宅建士)には、物件の売買契約に際して重要事項を説明し、内容を記した書面を交付する義務があります。
宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(以下略)
この重要事項説明(略して重説と呼ばれることが多い)は、買主が不動産の売買契約を結ぶか否かを判断する上で、重要な基準となる情報を提供するものです。
なので、契約する土地に地中埋設物があるか否かは重要事項説明に含められるとみていいでしょう。
もし重要事項説明において地中埋設物の説明が不十分だった場合、宅地建物取引業法第35条に違反する可能性が考えられます。
重要事項説明を怠った(不十分だった)ことについて刑事罰はありませんが、行政庁から以下の監督処分を受けるかも知れません。
(1)指示処分……宅地建物取引業法第65条1・3項
(2)業務停止余分……宅地建物取引業法第65条2項2号、4項2号
(3)免許取消処分……宅地建物取引業法第66条1項9号
※参考:重要事項説明義務違反に対する監督処分-公益社団法人 全日本不動産協会
不動産会社もプロですから慎重を期して臨むとは言え、こうしたリスクをできればとりたくないもの。
そのため、地中埋設物がある不動産の売却仲介には及び腰な傾向がみられます。
6.地中埋設物のトラブルを回避する方法
さて、ここまで地中埋設物を放置したまま売却してしまうリスクについて解説してきました。
こうした地中埋設物のトラブルは、なるべく回避したいですよね。
ここでは地中埋設物のトラブルを回避する方法について解説しましょう。
- 6-1.地中埋設物を撤去するのが理想だが……
- 6-2.重要事項説明であらかじめ告知しておく
- 6-3.地中埋設物があるか、よく分からない場合(事前調査の方法・費用)
- 6-4.買取り業者に買取りしてもらう
6-1.地中埋設物を撤去するのが理想だが……
地中埋設物を発見したら、撤去するのが理想です。なのですが……地中埋設物の撤去には先立つものが必要となります。
地中埋設物の撤去費用相場は、材質によって異なるためあらかじめ確認しておきましょう。
| コンクリート片 | 12,000円~/㎥ |
| 瓦・レンガ | 22,000円~/㎥ |
| 木片 | 5,000円~/㎥ |
| 石膏ボード | 12,000円~/㎥ |
| カーペット | 15,000円~/㎥ |
| タイル | 25,000円~/㎥ |
| サイディング | 25,000円/㎥ |
| 井戸の解体・埋め戻し | 30,000~50,000円/一式 |
| 浄化槽の撤去 | 30,000~70,000円/一基 |
※ここにない地中埋設物については、似たような材質・質量のものを参考にして下さい。
また、地中埋設物の撤去だけでなく搬出するためのトラックを用意する場合に別料金が発生する場合もあります。
| 2tトラック | 18,000円~/台 |
| 2tコンテナ | 18,000円~/台 |
| 3tダンプ | 20,000円~/台 |
| 4tコンテナ | 22,000円~/台 |
| 4tトラック | 25,000円~/台 |
更に、地中埋設物の形状や大きさによっては掘り出し、吊り上げるための重機が必要となるかも知れません。
| バックホー(ユンボ) | 7,000円~/日 |
| クレーン(ユニック) | 16,000円~/日 |
ここまで大がかりな地中埋設物もあまりないとは思いますが、なんせ表からは見えない地中のことなので、思わぬ出費がかさんでしまうリスクは織り込んでおきたいところです。
6-2.重要事項説明であらかじめ告知しておく
地中埋設物の撤去が難しいと判断された場合、いっそのこと「地中埋設物があります」と正直に告げてしまう=重要事項説明で伝えておく手もあります。
地中埋設物が問題となるのは、大抵「黙っていて、後からバレた」ケース。事前にきちんと伝えておけば、後からトラブルに発展するリスクは抑えられます。
ただし「地中埋設物があるなら、後で撤去するかも知れないし、それらの費用も織り込んで安くしてよ」と言われてしまうかも知れません。
いや、十中八九言うでしょう。隙あらば値引き交渉のネタを狙っているのが買主というものです。
売却に際して不利になるから、地中埋設物についてどうしようか迷っている方が多いのだと思います。
それでも、後から起こるかも知れないトラブルに怯えながら暮らすことを考えれば、気が楽になるメリットの方が大きいでしょう。
6-3.地中埋設物があるか、よく分からない場合(事前調査の方法・費用)
売却しようと思っている土地に地中埋設物があるのかないのか、そもそもよく分からないケースは多くあります。
よく分からないまま売却してしまい、後から地中埋設物が発見されたら一大事。だから事前に調査しておくのがおすすめです。
それでは、地中埋設物の調査方法と費用について解説しておきましょう。
6-3-1.地歴調査
地歴調査とは、文字通り土地の履歴を調べる方法です。
古い地図や地質図・地形図・地理図・登記簿・航空写真などを調査して、過去にどんな建物が建っていたのか≒地中埋設物がありそうかを検証していきます。
もっとも簡単な方法と言えますが、あくまで現地を見ていない推測に過ぎないため、これだけで完結することはできません。
とは言え、続いて紹介する調査方法の見当をつける上では有効なサブ手段と言えるでしょう。
地歴調査の費用は、かかる日数と人件費などから5~10万円程度が相場となっています。
6-3-2.地中レーダー探査(非破壊検査)
地中にレーダー(電磁波)を照射し、地中埋設物があれば探知できる方法です。地面を掘削しない非破壊検査なのでシンプルな反面、ボーリング調査に比べて信頼性では若干劣ります。
地中レーダー探査の相場は探査範囲によって異なるものの、一般的な戸建て住宅程度の土地(2~4人暮らしで約75~125㎡)で10~15万円程度です。
6-3-3.ボーリング調査
地面を直接掘ることで地中埋設物の有無を確かめる方法です。
ドリル状のボーリング機械で掘り下げた後、ハンマーを打ち込んで沈んだ深さや打撃回数によって地質を見極めます。
地歴調査や地中レーダー探査に比べて制度が高いため、地質が問われる場所では多く使われるものの、費用は25~30万円ほどと相応に高めです。
6-3-4.不明なら不明で「調べたけど発見できなかった」ことを告知しておく
さて、調査したけど地中埋設物が発見できなかった場合は、どうすればいいのでしょうか。
そういう時は正直に「地中埋設物については、調査したけど確認・発見できなかった」と買主へ伝えることが大事です。
後から発見された地中埋設物の状況や種類によっても異なりますが、少なくとも何もしなかった訳ではないと主張できるでしょう。
考えうるリスクはすべて事前に想定し、手を打っておくことで防げるトラブルは多いものです。
6-4.買取り業者に買取りしてもらう
地中埋設物が不安な不動産を売却したいなら、買取り専門業者に依頼するのがいいでしょう。
買取り業者のメリットは大きくこちらです。
6-4-1.地中埋設物をそのままで売却できることがある
地中埋設物がある不動産を買取専門業者に売却する場合、地中埋設物をそのままで買い取ってくれることもあります。
もちろん撤去費用などは差し引かれますが、煩雑な撤去作業を丸投げできる労力の節約は大きなメリットと言えるでしょう。
地中埋設物で悩んでいる不動産を持て余しているなら、この機会に売却してしまいたいですね。
6-4-2.仲介手数料がかからないこともある
不動産会社に売却を仲介してもらう場合、仲介手数料が発生します。
一方で買取専門業者に直接売却すれば、仲介ではないから仲介手数料が発生しません。
しかし買取りを謳っている業者の中には、自社で買取りをせず、他者へ仲介しているところもあります。
その場合は仲介手数料が発生してしまうので、自社で買取りしているかをあらかじめ確認しておきましょう。
6-4-3.契約不適合責任を免責にしてくれることも
個人を相手に売却する場合、地中埋設物による契約不適合責任を問われてしまうことがあります。
一方で買取専門業者であれば、地中埋設物があっても契約不適合責任を免責にする特約で不動産を売却できるケースもあるのです。
せっかく不動産を売却できても、後から地中埋設物を理由に契約不適合責任を問われたらたまりませんよね。
契約不適合責任が免責になる一点だけでも買取専門業者を検討する価値はあるでしょう。
7.地中埋設物のある不動産でお悩みならURUHOMEへご相談を
以上、地中埋設物のある不動産の売却について徹底解説してきました。地中埋設物の問題
解消は大変なことがご理解いただけたのではないでしょうか。
地中埋設物のある不動産でお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年の創業からニッチな不動産一筋。神奈川県・東京都を中心に日本全国で地中埋設物のある不動産などを数多く取引してまいりました。今回も、地中埋設物でお悩みの皆さんに役立てると思います。
買取査定は完全無料。最短のケースでは、ご依頼から2時間で査定完了、2日で売却できました。
地中埋設物のある不動産をスピード売却&現金化したいとお考えでしたら、ぜひ一度ドリームプランニングまでご相談くださいませ。